昭和の大スターである笠置シヅ子だが、家族思いで世話焼きな女性だった。著述家の柏耕一さんは「笠置は大阪で養母うめに大切にされて育ったが、うめが死ぬまで、生母ではないということを知らないふりをした。こうと決めたら揺らがない一本気な性格だから、それができたのではないか」という――。
※本稿は、柏耕一『笠置シヅ子 信念の人生 』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。
14歳で松竹少女歌劇団に入り「豆ちゃん」と呼ばれる
数え14歳で大阪の松竹少女歌劇団に入り、背の低い笠置は「豆ちゃん、豆ちゃん」と呼ばれた。
笠置自身の解説では、「私は大体元来が世話焼きでして、また身体が小さくてちょこちょこ動き回るものですから、大阪の花柳界にちいさいまげをひっつめて木綿の着物をきて芸者衆やかみさんなんかの用事をする豆奴まめちゃん というものがありますがそこからきたのでしょう」(自伝 より)
となる。だが万事、完璧にやろうとすれば、体も心も悲鳴をあげてくる。
真冬に洗い物をしているときなど笠置は、松竹楽劇部を何度やめようと思ったか、と回顧している。実際、彼女の指の節が高くなっているのは、このときの苦労である。
笠置は気働きに長け、誰からも重宝がられた。いいか悪いかわからないが、新人が入ってきても、幹部たちは「豆ちゃんでなければダメ」という始末だった。
笠置は、この部屋子をとうとう5年間務めた。それもこれも、笠置にいわせると理由があった。つまり、歌劇団へ入団テストを受けてまっとうな入り方をしたわけではないので、人一倍辛抱しなければならない、と自分にいい聞かせたのだ。
先輩たちにかわいがられ、やっかみの声も気にしなかった
笠置のこの根性は、以降、松竹楽劇部内部でいかんなく発揮されていく。いまの時代は違うが、当時は保守的で、新人が舞台で役らしい役をもらえるようになるには、時間も忍耐も必要とされていた。実力があるだけではダメなのである。
笠置は考えた。まず、先輩にかわいがられること。つぎに、休演者が出たときすぐ代役がつとまるよう、舞台袖そで で目を皿のようにして全部の役柄を覚えるようにした。
もちろん、楽屋の雑用も人を押しのけてまでこなすようにした。その結果、休演者が出れば、先輩たちが文芸部にかけあって、笠置を推薦してくれたのである。こうなると、同期などから「やっかみ」を買うこととなる。さかんに陰口をいう者もいた。しかし笠置は、いっさい気にしなかった。
それもこれも、自分を入団させてくれた松竹の音楽部長・松本四郎への恩義に報いるためであり、父母にも申し訳を立てたいからだった。
笠置本人の語るところでは、同期生が廊下ですれ違って挨拶あいさつ してきても、これを無視することがあった。筆者の考えるところ、これは笠置の意地悪な気分がすることではなく、同期生や後輩など、まるで眼中になかったのである。とにかく早く一人前になること、それが先決だった。
芸名は「三笠静子」だったが宮家と同じ名前になり変更
笠置の初舞台は昭和2年(1927)の「日本新八景おどり」のレビューで、岩に砕ける水玉だった。芸名は近所のもの知りが、三笠静子みかさしずこ とつけてくれた。
踊りの素養があるため舞踊専科に配属されたが、笠置は後年、自分の小さな体から舞踊は不利だと悟り、歌に転じることとなった。
それにつれて芸名も、笠置シズ子と改めることとなった。一つ大きな理由として、天皇陛下の弟宮である澄宮すみのみや が「三笠宮家」を創設したため、それに配慮してのことでもあったという。
「好かんな、あの子、少女歌劇の夢も美もあらへんわ。ガサガサで、えげつのうて、厚かましうて……」(自伝 より)
笠置はしょっちゅう声をつぶしていたが、どうやら彼女の舞台を観て、一部のファンの中には、そんなことを思う人もいたようである。
入団当初、カン高い声でがむしゃらに歌っていた笠置だけに、年じゅう声をつぶしていた。のどに包帯を巻いているのがトレードマークのようになっていた。
そんな笠置も、声楽専科に転じて歌うようになると、これが思わぬ健康法になったようだ。それまでは2週間の公演では、のどのみならず体力的にも持たなかったが、とても丈夫になったのである。
「笠置君は頭のてっぺんから声を出していた」と言った服部良一
この頃の笠置について、服部良一の次のような証言もある。
「私が知り染そ めた頃の笠置君は頭のてっぺんから声を出していた。地声で歌うようにいったが『ラッパと娘』などもまだ三オクターブくらい高かった。だから初日になると声をつぶして医者にかかり、いつも筆談で用を足していた。それが段々地声がイタにつくとともに咽喉が丈夫になった」
服部は、「先進諸国の人のように肉体的に生活文化的に声のボリュームが望めるなら兎と も角かく 、日本人が『つくった声』を出していると滅びるのが早い」という考えの持ち主であった。あわせて、エンターティナー、歌手としての笠置に対する服部の評価を引用してみたい。
「……彼女は鮮烈なパーソナリティと自己演出とを合わせて一本になる歌手である。歌そのものからいえば、もっとうまい人がいくらでもいた。だが、いろいろなものを合わせると彼女ほど大衆の心理をつかむ歌手はいない」 「……洒落しゃれ たところで洒落た人たちだけに洒落た歌を聞かせるたぐいの人ではない。あくまでもゴミゴミした街の中で、大衆の灯となって歌う陋巷ろうこう の歌い女である。そこに彼女の生命があり、魅力がある」
陋巷とは、「狭く汚い路地。貧しくむさくるしい裏町」のことだ。当時、笠置は服部からよくいわれたそうである。
「君の声は色気がないな。電話で、わて笠置だす、といわれるとお座がさめるよ」
「少女歌劇の異端児」だった笠置には東京が合っていた
先述した、松竹歌劇ファンの言葉が的外れでないことは、笠置自身も認めていた。「夢や希望」を松竹歌劇に求めていた人たちには、笠置は異質だったのだろう。
笠置本人も「ただ田舎者の向う見ずで、世に出ることばかりを考えていた私に、どうして夢や美がありましょう。最初から私は少女歌劇の異端児だったのかもしれません」と自伝 にある。
ともあれ、松竹歌劇団の生活をあと先考えずに送っていた笠置にも、少しずつチャンスが巡ってくるようになった。
昭和12年(1937)春、笠置は東京の国際劇場の「国際大阪踊り」に出演した。このとき笠置は幹部どころの出番で、「羽根扇はねおうぎ 」を歌った。これが東京の松竹幹部の目に留まったのである。
翌年、笠置は東上することになった。
かわいがっていた義理の弟が23歳で戦死してしまう
ところで、笠置の当時の家庭の状況はどうであったか。
亀井家は、笠置をのぞいて7人の子が生まれたが、末弟の八郎以外みな早逝そうせい していた。八郎は昭和12年(1937)当時、19歳になっていた。
家業の風呂屋もその権利を売って、家族はその手持ちの金で生活していたようだ。笠置は、父親の道楽で借金のカタにでもなっていたのではないかと推測している。とはいえ、病弱な母うめをかかえて父子が無職というわけにもいかず、天王寺の東門近くに散髪屋を開業した。そんな状況なので、笠置も月々の手当80円の大半を家に入れていた。笠置はお汁粉屋しるこや に入るのさえ、ためらわざるを得なかった。
そうこうするうちに八郎は、満州事変から中日事変へと戦雲が拡大するなか、四国丸亀の師団に入隊することになった。
だが後に太平洋戦争が勃発して、最愛の八郎は昭和16年(1941)12月に、仏領インドシナ(現在のベトナムやその周辺)で戦死してしまった。
八郎から入隊時に「あとは頼む」と託されていたとはいえ、笠置は実質的に一家の大黒柱となる。
笠置シヅ子は抜群に記憶力がいい。彼女の自伝を読むと、それがよくわかる。描写がきわめて細かいのである。会話の細部まで昨日のことのように鮮やかである。まして、自分にとって大事な人の話となれば忘れようがない。
笠置と親しい人によると、笠置は10年前のことでも20年前のことでも期日から時間まで、じつによく覚えているそうである。
養母うめの死に目に会えず、養母は執念の言葉を遺した
もう一つ笠置の特徴は、こうと決めたら突き進む一本気な性格にある。
母うめが亡くなったのは、昭和14年(1939)9月11日のことである。その前、東京の公演があり、主要キャストの笠置は代役がおらず、母が危篤きとく 状態になっても大阪へ帰ることができなかった。
うめが今日か明日かの命になったときのこと。周囲の者が「大役がついて帰れない」という笠置の電報をうめに見せると、
「そんなら、あの子も東京でどうやらモノになったのやろ。わてはそれを土産にしてあの世に行きまつけど、わてが死に目に逢うてない子を、生みの親の死に目にも逢わせとない。わてが死んだあと、決して母が二人あることを言うておくれやすな」
と、きっぱり言ったそうだ(自伝 より)。うめの執念か、はたまた業ごう だろうか。
笠置は笠置で、これはこれでよかったと思っている。死に目には会えなかったが、生みの親など知らないとシラを切り通せたのだから。
笠置を愛情深い一本気な女性と評した喜劇王エノケン
大戦期前後の国民的な喜劇王のエノケンこと榎本健一は、笠置を評して「生一本きいっぽん の人」と呼び、「舞台と楽屋の裏表がない」と褒めている。
いつでも捨て身で気どりのない笠置のことが、エノケンは好きなのだ。笠置はこうと決めたら、こざかしい真似まね はしない。親を守ると決めれば、自分を捨てても死ぬまで面倒を見る。
弟・八郎のためなら、軍隊を退役したあとのことを考えて、松竹退団の際の退職金すべて、1000円近い金を定期預金にして渡そうとしていた。
笠置は、これまでもそうだが、これからもそうやって生きていくつもりだった。
パワフルな歌声で知られる「ブギの女王」笠置シヅ子。シヅ子についての本を書いた柏耕一さんは「笠置の舞台上での底抜けの明るさは、自伝に『生まれながらに父を知らぬ』『陽かげの子』と書いた生い立ちとも関係がある。10代のとき自分が養子であることを知り、実母に会いに行ったが、養母うめに対する後ろめたさもあったようだ」という――。
※本稿は、柏耕一『笠置シヅ子 信念の人生 』(河出書房新社)の一部を再編集したものです。
出生について「父を知らぬ陽かげの子」と綴ったシヅ子
どんな平凡な人生にも、ドラマの一つや二つはある。まして笠置は、一世を風靡ふうび した大スターである。
「私の半生には幾つもの因縁がついてまわっております。誠にわれながら宿命の子だと思います。(中略)その因縁の一つは、私も、私のたったひとりのエイ子も陽かげの子なのです。生れながらにして父を知らぬ不幸なめぐり合わせは、奇しくも母子二代にまたがっているわけです」
この文章は笠置シヅ子の唯一の自伝的著書『歌う自画像私のブギウギ傳記 』(昭和23年刊)の書き出しである。
人気絶頂時の華やかな大スターとしては、およそ似つかわしくない告白ではないか。「陽かげの子」という表現は、たとえそれが事実だとしても、いまも昔も人気商売のスターなら避けたいフレーズであろう。
こうした表現をこだわりなく平気でつかう笠置には、その飾らない人柄と自信が見てとれる。
以下、自伝に詳細に綴られていく彼女の複雑で因縁めいた半生は、華やかな大スターの陰の部分である。
笠置は大正3年(1914)8月25日に、四国の香川県大川郡相生村(現・東かがわ市)に生まれている。
1914年といえば、第一次世界大戦(イギリス・フランスなどの連合国と、ドイツを中心とした中央同盟国との戦争。1918年に終戦)が勃発した年であり、アジアの端っこに位置する日本の四国にあっても、世界をおおう重苦しい空気とは無縁ではなかった。
非嫡出子として生まれ養子に出されたからこそスターに
笠置の出生しゅっしょう は、誰にも望まれぬものだった。というのも生母は、近在の富農の家で女中奉公をしていた。笠置は、母とその家の若い跡取り息子との間にできた結晶だった。母はまだ18歳か19歳だった。
しかし、結果的にはたかが奉公人の小娘と、「白塀しろべい さん」と呼ばれるほど白い土塀がつづく旧家の家柄からして、身分違いの私通だった。
その後、母は富農の家長から因果を含められて暇を出された。奉公先から遠からぬ引田町の実家に身を寄せた娘は、女児シヅ子をひっそりと産んだ。
元来、虚弱だった父も、笠置が生まれた翌年に22か23歳の若さで死んだ。
この引田町というのは播磨灘に面する港町で、醬油醸造で栄えた古い町並みがいまも残る。町の西側を清流が流れ、榛の木の樹陰にシヅ子の生家があった。この女児が、曲がりなりにもその地で成人していたとすれば、後年の笠置シヅ子は誕生しなかったはずである。
まだ10代の実母は乳が出ず、里帰り出産した養母が授乳を
さて、どんなことが笠置の運命の転換点になったのだろうか。それは乳児をかかえて賃仕事ちんしごと をして、家計を切り盛りしていた笠置の実母が、乳の出が悪かったことにあった。
乳呑児ちのみご に一日じゅうピイピイ泣かれては、仕事もはかどらない。そんなとき、亀井うめという大阪に嫁いでいた女性が、出産のため引田町の実家に里帰りしていた。次男を無事に生んだうめは、どういう経緯いきさつ があってかはっきりしないが、親切にもシズ子のために哺乳を買って出てくれたのである。
後年、笠置はうめのことを「義侠心ぎきょうしん がある」と評しているが、そんな心で授乳を引き受けたのだろう。
うめは、引田町の多額納税者でメリヤスと手袋工場を経営する中島家当主の妹だった。人情家で世話好きのうめは、大阪で薪炭しんたん や米・酒をあつかう仕事をしていた亀井音吉と所帯を持っていて、すでに長男もいた。
哺乳が2カ月もつづいた頃には、情も移り手放すのが惜しくなるのは人の常である。うめにとっては男の子二人に女の子だから、余計そんな気持ちが強くなってきたのかもしれない。
笠置は養母うめのことを「義侠心がある」と評した
いっぽう、生母としてみれば若い女の身空みそら で乳児をかかえ、田舎町で生計を立てていくという境遇は、今日でも決して楽ではないであろう。ましてや時代は大正である。
たぶん、親のすすめもあったのだろう。生母は、笠置を手放す決心をしたのである。
いっぽう、裕福というほどではないうめが、笠置を「可愛いから」「情が出て」という理由だけで、夫に相談もせず養子にするのだろうか。
この点に関して笠置は、養母の気持ちを自伝の中でこう推量している。
「養母の気持ちは今もってわかりません。決して私が別れ難ないほど可愛らしい子供だったとは思えませんので……」
と書くが、それでも持病の心臓脚気があるうえ、実の子の育ちもいまひとつで、何かのときの頼みに自分をもらう気になったのかもしれない……と想像する。
筆者の考えるところ、どれも間違いではないだろう。いまと違って子どもは労働力という時代でもあった。
笠置が生まれて半年たつ頃、うめは同年生まれの次男の正雄といっしょに、彼女を大阪へ連れて帰ることとなった。
養母はシヅ子に血のつながりがないと知られたくなかった
実子として笠置に愛情をそそぐうめには、大きな悩みがあった。娘に出生の秘密を知られることだけは、何があっても避けたかったのだ。
二人がずっと大阪にいれば問題はないが、うめはことあるごとに香川の実家に帰らなければならない。
相生村の「白塀さん」の家にも、大正4年(1915)に亡くなった跡取り息子の法事があるので毎年、出席していた。そのうちうめは、物心がついた娘のミツエに、出生にまつわる隠し事がいつバレるかと、大いに怖れるようになった。そのためうめは、ミツエが8歳になって以降は「白塀さん」の法事にも顔を出さなくなった。親せき縁者にも固く口止めしたことはいうまでもない。
7歳くらいだったか笠置には、父の位牌が飾られた「白塀さん」の仏壇の前で、お得意の「宵や町」を踊り、参会者に拍手された記憶が残っている。老いた祖父の目には、涙がにじんでいるように笠置には見えた。
ある日、笠置は養母がひた隠しにしていた出生の秘密を知ることになる。
笠置は自伝にこう書く。
「私はお蔭で大阪の松竹歌劇に入るまで、なんの疑惑も懊悩おうのう もなく、ただやさしい養母に甘えるだけ甘えて平和に過ごしてきましたが、18歳の秋に、とうとう私の秘密を知ってしまいました。多感な娘ごころに、これは大きな衝動でした」
香川で貧しい暮らしをする実母との一度きりの対面
笠置に実母がいたことが、なぜ彼女に知られることになったのだろうか。
笠置が18歳の夏のこと。松竹少女歌劇の団員だった彼女は、気管を悪くして休団していた。そこで養母は、笠置と8歳下の弟の八郎を連れて、郷里からさほど遠くない白鳥という白砂青松はくしゃせいしょう の海辺に避暑をかねて出かけたのである。
そんな折に、うめは兄の中島から「今年は白塀さんの息子の十七回忌だから唯一血のつながっている娘の静子を連れて出席するよう、白塀さんから強く頼まれている」と強要されたのである。
うめは抵抗したがかなわず、娘だけ法事に出席させて、大阪に残した夫からの矢の催促で八郎と共に帰阪した。
その結果、笠置は法事の席で、事情を知る年寄りが自分に向かって話す無神経な言葉で、「白塀さん」の家とは血のつながりがある、という疑念を抱くに至った。
中島の家にもどった笠置は、叔母を問い詰めて実母の存在を知ることとなった。
養子に出された人が実の親を追い求める強い気持ち
実父母を求めるこの気持ちは、他人にはうかがい知れないものがある。笠置は自伝で、その苦悩と逡巡しゅんじゅん を率直に書いている。笠置の舞台上での底抜けの明るさは、この闇の深さとも関係あるに違いない。
笠置に強談判こわだんぱん されて、叔母が打ち明けた結果、彼女の心は晴れたのだろうか。決してそうではなかった。その複雑な胸中を自伝において、こう吐露とろ している。
「私はやっぱり聞かなければよかったと後悔しました。血肉をわけた母がきのう同じ法事の席に連らなり、またこの近くに住んでいるとわかると、どんな意外な事実を聞こうとも、いまの養母に対する気持ちは変わらぬという自信で聞き出してきた私の身構えがぐらついてきたのです」
18歳の娘である。揺れる娘心が手に取るようだ。このあと笠置は、近在に住む実母と対面を果たすことになる。
実母に会おうとする決断には、理由づけが必要だった。
人間の本能として、実母を求めることは自然の感情である。とはいえ、養母うめに対する後ろめたさもある。
なにしろ養母は、実母の存在をこれまで笠置に、ひた隠しに隠してきたからである。笠置も、養母のその気持ちは痛いほど理解できた。
笠置は心の中で、こう折り合いをつけた。
シヅ子が百日咳にかかったとき懸命に看病してくれた養母
自分が百日咳ひゃくにちぜき で生死の境をさまよったとき、帯をひと月も解かずに看病してくれたお母さん、娘が死ねば自分も死ぬといってくれたお母さん、どんな人が出てこようと、お母さんはたったひとりだ……と。
半面、はたして実母はどんな人なのだろう、どんな人が出てこようが、自分さえしっかりしていれば問題はないはず……。
あれこれ考えるうちに笠置は、実母と会うことで母に対する気持ちの変化はないと確信したのだろう。実母を知りたいという気持ちに、功利的なものは一切ない。実母との対面は、後にも先にもこのとき一回きりである。
仕立てを生業なりわい とし、6歳くらいの男の子がいて、笠置への負い目を見せる実母と会い、笠置は、これはこれで得心したのではあるまいか。
実母と養母との間で揺れる心というよりは、実母と養母への自分の距離感を確認して、心の平安が得られたといっていいかもしれない。
実母との別れに際し、笠置の手には金無垢(純金)の置時計の入った小箱が握られていた。実母いとが、生前の夫(笠置の実父)から贈られたものだった。
昭和歌謡界華やかなりし頃に「ブギの女王」として活躍した笠置シヅ子だが、私生活では肉親の愛に恵まれなかった。作家の青山誠さんは「シヅ子(静子)の両親は大阪で銭湯を営んでいたが、実はシヅ子は養母が故郷の香川でもらい受けた養子だった。シヅ子は17歳のとき、その事実を知って人生最大の衝撃を受けた」という――。
※本稿は、青山誠『笠置シヅ子 昭和の日本を彩った「ブギの女王」一代記 』(角川文庫)の一部を再編集したものです。
松竹少女歌劇で活躍しはじめた17歳の静子は香川県へ
昭和6年(1931)、静子(のちの笠置シヅ子)は17歳になった。女学校に入学していればそろそろ卒業を迎える頃、親類や知人から縁談話が持ち込まれる年齢である。しかし、彼女は歌の練習と舞台に明け暮れる忙しい日々、異性に関心を抱く余裕すらなかった。
研修生から楽劇部に正式採用されて、いまや松竹少女歌劇の舞台には欠かせない存在になっている。この世界で生きてゆくために、歌の練習にはいっそう熱心に取り組んだ。重要な役を任されることも増え、舞台稽古にも長い時間をとられるようになっていた。2週間に及ぶ公演が終わった頃にはいつも心身ともに疲労困ぱいして倒れそうになる。
もともと体が丈夫なほうではない。オーバーワークがたたり、気管支を悪くして寝込んでしまう。当分の間、舞台を休演するしかない。心配した母親のうめは静子と弟の八郎を連れて帰郷することに。大阪にいるよりは、空気のきれいな四国でしばらく静養させたほうがいいと考えたようだ。
香川県の引田ひけた から5~6キロほど西に、白砂青松はくさせいしょう の美しい眺めが広がる景勝地・白鳥しろとり 海岸がある。昭和時代に入って付近に駅が開設されると、行楽客が増えて駅前には旅館や土産品店が建ちならぶようになった。うめは実家に寄らず、ここで親子3人滞在することにした。
静子の実父は村一番の名家の跡取り息子だった
今回の帰郷について、親族たちには告げていない。静子の生家である三谷家に知られるのを避けたかった。静子が産まれて間もなく、実父の三谷陳平は病に倒れて亡くなっている。すると、静子の存在を無視していた三谷家の態度が豹変ひょうへん 。実家に帰省する都度、彼女を屋敷に連れて来るよう催促するようになった。
静子の祖父・三谷栄五郎は乃木大将のような長い白髭しらひげ をたくわえて、威厳を感じさせる人物だった。静子が習ったばかりの唄や踊りを披露すると、その時だけはこの老人も厳しい風貌ふうぼう を崩してデレた笑顔をのぞかせる。亡き息子の忘れ形見。そう思うと情が湧いてくるのだろう。
しかし、静子が成長するにつれて、うめは色々と理由をつけて屋敷に行かせるのを断るようになった。小学校に入ってからは三谷家に行った記憶がない。
うめは静子が自分の出生の秘密を知ることを恐れていた。ともある。伯父はそれを避けたかったのだろう。
実の祖父とは知らずに三谷家の当主から法事に呼ばれた
執拗しつよう な説得に、うめもとうとう屈した。静子が法事に出席することを了承してしまう。間が悪いことに夫の音吉から早く戻ってくるように催促がきて、静子をひとり残しうめは八郎を連れて先に大阪へ戻ることになった。自分が見ていないところで三谷家の親族たちが静子に何か吹き込んだりしないかと、不安でしょうがなかったのだが。銭湯の商売は忙しく、自分がいつまでもここに居るわけにはいかない。
静子はひとりで残り、引田の伯父宅で寝泊まりしながら法事に出席することになった。久しぶりに訪れた屋敷に入ると、広間を埋め尽くして大勢の人々が座っている。豪華な料理もふるまわれた。じつはこの屋敷は借金のために人手に渡っており、祖父たちは隣の小さな離れに住んでいるという。法事のためにこの日だけ母屋を借り、無理をして料理や酒をそろえたのだろう。名家は没落していたようだ。
静子からすれば、そんなことはどうでもいい話。もう10年以上も行き来していない縁遠い親戚だと思っていただけに……しかし、その法事になぜ自分だけが呼ばれるのだろう。腑ふ に落ちない。
宴会の場でとつぜん自分が養女だったと知らされ…
彼女が少女歌劇の舞台に立っていることは地元でも知られている。つまり、親戚筋の有名人を法事に出席させて、没落した名家の面目を保つということか。と考えて、一応は納得していたが、すぐに自分がここに呼ばれた本当の理由を知ることになる。法事の同席者たちから求められて、レビューの踊りや歌を披露した。みんな大盛りあがりして喜ぶ。しかし、酒が入って口が軽くなっていたようで、
「見事なもんやなぁ、あの時の赤ん坊が立派になって」 「陳平が生きとったら、きっとこの娘を家に呼び戻していただろうになぁ」
などと、言ってはならない事をしゃべる者がでてくる。うめは伯父に出席者たちの口止めを徹底するよう言い含めていたが無駄だった。不審に思った静子は、法事を終えてから従姉妹や伯母を激しく問い詰めた。その勢いに気圧けお された伯母が出生の秘密をしゃべってしまう。
母も父も弟も、家族がみんな自分と血の繫つな がらない他人だったとは……これまで信じてきたものがすべて崩れ落ちたような、言葉にできない衝撃をうけた。
大阪の父母とは血がつながっていないという衝撃
事実を知った日の夜は一睡もできなかった。朦朧もうろう としながら朝を迎えて、ふらふらと家を出てあてもなく街をさまよい歩いた。そして町外れの川に辿たど り着き、衝動的に川に入ってしまう。肩まで水に浸かり、川から上がった時には髪も着物もずぶ濡れ。その姿で河畔の土手を走りまわったというから、誰かに見られていたら大騒ぎになっただろう。いったい何がやりたかったのか、自分でもわからない。尋常な心理状態でなかったことは間違いない。
静子は感情の起伏が激しく、突拍子もない行動にでることが時々ある。反面、切り替えの早いサバサバ系。後悔や未練をいつまでも引きずらない。悩んでいるよりは、悩みの原因を解決するために動こうとする。この時もそうだった。
水に浸かり頭が冷えて平常心を取り戻したところで、これから自分はどうするべきか? と、考えてみた。実父の陳平は亡くなったが、実母はまだ生きているという。まずは彼女と会って話してみることにした。何故、自分を捨てたのか? 理由を本人の口から聞かないことには納得ができない。このまま何もせず大阪に帰れば、後々に絶対に後悔する。
実母は生きていると知ってその家を訪ねてみると…
静子は伯母をさらに問い詰めて、実母である鳴尾の居場所をしゃべらせた。彼女はいま引田の街中に住んでいるという。古びた小学校校舎の裏手にその家はあった。鳴尾は陳平の死後すぐに結婚したが、その夫の姓も「三谷」だった。田舎の集落に同姓は多い、これは偶然の一致だろうか。それとも、三谷家が罪滅ぼしにと縁者に嫁がせたのか?
静子が意を決して格子戸の隙間から声をかけると、中から女性が5~6歳くらいの男の子の手を引いて出てくる。
「あんたはんでしたか……」
それが鳴尾の第一声。引田はさほど広い街ではない。亀井夫妻に連れられて帰省した静子を見かけることもあったのだろう。玄関先に立っている静子を見て、すぐに自分の娘だと気がついたようである。
家の中に通されるが、お互い何を話せばいいのか。気まずい沈黙がつづく。十数年ぶりの対面で緊張していたこともあったのだろうが、実母は顔色が悪く陰気な雰囲気を漂わせる女性だった。小柄でやせ細った体がその印象を強める。この体格は静子も受け継いでいる。自分はこの人から産まれたのだと思えてきた。長い沈黙の後、鳴尾がぼそぼそとしゃべりはじめた。
小柄でやせ細った体は実母から受け継いだものだった
「わては、若い頃にあちこちで女中奉公してましてな、あんたが小さい頃にもようお守も りをしました」
などと嘘で塗り固めた話ばかりで、自分が実の母親だとは絶対に言わない。涙を見せることもなく、その表情はほとんど動かない。松竹に入ってから静子は人をよく観察するようになっていた。相手が何を考えているのか、言葉に出さない感情や意図を機敏に察して先に動く。下積み時代の楽屋で会得した技なのだが、能面のような鳴尾の表情からは、何も察することができなかった。
静子にもそういったところがある。神経質で色々と気に病むことは多いのだが、人前ではけしてそれを表にださない。他人を信用していないだけに、自分の弱みを知られたくないのだろう。「明るい」「ガサツ」「さばさばしている」などと人からよく言われる性格も、弱い自分を隠すための演技? そう思ったりもする。
鳴尾と対面してから数日後、静子は大阪に帰って仕事に復帰した。伯父や伯母は自分たちの失態をうめに知られることを恐れて、絶対にこの事を話さないようにと何度も口止めしてきたが。言われずとも話す気など毛頭ない。
静子はこれまでと変わらぬ態度で家族と接した。それを見て、うめも「約束は守られた」と安堵あんど する。お人よしのうめを騙だま すことは簡単だ。が、騙しているという負目がずっとついてまわる。それを隠して平静を装いつづけるのは苦しかった。
実母は母親だと認めず、静子は養母に知らなかったふりを
自分と会った時の鳴尾も、あの無表情の裏側で沸き起こる感情を必死で抑えていたのだろうか。そんなことを考えたりもする。しかし、彼女の本意はまったく分からない。やっぱり、自分とあの人は似ているのかもしれない。自分はあの人から産まれたのだと確信するようになっていた。
だからといって、うめに対する信頼や愛情が揺らぐことはない。自分の母親はこの人だけ。その思いは変わらない。何を考えているか分からない実母とは違って、うめは分かりやすくたっぷりの愛情を注いでくれる。この世で一番、自分のことを愛してくれている人だ。それは間違いないのだから。
静子にはこの育ての親から受け継いだものも多くある。うめは苦しみや悲しみを笑い飛ばして忘れてしまうタフで明るい女性だった。人情に厚く困った人をほってはおけないおせっかい。そんな性格だから多くの人に好かれる。
自分も他人からそんなふうに見られたい。と、憧あこが れてもいた。静子は味方と思う人々には深い愛情を注ぎ、恩をうけたら倍にして返す義理堅さがある。このあたりは、うめの影響が大きかったのだろうか。
慈しんで育ててくれた養父母の影響も大きかった
また、静子の後天的な性格には、養父の音吉から譲り受けたものも多い。米屋の商売にさっさと見切りをつけて銭湯に転業するあたり。後先考えないようなところはあるが、果敢な行動力と決断力は静子も受け継いでいる。それにくわえて、いつも忙せわ しなく動きまわるせっかちなところまでそっくり。
余談だが、この父娘については面白いエピソードがある。
昭和2年(1927)3月7日に京都府北部の丹後半島を震源とする大地震が発生した。「北丹後地震」「奥丹後地震」などと呼ばれたものだが、ちょうど研修生から松竹楽劇部に正式採用が決まった日のことで静子もよく覚えている。
研修生の卒業証書をもらって帰宅する途中、市電を降りたところで小腹が空す いてきた。そこで家の近所のうどん屋に入り、きつねうどんを注文したのだが。丼を持って食べようとした瞬間、激しい揺れに襲われた。
記録によると大阪市は震度4。東京の人なら大騒ぎするほどの揺れではないが、関西人は地震に慣れていない。また、静子たちが住む恩加島は大阪湾岸の埋立地。軟弱地盤だけに他の地域よりも揺れが激しかったのかもしれない。身の危険を感じて、食べかけのうどんが入った丼を持ったまま店の外に飛びだした。
大衆に愛される「ブギの女王・笠置シズ子」を生み出したもの
店の外に出ると、通りの先にある自宅の方角から大勢の人々が慌てて走ってくる。そのなかには音吉の姿もあった。
「お父さん」
声をかけると音吉も気がついて、
「あかん、もっと遠くに逃げにゃ。うちの銭湯の煙突が倒れたらえらいこっちゃ」
そう言って静子を促す。父の後ろについて走りだすのだが、見れば音吉も茶碗をかかえていた。御飯時だったのだろう。丼と茶碗を手にしたまま必死に走る父娘の姿を想像すると、なんだか笑えてしまう。せっかちな性格ゆえの失態は、静子はこの後もよくやらかす。天然ボケも他人からは好感をもたれるものだ。
実母から受け継いだ忍耐とポーカーフェイス、育ての親から学んだ人情の大切さや行動力。それにくわえて、天然のギャグセンス? すべて芸能界で生きてゆくのに必要なスキルだ。複雑な生い立ちも“ブギの女王・笠置シズ子”を育むためには不可欠の要素だったのかもしれない。


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













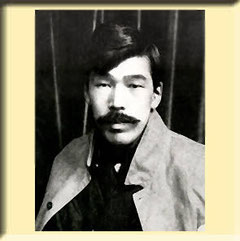














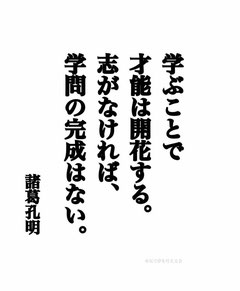









コメントをお書きください