
Japaaan読者の皆さんこんにちは。ライターの小山桜子です。今回は19世紀後半、主に長崎や熊本から東アジア・東南アジアに渡って働いた日本人娼婦「からゆきさん」の悲しい歴史について前後編に分けてご紹介します。

からゆきさんの歴史
からゆきさんの歴史を遡ると江戸時代まで辿る事ができます。1639年(寛永16年)ごろに西洋との唯一の窓口として栄えた長崎に丸山遊廓が誕生。
江戸幕府は出島や唐人屋敷への出入り資格を制限していましたが、丸山遊郭の遊女は例外として許されていました。
日本人男性相手の「日本行」の遊女とは明確に区別され、出島へ赴く遊女たちは「紅毛行」、唐人屋敷へ赴く遊女たちは「唐人行」と称されました。「唐人行」とは中国人を相手にする遊女らを指したもので、それが「からゆきさん」の語源となったのです。
ちなみに実際には江戸時代からすでに長崎の外国人貿易業者により何万人もの日本人女性が妻妾や売春婦として東南アジアなどに渡り、からゆきさんとなっていたとされています。
更に明治維新で正式に日本人の海外渡航が可能になると、鎖国時代から長く中国人のみを相手にしてきた「唐人行」の遊女たちは更なる仕事の場を求めていち早く海外へ飛び出しました。
からゆきさんのほとんどは幼い少女
からゆきさんとして海外に渡航した日本人女性の多くは、農村、漁村などの貧しい家庭の娘たちでした。つまり当時の日本では少女の人身売買が普通だったのです。
幕末に来日したオランダ人の軍医の記録の中に、日本人少女の売春について
「全然本人の罪ではない。大部分はまだ自分の運命について何も知らない年齢で早くも売られていくのが普通なのである。」(沼田次郎、荒瀬進共訳『ポンぺ日本滞在見聞記』雄松堂、1968年)
という文章も残っています。
彼女たちを海外の娼館へと橋渡しした斡旋業者、女衒たちは貧しい農村などをまわって年頃の娘を探し、海外で奉公させるなどと言ってその親に現金を渡しました。
親の方も娘の「奉公」の内容については大方の察しは付いたでしょうが、どうにもできないほど貧困が蔓延していたのです。
1日で30人相手する日も…異国に売られていった日本人少女たち「からゆきさん」の売春の実態【後編】
Japaaan読者の皆さんこんにちは。ライターの小山桜子です。今回は19世紀後半、主に長崎や熊本から東アジア・東南アジアに渡って働いた日本人娼婦「からゆきさん」の悲しい歴史について前編に引き続きご紹介します。
からゆきさんの隆盛と闇

こうして日本人女性の海外渡航は明治末期にその最盛期をむかえました。
からゆきさんの主な渡航先は、シンガポール、中国、香港、フィリピン、ボルネオ、タイ、インドネシアなどアジア各地で、さらに遠くシベリア、満州、ハワイ、北米(カリフォルニアなど)、アフリカ(ザンジバルなど)に渡った日本人女性の例もありました。
人身売買業者が長崎や熊本から彼女たちを運んだ船はひどい状況で、船の一部に隠されて窒息死する少女や餓死しそうになる少女もいました。
生き残った少女たちは香港、クアラルンプール、シンガポールで娼婦としてのやり方を教えられ、オーストラリアなど他の場所へ送られました。
からゆきさんの生活の実態
当時日本では彼女たちの生活の実態はほとんど知られていなかったものの、からゆきさんを題材にしたルポ『サンダカン八番娼館』(1972年、山崎朋子)が映画化され、その実態が徐々に明らかになっていきました。
『サンダカン八番娼館』に描かれた大正中期から昭和前期のボルネオの例では、娼婦の取り分は50%、その内で借金返済分が25%、残りから着物・衣装などの雑費、更にはフィリピン政府の衛生局での週1回の淋病検査、月1回の梅毒検査の費用もあり、その雑費の2倍が娼婦負担にさせられていました。
「返す気になってせっせと働けば、そっでも毎月百円ぐらいずつは返せたよ」という元からゆきさんの言葉から、月約130人は相手していた計算になります。
特に大変だったのが港に船が入った時で、どこの娼館も満員になり一晩に30人の客を取ったからゆきさんもいたといいます。
客の1人あたりの時間は3分か5分、それよりかかるときは割り増し料金の規定でした。休みたくても休みはなく、とある元からゆきさんが当時を振り返って言った「月に一度は死にたくなる」という言葉に当時の過酷さが表れています。
やがて国際的に人身売買に対する批判が高まり、日本国内でも彼女達の存在は「国家の恥」として非難されるようになってしまいました。
1910年代および1920年代の間(明治43年~昭和4年)、海外の日本当局者は日本人売春宿を廃止し、からゆきさんの多くは日本に帰りましたが、更生策もなく残留した人もいました。
戦争の被害者。第二次世界大戦後の米兵相手の娼婦「パンパン」はなぜ生まれた?

Japaaan読者の皆さんこんにちは。ライターの小山桜子です。突然ですが、「パンパン」という言葉を聞いた事があるでしょうか。
「パンパン」とは、戦後混乱期の日本で、主として在日米軍将兵を相手にした街娼です。彼女たちの多くは戦争で家族や財産を失って困窮し、売春に従事することを余儀なくされた女性でした。

どうしてパンパンは生まれたか
日本の第二次世界大戦敗戦後間もなく設置された特殊慰安施設協会 (RAA) の廃止(1946年3月26日)に伴い、職を失った売春婦が街頭に立ちパンパンとなったとも、RAAと並行して存在していたとも言われています。
1947年時点の推計で、東京に3万人、六大都市合計で4万人のパンパンがいたとされ、東京では主に上野、新宿、有楽町で活動しました(それぞれ隠語でノガミ、ジュク、ラクチョウ)。
インタビューに残る悲痛な叫び
彼女たちは「パン助」などとも呼ばれ軽蔑されましたが、「ラクチョウのお時」という名で呼ばれた有名なパンパンが、 ラジオ番組『街頭録音』で取り上げられた際にインタビューで次のように述べ、大きな反響を呼びました。
「 そりゃ、パン助は悪いわ、だけど戦災で身寄りもなく職もない私たちはどうして生きていけばいいの、好きでこんな商売をしている人なんて何人もいないの、それなのに苦労して堅気になって職を見つけたって、世間の人はあいつはパン助だって指さすじゃないの。
私は今までに何人も、ここの娘を堅気にして送り出してやったわよ。それがみんな(涙声)いじめられ追い立てられて、またこのガード下に戻ってくるじゃないの。世間なんていいかげん、私たちを馬鹿にしてるわ」
差別が社会復帰を妨げた
この時お時さんは有楽町で約500人のパンパンを率いるやり手の立場をつとめていたため、女性たちの母親代わりのような存在でした。
お時さんのインタビューからは一度パンパンになった女性は激しい差別を受け、なかなか他の職に就く事が難しかったという辛い現実が垣間見えます。
戦前は学校に通ったり大切な家族が居たり、普通に生活していた彼女たちが、戦争のせいで社会的に孤立してしまったという悲しい歴史の一つです。


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













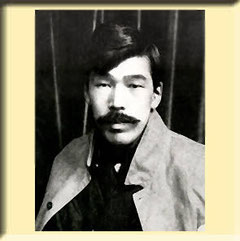














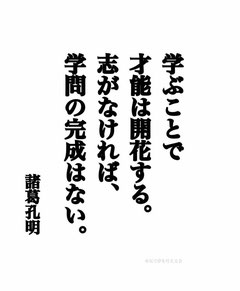

コメントをお書きください