
ハゼ釣りのシーズンも終盤戦。落ちハゼを狙って千葉県・上総湊へ出かけてきました。ここ数年低調だった上総湊(上総湊港、湊川)でしたが、今年はまずまずの湧きであることを確認。18cm筆頭に19匹の釣果をあげることに成功した釣行をレポートします。
上総湊でのハゼ釣り
ポイントが河口ということで、10月中旬位からの「落ちハゼ」狙い専門のポイントというイメージを持つ方が多いと思います。しかし、ここは8月にはデキハゼも狙える、意外とロングランで楽しめるポイント。
とはいえ、近年は低調続きでロングランどころではなかったのですが、今年はちょっと状況が違いそう。実は3週間前、お隣の白狐川でのハゼ釣りの帰り道、湊川で多数の釣り人を目撃。
「今年はひょっとして釣れるのではないか」と気になり、10月最後の週末、調査に出かけました。
上総湊のハゼ釣りポイント
上総湊のハゼ釣りポイントは、車が釣り場のすぐ近くに停めることができ、かつ足場がとても良い上総湊港と、先日多数の釣り人を見かけたやや上級レベルの湊川の2ヶ所。
特に前者の港は人気の釣り場となっていて、天気の良い休日は、8時過ぎたあたりから釣り人で賑わいだします。実は上総湊港、あまり早い時間だと何故かアタリが皆無。釣り船が出払った8時頃からアタりだす、といった特徴があります。
釣り船のエンジンの音でハゼ達が目覚める、かどうかはわかりませんが、お出かけの際はこの時間を目指すと良いでしょう。

またお隣の湊川は、水位があると足場が水没しているため、潮位がある程度低い時間帯限定となります。しかし、川ということで潮止まりの影響を受けづらく、魚影も港に比べて濃いことが多いので、下げ止まりが近づいてきた際は、こちらに移動してみる選択肢を持っておくと好釣果に繋がります。
特に港の反対側(南側)は手前から水深がある好ポイントとなっており、狙い目です(港より海側の川付近は立ち入り禁止になっていました)。

タックル&仕掛け等
港は足元から高さがあり、また水深も2m前後あることから、のべ竿なら4.5m~の長めの竿、ヘチ狙いでも3.6mが必要となります。
ちょっと根掛りが多くなってしまいますが、リールタックルのちょい投げでももちろん構いません。また、湊川についてもハゼが溜まっているポイントが遠い場合も多いので、同様のタックルがおすすめ。
また、特記すべき点として、港なら足場が高いということで、ロープ付きの水汲みバケツがあると重宝し、川では大抵足場が濡れているので、長靴の着用がマストとなります。
エサは周りを見渡すと、皆さんほぼ100%アオイソメやジャリメといったムシエサを使用していました。ということで、筆者もアオイソメ(細虫)を準備。ポツポツ釣れる想定で、1時間10g(10匹目標?)で、納竿予定時間から逆算し準備すると良いでしょう。

出だしは港でウロハゼ連発
上総湊には7時ちょい前に到着。缶コーヒーを飲みながらゆっくり準備し竿を出します。案の定この時間帯はアタリなく、釣り人もいません。やがて、港はカワハギ狙いの船釣り客で賑わいだし「今日は釣れる気がする!」「20はかたいかな!」なんていう景気の良い会話が聞こえてきました。
太公望達を乗せた釣り船が港を出ていき、賑やかだった港が静かになると、これが合図とばかりにハゼのアタリが出始める。この時点で、今期は釣れるかどうか半信半疑だったので、ホッと一息です。

ヘチを探ってアタリを出す、といった釣り方でポツポツと数を重ねていきます。ここでウロハゼなんてたまに混じる程度、という記憶なのですが、この日は何故か出だしから5連チャン。しかも良型揃い。

そして段々と港にハゼ狙いの釣り人が増えてくると、ようやくマハゼが混じりだし、9時を過ぎると、今度は10cm前後のマハゼのみとなっていきました。

上総湊港
湊川はフグの猛攻
やがて下げの潮止まりが近づき、アタリが遠のいてきたところで湊川へ移動。実は港での釣りの最中、地元の方に「湊川の方が釣れるよ」とアドバイスを受けていました。
確かに上総湊で入れ喰いになる場合は港ではなく湊川かな、と過去の記憶を思い出し、長靴を履いて移動します。川に到着すると、予想通り足場が姿を現していました。
早速入れ喰いを期待し竿をだしてみるも……どこを探るもフグ、フグ、フグ。一応入れ喰い、ということであっという間にエサがなくなっていき、湊川ではハゼの顔を見ることは叶わず。

ただし、道具を片付けていると、10m位離れた所でやっている方はハゼを連発している様子。竿は5mかそれ以上のものを使っているようで……筆者の3.6mの短い竿が敗因だとしたら、この日ハゼが溜まっている場所、というよりフグがいない場所は遠めにあるようでした。
最終結果
ウロハゼ7匹、マハゼ12匹の19匹。最大はウロハゼ18cm。ここ数年は低調だっただけに、最後はフグの猛攻にあってしまうも、満足の釣行となりました。
左ウロハゼ、右マハゼ。こうして比べてみると、ウロハゼの方が色黒で太め。

良型(特にウロハゼ)が多く混じったのですが、10cm前後も多くいたことから、まだまだハゼ(特にマハゼ)の成長は遅れている様子。温暖化? 豪雨? ハゼの気まぐれ? 近年はちょっと予想しづらいのですが……上総湊のハゼ釣りシーズンはまだまだ続くと思います。(外したらスイマセン)
マハゼとウロハゼの食味の違い
気になって……ロウハゼとマハゼを食べ比べてみました。ウロハゼとマハゼの違いは、色や模様、体つき、パーツの形等で一目瞭然なのですが、その他のポイントとしては、ウロハゼの方がヌメリあり、また生命力もある印象。
ジップロックに入れて持ち帰ると、生き残っているハゼは大抵ウロハゼです。

刺身とから揚げに
まず刺身については、大きさが4cm違うということで、スタートライン時点でマハゼ不利なのですが、両者ともに旨味甘みともに大いにあり。特に18cmのウロハゼはシロギスをしっかりさせたような食感で、「これ寿司にしたい」と思いました。
また、実際食べ比べたわけではないのですが、海で釣れる、いわゆる「落ちハゼ」は、刺身にしても泥臭さがなく特に絶品。良型の落ちハゼが釣れた際は、是非試してみてください。
また天ぷらについては、揚げたて熱々のマハゼを安定の100点満点とすると、ウロハゼは95点。やや頭と骨が硬いかな、と思いました。
ちょっと時間が経った2匹目のウロハゼは、更に頭と骨の硬さが気になり90点。しかし……ビールを飲みだした後にかぶりついたマハゼ、ウロハゼは、両者とも120点!細かいことなど気にせず、心豊かに一日をしめくくりましょう!

<尾崎大祐/TSURINEWSライター>
湊川
2時間超で最大17cmのハゼが50〜70匹!今後は天ぷらサイズにも期待!

ハゼ釣りフリークにとって本格的なシーズンは、秋の彼岸(9月23日の秋分の日を挿み1週間)以降に始まる。夏のデキハゼの数釣りも良いが、年末や年明けに向け大型化するヒネハゼを狙いに、ホームグラウンドとしている木更津潮見運河周辺と君津方面へ10月末、探索に出掛けた。今回も当方が釣りの師匠と仰ぐ古山輝男さん(元JGFA常任理事:73歳)に同行をお願いした。
陸釣りでもライフジャケットを!
木更津潮見運河周辺は駐車場が少ないので、パーキング利用の方は少々歩かなければならない。木更津駅西口よりバスで潮見線・君津製鉄所行に乗車し、潮見3丁目で下車すると徒歩5分ほどで釣り場に到着する。近くにコンビニも数軒あるのでトイレや買い物にも便利だ。
釣具店や船宿にもエサの青イソメは売っているが釣り場からは遠いので前もって用意しておきたい。運河周りはボートが係留されていて、護岸が整備されている釣り場と足場が高い桟橋がある。いずれにせよ安心、安全のためライフジャケットは着用したい。




一投目からアタリ!
今回、用意した竿は竹製の和竿メイン。6尺(1.8m、中通し)、9尺(2.7m、延べ竿)、13尺(3.9m、カーボン製振り出し竿)、15尺(4.5m、渓流竿)を釣り場に合わせ使用した。道糸は、フロロカーボン1号を竿の長さに合わせ、ハリス0.8号に袖針7号、目印のシモリウキ4個にオモリ1.5号を使うミャク釣り。エサの青イソメの垂らしを少な目に3cmほどの長さで付ける。
正午近く最初に選んだ桟橋ポイントでは2.7mの竹竿を使った。水深は1〜1.5m。
一投目、底ダチを取り竿先が軽くもたれるように糸を張る。シモリウキが少し動いた“プルプルッ”と手元に伝わるアタリがあり、利き上げてみると13cmのマハゼが顔を見せてくれた。軟らかい竹の感触、和竿の釣趣は一度経験したら病みつきになる。幸先が良いスタートに期待が膨らんだ。
師匠は6尺の中通し竿を使い、入れ食いを堪能している。しかも11〜15cmと良型揃いだ。この時期にしては浅場に良型が残っている印象だ。今年は暑さのせいか水温が高く、深場へ落ちるのが遅いように感じた。
多少移動しながらの釣りも、場所によっては10cm以下のハゼも釣れてくる。1時間30分ほどの釣果は30〜40匹ほどの釣りだったが、良型が多く最大16cmも出た。十分満足出来るものだったので富津方面へ移動した。


富津新富水路は最大17cmのハゼ
木更津から国道16号を走り移動すること30分。富津漁港に流れ出す新井橋と西川橋の間の公民館駐車場を目指した。しかし、この日は日曜日のためイベントが行われていて駐車できず、川の反対側の総合体育館臨時駐車場に止めることができた。
右岸側、ゆうやけ橋の手前に釣り座を構えて様子を見る。師匠が「居る居る!」振り込みと同時にアタリがあったようだ。抜き上げたのは16cmのハゼ。続いて当方にも15cmが掛かってきた。パタパタと釣れてくる15cm前後がここのアベレージサイズなのだろう。ひときわ重みがある引きで上がってきたのは今日一、頭のデカい17cmのハゼだった。
師匠が振っている竿は4.5mの渓流竿、当方は3.9m。岸に近いポイントでの釣りは問題なかったが、少しずつ深いポイントへハゼが移動している。ここでは長い竿が有利だった。1時間ほどの釣果は12〜17cmが20〜30匹。今後、天ぷらサイズの20cmオーバーも釣れてくる晩秋に期待しながら釣り場を後にした。






施設等情報
電車:JR内房線・青堀駅下車、富津公園行バス
自動車:館山自動車道「木更津南IC」を下り、国道16号線を富津岬方面へ15分
施設等関連情報
住所:千葉県木更津市太田3-11-1
電話:0438-23-4130
■『キャスティング木更津店』
住所:千葉県木更津市幸町3-1-2
電話:0438-30-1476
著者:小金井 考和

意外と知らない『マハゼ』の生態 生命力強く海外では外来魚扱いも?

マハゼとは
ハゼは「スズキ目ハゼ亜目」のサカナで、世界で見ても非常に種類が多く、現在では魚類の8%、およそ2,200種が確認されています。
ハゼ科だけを見ても、ムツゴロウ、トビハゼ、ワラスボ、ウキゴリ、ヌマチチブ、シロウオ、ヨシノボリなど、多くの人が一度は耳にしたことがあるサカナがいるのではないでしょうか。
そのなかで、日本人にとってもっとも親しみのあるのがマハゼ。マハゼは「スズキ目・ハゼ科・ハゼ属」に分類されています。釣って楽しい、食べて美味しいマハゼの生態を見ていきましょう。
マハゼの生息域
マハゼは北海道から種子島まで広く分布し、国外では朝鮮半島と中国の沿海地方に棲息しています。
波の穏やかな内湾や汽水域の砂泥底を好み、若魚のうちはごく浅い海岸や川の純淡水域にも進入してきます。
また、水質汚染にも強く、都市部の港湾でもその姿を見ることができます。
東京湾では昔から江戸前の魚としてポピュラーですが、水質が悪化した昭和40年代には一時期、その個体数は減少傾向でした。現在、干潟の環境整備や保全活動等で、数は増えてきてはいますが、干潟の消失などのダメージは大きく、かつての状態とはほど遠いと言われています。
マハゼの食性と性格
食性は肉食性が非常に強く、ゴカイなどの多毛類、カニやエビのような甲殻類、貝類、小魚など様々な生物を貪欲に捕食します。しかし生息域によっては藻類を食べることもあり、地域性もあるユニークな食性ともいえるでしょう。
また、縄張り意識が非常に強いため、自分のエリアに侵入してきた他のサカナには果敢に攻撃をしてきます。
最近ではこの習性を利用した「ハゼクラ」と呼ばれるルアー釣りが密かにブームとなっています。
名前の由来
マハゼの語源の由来は諸説ありますが、 「飛び跳ねる=はぜる」または 水中をすばやく移動するさまから「馳せる」から『ハゼ』 となった説が有力だと考えられています。
日本における地方名は、カジカ(宮城県)、カワギス、グズ(北陸地方)、デキハゼ(関東地方・若魚)、フユハゼ(浜名湖)、カマゴツ(鳥取県)、ゴズ(島根県)、クソハゼ(大村湾)など、たくさんあります。愛されて認知度が高いからこそ、その名も数多く存在しているのでしょう。
 多くの人から愛されるハゼ(出典:PhotoAC)
多くの人から愛されるハゼ(出典:PhotoAC)
成長すると名前が変わる?
マハゼは冬から初夏にかけての1~5月で、産卵期を迎えるとオスは砂泥底に長さが1mにもなるV字やY字型の巣を作り、メスを迎えて夫婦となり産卵活動を行います。
オスは卵が孵化するまで巣穴を守り、 孵化した稚魚はフワフワと遊泳生活でプランクトンを捕食しながら成長し、2cm程度に成長すると底棲生活にうつっていきます。
生後数か月の小さなハゼを「デキハゼ」と呼び、9月頃に体長10cmが超えると、「彼岸ハゼ」と呼び名が変わっていきます。成長とともに海の近くへと移動し、晩秋~冬になると沿岸の深場に生活の場を移り、このころになると「落ちハゼ」や「ケタハゼ」などと呼ばれるようになっていきます。
ハゼの寿命
生息地にもよりますが、一般的にはハゼの寿命は1~3年と言われています。
3歳魚ともなるとハゼの体長は30cmを超えてきます。
しかし、3歳まで成長する個体はそこまで多くなく、30cmを超える個体を見たことがある人は限りなく少数です。
日本のハゼが国外へ
近年はアメリカ・カリフォルニアやオーストラリア・シドニーにもマハゼが定着していることが判明しています。
これは日本におけるブラックバスやザリガニのように外来魚として扱われています。ハゼは環境の変化に強く、食性も富んでいるため、その強靭な生命力で、様々な海で定着してしまっているのです。
船舶のバラスト水などによって運ばれたと考えられており、今後はより一層の注意が必要です。
釣り初心者にオススメのサカナ
マハゼは釣りを始めた初心者や子供が釣りを覚えるのにうってつけのサカナです。沿岸部のいたるところに群れで行動するため、すぐに見つけることができ、食性も豊かなためエサの選択肢も様々です。
ムシが嫌いな人ならオキアミやホタテ、ルアー釣りをしてみたい人なら「ハゼクラ」など、釣りのイロハを学ぶことが出来るでしょう。
また、ハゼは江戸前では天ぷらにも使われるほどに美味しいサカナです。
釣って楽しい、食べて美味しいハゼをさっそく今週末に釣りに行ってみてはいかがでしょうか。
とても身近な魚『ハゼ』の保護活動が行われるワケ 気づけば高級魚に?

中海でマハゼ陸上養殖活動
鳥取と島根にまたがり、日本有数の規模を誇る汽水湖・中海。その鳥取側の水域で、地元の高校生が参加した、養殖用マハゼ稚魚の採取体験が実施されました。
マハゼはかつての中海ではとても馴染み深い魚でしたが、今では特に鳥取側で激減し、その復活が試みられています。
 釣り上げられたマハゼ(提供:PhotoAC)
釣り上げられたマハゼ(提供:PhotoAC)
鳥取県の水産試験場と地元企業が共同で3年前から、マハゼの陸上養殖の試験を続けていて、今回獲られた稚魚もその養殖試験に提供される予定だといいます。(『「地元の魚食文化を守りたい」中海のマハゼ復活めざし高校生も一役 養殖へ稚魚を採取(鳥取・境港)』さんいん中央テレビ 2021.5.20)
天ぷらの最高級魚・マハゼ
マハゼはその名前の通り、ハゼ類の代表種と呼べるもの。全国の浅い海や汽水域に生息し、ときに純淡水に入り込むことのある、環境適応力の高い魚です。
小魚で大きくても20cmほどにしかならず、またほとんどの個体は1年で死んでしまう年魚です。しかしその味は極めてよく、古くから食通たちを唸らせてきました。
 調理されるマハゼ(提供:PhotoAC)
調理されるマハゼ(提供:PhotoAC)
マハゼは上品な白身魚で皮に独特の風味があり、出汁がよく出るのが特徴です。加熱すると魅力が存分に発揮され、とくに江戸前の天ぷらだねには欠かせない存在でした。また干したものは雑煮や甘露煮の素材として、全国各地で非常に珍重されています。
東京湾では、屋形船で乗客にハゼを釣らせ、その場ですぐに天ぷらにしてくれるようなサービスも数多く存在しています。需要はまだまだ高いものの、ハゼ漁の専門の漁師が減り、また小魚であるために調理技術に熟練を要すことも、今ではスーパーなどではなかなかお目にかかれない魚になりました。
ハゼの産卵地が減少
その一方で「釣りの対象」としては馴染み深い存在でもあるマハゼ。貪欲な性質で、その大きな口で餌を見境なく食べます。そのため初心者でも簡単に釣れ、釣魚としての人気は高い魚です。
しかし、上記の中海のように、近年では減少が著しい場所も多くなっています。彼らが生息し産卵を行う砂地の浅場が、埋め立てやヘドロの堆積によってどんどんなくなってしまっているためです。
 マハゼの天ぷらが食べられなくなる?(提供:PhotoAC)
マハゼの天ぷらが食べられなくなる?(提供:PhotoAC)
今ではいわゆる「ハゼの天ぷら」も、メゴチなど別の魚を代用したものが増えているといいます。もしかするとそのうち「マハゼの天ぷら」は庶民には手が届かない存在になってしまうかもしれません。
<脇本 哲朗/サカナ研究所>
インパクト抜群の「青い刺身」を作れるサカナ『アナハゼ』 味はラムネ?

身も骨も青色の「アナハゼ」
青魚という言葉もあるが、これは身の色ではなく背中が青く見えることからそう呼ばれる。不飽和脂肪酸を多く含む魚は、背中が青く見えるのだという。
ダツやサヨリ、サンマなど骨が青いことで知られる魚でも、さすがに身まで青いということはない。いくらなんでも、青い身の魚なんて……。
それがいるのだ。
その魚の名はアナハゼ。一見すると褐色(黄色っぽい個体もいる)だが、口の中も青ければ骨も青。さらに身までもが青い。色の濃淡には個体差もあるようだが、この青い色はダツの骨と同様、ビリベルジンという胆汁色素によるものだ。
どこから見ても毒があるようにしか見えない色だが、もちろんアナハゼに毒などない。それどころか、このビリベルジンには、なんと抗酸化作用や抗炎症作用があるらしい。ということは、アナハゼを食べてアンチエイジング、なんてことも!
アナハゼの生態
この魚、ハゼという名は付くが、ハゼの仲間ではない。実はカサゴ目カジカ科に属する根魚なのだ。漁港周りのライトゲームではおなじみのターゲットで、漁港の壁際や係留ロープの周りでサスペンドしている姿をよく見かける。
見かけによらずどう猛な性質なので、ルアーを落とせば高確率で食らいついてくる。比較的容易にヒットしてくれるので、初心者でも十分に楽しめるだろう。サイトゲームで狙えば予想以上の面白さだ。
 手軽にゲットできる(提供:週刊つりニュース中部版 APC・浅井達志)
手軽にゲットできる(提供:週刊つりニュース中部版 APC・浅井達志)
また、アナハゼは交尾をする魚としても知られている。通常魚類の繁殖行動は体外受精だが、この魚は合体するのだ。せいぜい10~20cmほどの小魚だが、オスには立派な生殖突起がある。ウソでしょ?と思ったアナタ、今度釣り上げたら、じっくりと眺めてみていただきたい。
インパクトある「青い刺身」
そんなアナハゼを食べるなら、やはり刺し身だろう。さばき方は普通の魚と変わらないが、小魚なので糸造りにした方が見栄えがいい。鮮度が落ちると青い色は薄くなるそうなので、新鮮なうちが勝負だ。
 世にも不思議な青い刺身(提供:週刊つりニュース中部版 APC・浅井達志)
世にも不思議な青い刺身(提供:週刊つりニュース中部版 APC・浅井達志)
1匹から取れる身の量が少ないので食べ応えはないが、ソーダ味がすると言われたら思わず信じてしまいそうな青い刺し身。お世辞にも食欲をそそる色ではないが、ビジュアル的なインパクトで、このアナハゼに勝てる魚はいないだろう。
撮りようによってはインスタ映えもしそうだ。
その味はと言うと、そこはカサゴの仲間。ほどよい甘みもあり、色さえ気にしなければ普通の、いや、むしろうまい部類に入るといってもいい白身魚だ。もちろん、ソーダ味なんてしないから心配はいらない。
私は刺し身でしか食べたことはないが、この青い身は火を通すと普通の白身になってしまうらしい。どうしてもあの色になじめない、という場合は加熱調理をするといいだろう。定番は唐揚げや天ぷら、煮魚など。カサゴの仲間だけに、どう料理しても間違いはないはずだ。
<週刊つりニュース中部版 APC・浅井達志/TSURINEWS編>

 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













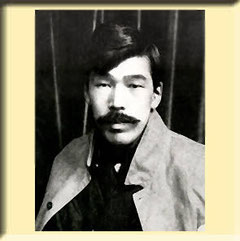














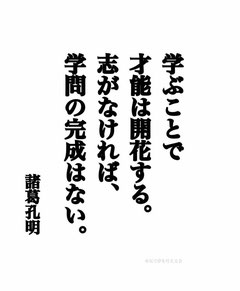

コメントをお書きください