
聡明だけど、人の心がわからず、誤解されやすい性格だ――戦国時代を扱う作品では、そんな人物として描かれることが多い石田三成ですが、不思議とその近くには魅力的な武将がいました。
島左近は以下の記事に譲りまして、
今回注目したいのは大谷吉継。
病状を覆うために被っていた白い頭巾がトレードマークでもあり、今なお「友情のために散った」武将として戦国ファンの間で圧倒的な人気ですが、いったい彼の何が魅力なのか。
大河ドラマ『どうする家康』でも注目される、大谷吉継の生涯を振り返ってみましょう。

近江国に生まれ 秀吉に仕え
大谷吉継はいつ何処で誰のもとに生まれたのか?
その詳細は謎に包まれています。関ヶ原の敗戦を経て大谷家が潰され、記録が残されなかったためでしょう。
かつては永禄2年(1559年)の生年説が有力でした。
盟友の石田三成が永禄3年(1560年)であり、同世代というのは間違いなさそうで、現在は永禄8年(1565年)の生年説が有力視されています。
生まれは近江国伊香郡小谷村で、父は六角氏に仕えていた大谷吉房(こちらも諸説あり)。
それがなぜ秀吉に出仕することとなったのか?
というと、母の東殿が、秀吉の正室・寧々(北政所/高台院)の親族あるいは彼女に仕えていたからと伝わります。
その東殿が、秀吉夫妻から信頼を得ていたのでしょう。
彼女の子である吉継も秀吉に仕え始め、天正年間はじめの頃には、小姓としての記録が見え始めました。
そして毛利攻めにも従軍しながら、頭角を現していく吉継。
中国攻め織田家の傘下でそのまま順調にいくかと思われた生活は、天正10年(1582年)、突如終わりを告げました。
ご存知のとおり、当時の秀吉は備中高松城を包囲していた最中。
そこで本能寺の凶報を知ると、急転直下で毛利と和議を結び、清水宗治に自刃をさせ、すぐさま京都方面へ向かって進軍を始めました。
俗に【中国大返し】と呼ばれる行軍で京都にまで戻り、直後の【山崎の戦い】で明智光秀と激突します。
結果は、秀吉軍の快勝。
吉継の主である秀吉は、織田家臣の中で一歩抜きん出た存在となりました。
賤ヶ岳で評価された吉継の功績
光秀を破った後の清州会議では、信長の嫡孫・三法師を担いだ豊臣秀吉。
織田家中での権力闘争は激化し、次なる相手となった柴田勝家とは、天正11年(1583年)【賤ヶ岳の戦い】で激突しました。
この戦いが大谷吉継の名を高めるものとなります。
一般的に賤ヶ岳の戦いといえば、以下の武将たちがよく知られた存在です。
いわゆる「賤ヶ岳七本槍」で、この呼称自体は江戸期以降のものとされています。
彼らの武功がいかほどのものだったか。
詳細は省かせていただきますが、吉継もまた活躍し、その武功は七本槍に次ぐとされています。
槍働きとは異なるものです。
長浜城主・柴田勝豊を調略し、内応させたのです。
秀吉の得意とするのはこうした戦術であり、それを実行できた配下の者は当然高く評価されたことでしょう。
天正13年(1585年)に秀吉が異例の従一位・関白に叙任すると、吉継も従五位下刑部少輔になったのです。
このことから彼は「大谷刑部」と称されるようになりました。
奥羽に残した禍根
大谷吉継は豊臣政権でどのような役割を期待されていたのか?
石田三成と同じく、武働きというより兵站管理や後方支援、あるいは外交や調略だったのでしょう。
天正14年(1586年)の【九州征伐】においても、兵站奉行・石田三成の下で功績をあげています。
こうした役割は、どうしても影が薄くなりがちです。
江戸時代以降、庶民に愛された軍記物では『三国志演義』の諸葛亮ですら霞んでしまう。そんな状況では、石田三成と大谷吉継の存在感が薄くなっても致し方ないことでしょう。
しかし豊臣政権のもとで重用されたのは間違いありません。
例えば、秀吉が天下人になると、全国の大名が人質の妻子と共に上洛してきましたが、そのとき彼らの屋敷をどうするのか、そもそも荒れ果てた京都をどうやって復興させるのか、その後の治安は?などなど諸問題を吉継や三成は対応していました。
その結果、天正17年(1589年)、大谷吉継は越前国敦賀郡2万余石の敦賀城主となります。
大名になっても多忙の身に変わりはなく仕事を任され、後に5万石へ加増されました。
天正18年(1590年)の【小田原征伐】にも従軍。
続けて【奥州仕置】にも出向き、出羽国では検地も担当しました。
ただし、このときの検地で禍根を残してしまいます。
豊臣政権の行く末について重要ですので、少し詳しく見ておきますと……奥羽の大名は、豊臣政権の検地に対して強い反発を抱き、出羽北部では【仙北一揆】が発生しました。
奥羽の寒冷な気候や状況を踏まえない取り立てが、大規模な一揆の背景にあったと思われます。
大谷吉継の手勢は、そこで強硬な締め付けを行ない、一揆を拡大させてしまったのです。
一揆が勃発する少し前、北条氏の所領には徳川家康が入り、東国大名の取りまとめを行なっていました。
そんな家康と比べて、豊臣政権はどうなのだ。ズカズカと乗り込んできて、東北の事情も考慮せずに強引な検地をしやがる。ヤツらは頼りにならない――そう考えた東国大名が、家康を慕う構図ができてもおかしくはありません。
いわば豊臣政権にとっては大きなマイナスであり、後の情勢に響いてきます。
傾く豊臣政権
文禄元年(1592年)、秀吉は念願の征明を開始しました。
【文禄の役】です。
豊臣政権の中心である吉継も当然のように船奉行に任じられていますが、だからこそこの出兵は不可解なものとされます。
石田三成や大谷吉継のような兵站の担当者が、事前に止められたのではないか?
どうしてもそう考えてしまうのです。
頭脳明晰であった彼らに、それがどれほど無謀なものか、わからないはずがない。
それでも吉継は、石田三成・増田長盛と共に渡海し、勤めをこなしてゆきます。
緒戦は破竹の勢いでした。
しかし長くは続かず、懸念どおり補給が途絶え、諸将の間では深刻な不和が生じてゆく……。
吉継は、明使との和睦交渉においても大きな役割を担いました。明使と秀吉の面会実現にも尽くしました。
秀吉から信頼されていただけでなく、明側からも重要視されていることが浮かび上がってきます。
しかし、この戦役の秀吉軍は、常に兵糧不足に苛まされており、戦病死者や餓死者が続出。
大名の間で生じた深刻な禍根は、取り返しのつかないレベルにまで達してしました。
無益で無謀、無茶でしかない――不毛な戦役は慶長3年(1598)、秀吉の死により、ようやく終わりを告げます。
それと同時に、秀吉の死は、豊臣政権を大きく動揺させました。
秀吉の遺児である豊臣秀頼を守る【五大老】。その一人、徳川家康が秀吉の遺訓に反し、諸大名との婚儀を進めたのです。
同じく五大老の前田利家と家康の間では、ただならぬ雰囲気も漂い始め、吉継が徳川邸の警護を務めたりしています。
そして慶長4年(1599年)、前田利家が没しました。
家康の専横は、もはやとどまらぬものとなってゆきましたが、利家と志を同じくする【五奉行】石田三成では、石高が少なく動員兵力も少ない。
歯止めをかけるどころか三成自身は失脚してしまい、佐和山城の蟄居へ追い込まれてゆきます。
かつて三成や吉継と馬を並べて戦った豊臣系の武将が、ここぞとばかりに三成に不満をぶつけていたのです。
盟友・三成とともに起つ
慶長5年(1600年)、時代は一気に動きます。
まず、五大老の一人であり、会津の大大名である上杉景勝に対し、家康が不穏な動きありとして上洛を促します。
と、上杉景勝がこの催促を拒否。
後世の捏造説も囁かれ、もしかしたら文言に加筆修正があるかもしれませんが、いずれにせよ同様の文書はあったのだろうと見なされています。
そして家康が上杉討伐の兵を挙げ、会津へ進軍。
吉継もこれに参戦すべく、敦賀から3千の兵を率いて、まずは三成のもとへ向かいました。
家康のもとに人質とされていた三成嫡男の重家がこのとき佐和山にいて、これを引き取るため、吉継は三成のもとへ向かったのです。
三成は家康に対し、「嫡男・重家を従軍させて不和を解消したい」と申し出ていました。
しかし、いざ吉継が三成の前に出向くと、驚きの決意を伝えられます。
家康を討つ――。
慌てふためく吉継を前に、三成はその必要性を説きます。
「いま、家康は天下を取ろうとしている。秀頼公を侮っている。太閤の恩を被りながらなんという不義か。家康を許すことはできぬ、討つほかあるまい」
「まて、家康は300万石になろうとするほどの大身だ。軍勢も多く集められる。お前はどれほど集められるのだ? 勝てるわけがなかろう。私が病身でありながら会津へ向かうのは、上杉と徳川の和議をはかるためだ。それこそ秀頼公のためではないか」
吉継は、家康とも親密な仲を築いており、その実力をよく知っています。
家康がハッキリと天下簒奪の意を示した際に動けば良い――そう考えていた吉継は、軽挙妄動によって秀頼に害が及ぶことをおそれ、慎重な行動を心がけていたのです。
しかし、いくら説得しようとも、三成の決意は固い。
吉継はやむをえず単独で会津へ向かいながら、途中で引き返し、三成と行動を共にすることとしました。
二十年以上も付き合いのある三成に対し、吉継は率直な意見を述べています。
兵力が、あまりにも心もとない。毛利輝元か宇喜多秀家を立てて事に挑むべし。
戦略的な提案を提示すると同時に、三成の性格的な欠点も指摘して、それを改めるべきだと説得しました。
三成の決意は固く、ことは内密に進められました。後に真田昌幸が「もっと早く知らせて欲しかった」とこぼしているほどですが、この密謀は即座に家康へ漏れます。
五奉行の一人である増田長盛が、家康と通じていたのです。
関ヶ原に散る
病が進行し、このとき視力はほぼ失われていたともされる大谷吉継。
それでも西軍の将として精力的に動きました。
いったん敦賀城に戻ると東軍についた前田利長を牽制し、前田軍の動きを封じると、今度は得意の調略で、越前や加賀南部大名の取り込みも行います。
そして9月、家康が引き返してくることを察知すると、諸将を率いて美濃関ヶ原に布陣しました。
吉継は、怪しい動きをする小早川秀秋隊に対して備えていたのです。
慶長5年(1600年)9月15日、戦いの火蓋が切られました。
もはや馬にも乗れず、輿の上で指揮をとる吉継。そこへ西軍から東軍についた小早川隊が襲い掛かります。
大谷隊は激しく抵抗し、一時は小早川軍を押し返しましたが、雪崩をうつように他の部隊も東軍へ寝返ってしまい、押しまくられます。
もはやこれまでか……。
と、そのとき配下の平塚為広から、敵将の首に添えられた辞世が届きます。
名のために 捨つる命は惜しからじ 終に留まらぬ浮世と思へば
名誉の為に命を捨てるのならば惜しくなどない。この浮世に留まれるものではないのだから
吉継はこう返しました。
契りあらば 六つの巷に待て暫し おくれ先立つ事はありとも
共に命を捨てると誓ったのだ、六道の辻でしばし待っていてくれ。どちらが先に逝くかわからぬから。
そして、ついには絶命へ……自刃とも、混乱の中の討死とも伝えられます。
★
病を恥じた吉継は、死後、その首を隠すよう湯浅五助に託し、いずこかに深く埋められたと伝わります。
吉継の嫡子・吉勝は戦場を抜け出し、その後【大坂の陣】に果て、次男・頼勝は病死しました。
娘もいます。
真田信繁の正室として嫁いだ竹林院。
もともとは豊臣政権を強化するための政略結婚であり、夫婦の間には父と共に自刃した大助幸昌、伊達家に仕えた二男・大八守信、女子四名がいました。
吉継女系の血統は、この娘により伝えられています。
病身でありながら、盟友・石田三成のため輿に乗りながら戦った大谷吉継。
誠意に溢れ、最期まで壮絶に戦い抜いたその生き様は、今なお多くのファンに支持されています。
家康とも親しく、かつ三成の欠点を諌めるといった逸話からは、人柄の良さも伝わってくる。
その高潔な生き様は、義に生きた将として多くの人々を魅了し続けています。
石田三成・日本史随一の嫌われ者を再評価~豊臣を支えた41年の生涯

かつて石田三成のイメージと言えば悪性評価の一辺倒でした。
しかし最近では「義を貫いた忠臣」という良性三成像も着実に広まっており、人気を取り戻しつつもあります。
では、変わりつつある三成の実像とは一体いかなるものか?
本稿では、慶長5年(1600年)10月1日に亡くなった三成の事績を史実ベースで追ってみたいと思います。
身長156センチ 石田三成の骨格は華奢
石田三成は永禄3年(1560年)、近江国坂田郡石田村(滋賀県長浜市石田町)にて誕生しました。
父・正継は石田郷の土豪であり、浅井家に仕える身。
三成は二男にあたり、幼名を佐吉(左吉という表記もあり)と言います。母は浅井家臣・土田氏の娘でした。
主君の滅びた石田家の者たちは、その後新しくやってきた、織田信長の家臣・羽柴秀吉(豊臣秀吉)に仕官します。
そこで注目されるのがこのエピソード。三成少年期といえば、とにかく「三献茶」が有名です。
残念ながら、このお話は別人のものであるとか、そもそも史実ではないとされています。
旧浅井家臣の子に過ぎない青年が、電撃出世をするはずがない、よほど賢かったのだろう――という後世の憶測が、このエピソードを生み出したのでしょう。
※ちなみに三成よりも早くこの三献茶と同じことをしたエピソードが島津家配下の種子島一族にあります・参考までに
「三献茶」伝説はともかく、三成が仕事のデキる男であったことは確かです。
小姓として仕官したのち、二十代前半で有能な家臣として、他家にまで知られるようになります。
加藤清正や福島正則といった猛将とはひと味違い、事務系の仕事に適性を見せる三成。賢さを主君に見抜かれ、出世を遂げていた様子がうかがえます。
ちなみに三成は、遺骨をもとに複顔したため、身長や顔つきが判明しています。
身長は156センチで骨格はかなり華奢。江戸時代の記録によると、色白、目が大きく、睫は濃く、声は高かったとのこと。
復元された顔も無骨というよりも穏やかです。
近年演じた俳優の中では、『真田丸』の山本耕史さんが最も近い容姿ではないでしょうか。
若きエリート官僚・石田治部少輔
石田三成の名が他家にまで知られ、彼の名による“発給文書”が見られるようになるのは天正10年(1582年)頃から。
三成も武功をあげますが、やはり彼は戦場よりも外交や内政で存在感を示すタイプでした。
天正13年(1585年)に秀吉は、従一位関白に就任します。
三成もこのとき、従五位下治部少輔に叙任されています。三成26才の時でした。
このころ担当した大事な役割は、対上杉家との交渉です。
当時の上杉家は、危機を脱したところ。
織田信長と対峙し、武田家の次は自分たちが滅亡すらのではないか、とすら考えていた上杉家です。ところが急転直下の本能寺により窮地を脱し、その後は天下人となる秀吉に接近を開始してました。
とはいっても、上杉家は始めから秀吉に臣従すると決めていたわけでもなく、両者には緊張感が漂っていました。
よく三成は人付き合いが悪く横柄だとされますが、重要な外交交渉を担う者が本当に無愛想で、取り付く島もないような人物であるとは考えにくいです。
むしろ彼は細かい気配りのできる一面も持ち合わせていたのではないでしょうか。
残された三成→景勝宛の書状を見ると、なかなか親しげな様子のものもあるようで、天正14年(1586年)の景勝上洛の際には、三成が出迎えています。
ただし、彼の外交官としての活躍は上杉家に対してのみではなく、他の多くの大名家に対しても外交窓口として活躍しています。信頼できる外交窓口としての三成像が見えて来ますね。
この年、三成は堺奉行に任じられました。前任者の松井友閑とは親子ほどの年齢差があり、彼がいかに若くして重責を任されていたかがご理解いただけるでしょう。
結婚時期は不明ですが、この頃にはしていたと思われます。
相手は宇多頼忠の娘。実は、真田昌幸の正室も宇多頼忠の娘という説があります。
この説に従えば、三成と真田昌幸は、妻が姉妹同士で義理の兄弟ということになります。
九州、小田原、検地と次々に
秀吉が天下を統一するにあたり、三成はますます忙しくなります。
九州の仕置き、後陽成天皇の聚楽行幸への対応、関東の北条氏攻め【小田原征伐】、そして検地。
ときに天皇を粗相なくもてなし、ときに大軍勢を率いて行軍するための輸送を徹底する――そんな実務能力を次々に求められるのです。
こうした「奥羽仕置」では、不満を持つ者による一揆も続発し、三成はこの対応にも追われています。
彼の性格が「義の人であったか?」というのはとりあえず横に置くとしても、この高い実務能力はきちんと評価すべきでしょう。
日本史の授業で習った秀吉の革新的な政策の数々を、実行に移していたのは三成ら官僚です。
大変な仕事量です。
そしてこの三成の役目が、彼の嫌われる一因かもしれません。
天下人秀吉の意志で行われて処理であっても、秀吉に怒りをぶつけることができずに、執行者である三成に怒りや苛立ちが向かってしまう、と……。
中間管理職の苦悩が三成にはつきまとっていたのではないでしょうか。
そして文禄の役が始まった
秀吉の天下統一に伴い、豊臣に従属する者たちも大名として転封されます。
三成は美濃国内に10万石程度で封じられました。
そして文禄元年(1592年)。
秀吉は「唐入り」、すなわち朝鮮出兵を行うことになります。
参戦者は大変な苦労をしたことで知られるこの戦役。中でも、超大軍の兵糧や船舶輸送を管理した三成の仕事量は、膨大なものであったはずです。
渡海しない大名たちも、肥前名護屋城に滞在していたわけで、ともかく大変なことです。
しかも同年3月に渡海した三成が直面したのは、厳しい戦況です。
名護屋にいた頃に想定していたものより、状況ははるかに深刻でした。
三成は漢城に入ると、諸将に秀吉からの命令を伝える役目を果たし、膠着した戦況の中、渡海したまま年を越します。
翌文禄2年(1593年)には、渡海先で“碧蹄館の戦い”や“幸州山城の戦い”に参戦。後方支援だけではなく、戦闘にも参加しています。
三成のいる漢城は、凄惨な状況でした。
人馬の死体が積み重なり、生き残る者も飢えてやせ衰え、まさにこの世の地獄です。もはや漢城の支配を継続することは不可能でした。
このまま、ただ撤退すれば、そこを追撃されて大損害を被ります。
もはや明との休戦交渉しか活路はありません。
やむをえず三成は、明軍の講和使・謝用梓・徐一貫を伴って肥前名護屋に向かうことになりました。
この和睦は、偽りだらけでした。
謝用梓・徐一貫は明の正式な使節ではなく、参将に過ぎません。また日本側は「明の征圧には至らないものの、降伏させた」と偽ることで、秀吉の怒りを抑えようとしていたのです。
所詮は、偽りの和睦です。
日本が勝利を前提とし、明の皇女降嫁や朝鮮王子を人質とする非現実的な条件をつきつけたため、交渉難航は必至……。
これに関わった三成らの心労を想像すると恐ろしくなります。
三成は和睦交渉と同時に、朝鮮へ再度渡り、「倭城」と呼ばれる要害の築城、朝鮮での在番体制の整備等をこなさねばならないのでした。
しかも朝鮮半島の陣中において、島津義弘の二男・島津久保が没したため、島津家に後継者問題が持ち上がりました。
三成はこの処理にも関わらねばなりません。
島津家に、反豊臣政権的な後継者が据えられることを、警戒しなくてはならなかったのです。
同時並行してマルチタスクをこなす。
その働きぶり、四百年後に史実を辿っている私ですら心配になるほどです。
秀次事件の衝撃
その頃、豊臣政権内には新たな問題が持ち上がっていました。
秀吉は結局朝鮮半島に渡海しないまま「唐入り」が終わろうとしています。これが新たな問題の火種となるのです。
秀吉は渡海を前提として、留守を守ることになる甥で関白の秀次に、権限を委譲しつつありました。
太閤と関白で日本を分割し、支配する体制になりつつあったのですが、秀吉は秀次の統治ぶりを厳しく叱る等して、両者の間に緊張感が生まれることになります。
同時に、秀次は秀吉からのあまりに大きな期待に、押しつぶされるようなプレッシャーも感じていたことでしょう。
この間、三成は島津領・佐竹領、そして蒲生氏郷が死去した蒲生領等、各地の検地を進めていました。前述の島津家の後嗣問題への関与は続いています。
日明和平交渉も継続中。
しかし、これは前提に無理がありすぎまして、文禄5年(1596年)に破綻してしまいます。
そんな中、おそるべき事件が起こります。
文禄4年(1595年)7月15日。高野山で関白の豊臣秀次が切腹してしまったのです。
しかも事件に連座して、関係者が大量に処断されました。
秀次の残された妻子(最上義光の娘・駒姫も含む)も、まとめて処刑されてしまいます。
これに三成が立ち会ったとされています。
幼子が母の胸から引き剥がされて刺し殺され、女性たちが斬首されていく光景を、一体どんな気持ちで見守ったのでしょうか。
従来、秀次はその悪逆ぶりや謀叛を企てたことから、切腹を命じられたのだとされていました。
しかし近年では、無実を証明する、あるいは精神的に耐えきれずに自ら切腹したとされるようになりました。
その事実を隠蔽するため、秀次に【殺生関白】という不名誉な名がつけられ、妻子を見せしめのように殺すという隠蔽工作が行われたのです。
ただでさえ親族、特に男子が少ない豊臣政権。秀次とその息子が生きていたら、どうなっていたことでしょうか。
三成が豊臣家をなんとしても存続させたいのであれば、関ヶ原より前に尽力することがあったのかもしれません。
いや、それは歴史を知る現代人の言葉で、当時の彼にしてみれば不可抗力でしかありませんね……。
黄昏の豊臣政権
秀次事件のあと、三成は加増されます。
秀次の知行のうち、近江7万石が代官地に。そして近江佐和山19万4千石の所領が与えられたのです。
また三成は、秀次の家臣団を自らの家臣団の列に加え、更には増田長盛と共に京都所司代に任命さています。
大名としての三成は、領民に細やかな指示を出し、善政を敷いたとされています。
多忙な三成に代わって、嶋左近清興らが領国支配にあたりました。
かくして三成は豊臣政権の屋台骨として、欠かせない存在になっていきます。
前述の通り、明との和睦交渉は破綻してしまいました。
そして失敗することは目に見えている朝鮮への再派兵が決まります。
造船そして伏見城築城と、三成はまだまだ働き続けねばなりません。
伏見城の普請の際に、三成が真田信之とやりとりした書状からは、彼が病気にかかったことがわかります。これだけ働いていたらそれも無理のないところでしょう。
慶長2年(1597年)、朝鮮への再派兵が始まりました。
総大将は、豊臣一門の若き貴公子・小早川秀秋。今回の派兵は明の征服ではなく、朝鮮半島の領土切り取りを目的としたものでした。
三成ら政権中枢にいる奉行は日本にとどまり、渡海した目付集が現地から戦況を報告するという体制です。
日本にいて現地の状況を知らない秀吉や奉行たちが、無責任に戦場へ命令してくるという状況は、確実に軋轢を生んだことでしょう。
「戦闘は会議室で起きてるんじゃない! 現場で起きてるんだ!」
まさにそんな状況だったはず。
秀吉政権そのものに冷たい目線を向ける者もいましたが、恩義があってそうはできない者もいます。
彼らの憎しみの矛先は、三成へと向かうわけです。
実のところ三成は、戦況を冷ややかに、悲観的にみていました。
政権としての計画では、実力で朝鮮半島に領土を獲得し、そこに九州大名を転封、空いた九州に毛利や宇喜多を転封するという構想を練っていました。
こうした計画を不安がる輝元に対して、三成は「そんなことにはならないだろう」と見通しを述べているのです。
政権中枢の実力者である三成すら、正面切って無謀な計画に異議を唱えられない異常な状況でした。
秀吉の死と三成の失脚
慶長3年(1598年)8月。問題山積の中、秀吉が世を去りました。
秀吉というカリスマを失い、餓狼の中に置き去りにされた赤ん坊のような状況に陥った豊臣政権。狼が舌なめずりをしている中で、三成はどうすべきでしょうか。
もしアナタが三成であれば、どのような選択が最善であったでしょう?
秀吉とて、死後のことを考えていなかったわけではありません。
彼は遺言を残していました。
後事を託されたのは、著名な五大老と五奉行です。
【五大老】
・徳川家康
・前田利家
・毛利輝元
・上杉景勝
・宇喜多秀家
【五奉行】
・前田玄以
・長束正家
・増田長盛
・石田三成
・浅野長政
奉行の一人として、政権運営を担当することになった三成。秀吉の死は秘され、しばらくの間五奉行は、秀吉の命令という形で政務を行いました。
そして三成らは、山積みの課題を消化していきます。
まずはともかく朝鮮半島からの撤兵および和睦交渉。秀吉が亡くなる前から朝鮮軍は反転攻勢を開始しており、撤兵は難しいものでした。
三成は10月に九州へ向かい、撤兵指揮を行います。
その二ヶ月後の12月には再度大坂に戻り、政権へ復帰。撤兵が終わってからも問題は続きます。
不平不満を抱えた大名たち相手の論功行賞や大名領の再編成をせねばなりません。無謀な唐入りで、大名たちの不平不満は頂点に達しています。
こんな状況で三成が無事に政務を行えるはずもなかったのです。
「五大老・五奉行」制度は、動乱の中で機能してはいたものの、危ういパワーバランスの上に築かれたものでした。
しかも慶長4年(1599年)はじめには、大老の一人である前田利家が死去。
この直後、彼を追い込む有名な事件が起きます。
七将(加藤清正・福島正則・細川忠興・浅野幸長・黒田長政・蜂須賀家政・藤堂高虎)に襲撃されたのです。
※家康書状に記された7名で、この他に池田輝政・加藤嘉明という説も
三成は伏見城の治部少丸に逃げ込み、難を逃れました。家康の屋敷に逃げ込んだという説は、史実ではありません。
近年、この襲撃事件は三成が家康暗殺を企んでいたことが前段としてあったとされる史料が見つかりました。
この史料を取り入れたのが、2016年大河ドラマ『真田丸』です。
結果、三成はこの事件の処遇として、佐和山城への隠退を余儀なくされてしまいます。
粉骨砕身して豊臣に尽くしてきたのに、政権から追放されてしまったのです。
凄まじい無念さであったことでしょう。
果たして三成はここからどうやって、再び豊臣を盛りたてようとしたのでしょうか……。
会津へ向かう家康、三奉行のクーデター
慶長5年(1600年)、秀吉の死からまだ二年も経ていないにも関わらず、家康は次なる天下人として力をつけていました。
この年、浮上したのが上杉景勝の上洛問題です。
上杉家は慶長3年(1598年)の時点で、越後から会津へと国替えを命じられていました。
しかし景勝はすぐに会津には向かわず、上方にとどまり大老の一人として政権運営の一端を担っていたのです。
三成隠退後、景勝は直江兼続とともに会津に向かいました。そして新たな領国で支配を固めます。
その矢先のことでした。
「景勝謀叛の恐れあり!」
上杉家を退去した藤田信吉から徳川側に一報がもたらされるのです。
ここで直江兼続が長い手紙(直江状)で徳川を挑発したか、してないか。その真偽は実は不明ながら、家康にとってみれば大老を排除する絶好の口実になることは確かです。
景勝と三成が連携しているという噂もありましたが、本当かどうか、確証はありません。フィクションではその方が面白いから、よく採用される説ではあります。
奉行たちは、家康の意見に唯々諾々と従うほかありません。
彼らも賛同して上杉討伐が決まりました。
この派兵はただの上杉倒しではありません。今や家康こそが天下に最も近く、彼に逆らえばどうなるか示す軍事行動でもあったのです。
かくして会津へと向かう家康。徳川の中枢が留守となった上方では、長束正家・増田長盛・前田玄以ら三奉行が動き始めました。彼らは……。
彼らは秀吉の遺言をないがしろにする家康を「内府ちがひの条々」にまとめて糾弾したのです。
さらに大老の一人・毛利輝元を大坂に呼び出します。
家康に対するクーデターとも言える行為でした。大老の一人・宇喜多秀家もこの動きに同調します。
三成はこうした徳川包囲網が整う中、ひっそりと活動を開始します。
公職から退いていた彼は、懇意の大名に私信を送り始めるのです。
三成の再起と誤算 「関ヶ原」への道
佐和山で隠居の身だった三成は、この機に乗じて奉行職に復帰。
8月には伏見城を落とし、大坂城へ。さらに佐和山に戻ると、出陣の準備を整えます。
三成は尾張から三河あたりで家康を倒すことを念頭に、戦略を練りました。
一方、徳川家康は上方の動向を知るとサッと軍を引き返し、軍勢を整えます。
上方の西軍が、政権のシンボル・豊臣秀頼を手にした以上、豊臣恩顧の将がこのまま従うのか、家康としては気になるところです。
フィクションですと「待ってました!」とばかりに軍を動かす家康像で描かれますが、実際は、味方のコントロールも十分でなかったフシが見て取れます。
要は、家康も内心では心臓バクバクだったでしょう。
「今後も徳川に味方するのか?」
「なれば行動で示すべし!」
かくして家康は、諸将に対して西へ向かうよう命じます。
言葉ではなく行動を求められた福島正則・池田輝政・細川忠興らは、電光石火の軍事行動で織田秀信(三法師)のいる岐阜城を陥落させました(岐阜城の戦い)。
さらに彼らは三成の大垣城まで攻めようとして、家康に止められます。
家康やその嫡男・秀忠の隊は出発が遅れています。
彼らが到着する前に豊臣恩顧の将に必要以上に活躍されても困るわけです。
江戸で様子を見ていた家康は、9月1日に出立するのでした。
小早川秀秋らの動向は早くから
三成の戦略としては、家康不在の間に畿内周辺を制圧するはずでした。
しかし上杉勢が背後から家康を衝く「挟撃案」は、そもそも上杉の背後に伊達政宗や最上義光がいたことを考えるとあまり現実的とは思えません。
もっとも三成は、伊達と最上の人質を確保している以上、自分たちに味方するハズだと真田昌幸宛の書状に書き記しています。
しかしその計算は狂い、もはや西美濃で両軍が激突することは不可避でした。
秀吉恩顧の将たちですら言い訳をしつつ家康に味方し、想定以上に苦しい戦況に持ち込まれた三成。
彼にとって最大の敵は、家康よりもいつ裏切るともわからない味方かもしれません。
増田長盛、小早川秀秋らの動向があやしいということは事前に把握していました。
秀秋は陣地でも最も重要な松尾山に無断で着陣。
優柔不断な秀秋が家康に射撃されたことで翻意したというよりも、むしろ裏切りを前提として最善の行動を取っていたのでしょう。
大老の一人として総大将を務める毛利輝元に至っては、大坂城から出ようとはしません。
両軍は関ヶ原に陣取りました。
長い乱世において最大規模の軍勢を指揮しているにも関わらず、三成が信じられる者はごく一部。
嶋左近清興
大谷吉継
宇喜多秀家
小西行長
島津義弘(ただし微妙な立場)
彼らは勇敢で誠実でした。
しかし、余りに少なかったのです。
決戦! 関ヶ原
決戦の日は、9月15日。午前10時頃、東軍の井伊直政が銃撃を加え、激戦が始まりました。
三成の本陣は、敵の激しい攻撃にさらされながらも、必死で防戦します。
彼らの奮戦ぶりは味方を勇気づけたことでしょう。
しかし、小早川秀秋だけでなく脇坂安治や小川佑忠らも裏切って戦況は一転。西軍は大きく崩れ、大谷吉継らが討ち取られていきます。
三成の本陣も崩壊。三成は再起を誓い、伊吹山山中へと落ち延びてゆくのでした。
居城の佐和山城は父・正継と兄・正澄が守っていました。
これも東軍に攻められて落城。
攻め込んだのが小早川秀秋を中心とする関ヶ原での裏切り者たち(朽木元綱・赤座直保・小川祐忠・脇坂安治)というのは、なんとも酷だなぁと胸が痛くなりますね。
このとき三成の正室が討ち死にしたという説もありますが、同城にはおらず生存していた説もあります。
伊吹山を逃亡していた三成は、田中吉政の追っ手によって捕まりました。
吉政が三成を丁重に扱ったところ、三成は形見に「石田貞宗」を贈りました。
かつて秀吉から下賜された名刀でした。
かがり火とともに消えた忠臣の命
ただし長男は助命されて出家。
二男は津軽家に匿われ、苗字を「杉山」と変えて仕官します。
三女は、弘前藩2代藩主・津軽信枚の室となりました。
非業の死を遂げた三成ですが、彼の子は厚遇を受けたのでした。
当時の人々は、三成に対する処分をおかしいと感じていました。
処刑そのものではなく、三成が総大将であったかのように処罰されたことに対して、です。
三成は確かに大きな役割を果たしましたが、西軍最大の責任者は毛利輝元であったはずです。上杉景勝も、慶長5年の軍事行動において三成と同等、あるいはそれ以上の責があるはず。
ところが彼らは助命されました。
三成は罪を背負わされ、死んでいったとも言えます。そして悪名もまた、背負わざるを得なかったのです。
豊臣秀吉は、異例の出世を遂げた「太閤はん」として人々に愛されました。
しかしその一方で三成は、秀吉の偉業を台無しにし、家康に逆らった奸臣として、あまりに不名誉な扱いを受け続けたのです。
かくして江戸時代を通して、奸臣の代表的存在とされてしまった石田三成。
しかしそんな時代にあっても、三成ゆかりの地に住む人々は、彼の名君ぶりをひそかに伝え続けたのでした。

冒頭にも書きましたが、現在は奸臣としての石田三成像は古いものとして認識されています。
人格的や性格的に問題があったというよりも、立場として憎まれ役にならざるを得なかったというのが実態ではないでしょうか。
圧倒的な不利の中でも豊臣家のためにぶれずに尽くし、そして散った彼の姿は、これからも人気を集めてゆくことでしょう。

 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













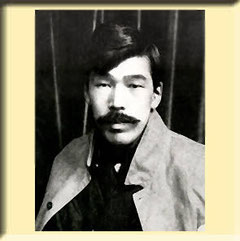














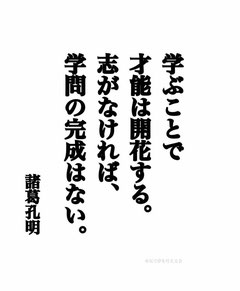

コメントをお書きください