―[家族に蝕まれる!]―
「宗教2世が世間を騒がせる事件を起こすたび、『先を越された』――そんなふうに思っていました。同時に、『自分が殺人犯になっている世界線もあったかも』などと本気で考えていました」 言葉を慎重に選びながら内面の葛藤を口にするのは、水野宏美氏(仮名・40代)だ。山上徹也被告による安倍晋三元首相襲撃事件を想起させる発言に驚くが、こちらの意図を察したようにこう続けた。 「もちろん、人の命を奪うことは許されないし、実行しようと具体的に考えたことはありません。けれども、宗教によって家庭や人生がめちゃくちゃになった人は多く、それを黙殺してきた社会に恨みを抱く人は相当数いると私は思います。極限まで追い詰められれば、大量殺人という過ちを犯す人がいたとして、不思議はないといまだに思っています」

「きちんとしているタイプではなかった」母
水野氏は、宗教を信仰する母親との縁を事実上断ち切った、宗教2世である。氏が母親を「おかしい」と感じたのは、かなり昔に遡る。 「母はもともとそそっかしいというか、あまり社会人としてきちんとしているタイプではなかったと思います。幼少期の記憶にあるだけでも、家や自転車の鍵をよく無くしたり、幼稚園に持っていくお弁当を忘れたり、細かいことかもしれませんが、『この人、大丈夫かな』というやや冷めた目で私は彼女を見ていました。 一方の私自身は、文字の読み書きが他の子どもより早い段階でできたり、人を見て発言や態度を変えるような感じの、やや大人びた子どもでした。母にとって“やりづらい”子どもだったのでしょう。当時から、折り合いはあまりよくなかったと感じます」
子の世話をせず、放置されたこともあった
とはいえ、殴る蹴るの暴力を受けた経験もなければ、信仰を強要された覚えもない。ただ純粋に、母親への違和感と不信感だけが募っていった。 「幼稚園生くらいのころから、心身ともに健康な他の母親とは明らかに違う部類の女性だなと感じていました。当時の私は、完全な放置子だったと思います。日中、母は寝ていて、私の世話などは一切しません。私は家にいても退屈なので、寝ている母を尻目に外出します。狭い集落で、だいたいの人が私を暖かく受け入れてくれたので、人の情みたいなものは他人から教わったのかもしれません。 放置といえば、実際に母と外出した際に置き去りにされたこともあります。本当に私を忘れていたようでした。そんなこともあって、当時からなんとなく、『母には、私や家族よりも大切なものがあるのではないか』とは漠然と思っていました」
「人を疑うことを知らない」からこそ…
その大切なものこそ宗教だが、宗教へすがりつくまでには、段階があった。 「母は、たとえば道に迷った人を家にあげたり、障害者を騙って物を売ろうとする人の話を聞いたり、とにかく人を疑うことを知らないような人でした。見も知らない他人を自宅に招き入れることにさほどのハードルがないようにみえました。母と暮らしていると、逆に私が人を警戒しすぎているのではないかと錯覚したほどです。 訪問販売などをはじめとして、母のもとにはいろいろな人が訪ねて来ましたが、それが宗教の勧誘になるまでにはそう時間を要しませんでした。病気や怪我が手かざしで治癒すると謳う宗教にはまったり、連日報道で話題になった宗教に加入していた時期もありますし、マルチ商法に傾倒したこともありました。そして、行き着いた先は、エホバの証人でした」
「母への興味関心は薄かった」父の存在
1992年の輸血拒否事件によってその名前を知る人も多いエホバの証人は、世界中に多くの信者をもつキリスト教系の新宗教である。 水野氏の父親は、妻の行動をどのようにみていたのか。 「父は寡黙ですが自分の考えをしっかり持っている人で、芯のある男性だったと思います。外見はヒッピーのようで、器用貧乏というのでしょうか、さまざまな職を転々としていました。そのたびに経済的な不安にかられた母と諍いになって、父が母を諭すように穏やかに話すのを聞いていました。 ただ、総じて母への興味関心は薄かったと思います。仕事に関しても家庭に関しても、自分が楽しめるかという軸で行動していた感があり、家庭人らしさはない人でした。父の不干渉が、母の信仰が加速した遠因にはなったかもしれません」 その父親の死をきっかけに、水野氏と母親は決裂する。
決裂したのは宗教のせいだけではない?
「母はエホバの証人の方式で葬儀を行いと言い出し、それを私が拒絶しました。復活を信じているエホバの証人では、喪服も着ません。これまで母親の宗教の都合に振り回されてきた不満が噴出した形です。直接的にはそれを契機として、交流が途絶え、実質的にはもう会話などもしていません」 宗教が絡むことによって孤立した母は暴走し、家庭は瓦解した。一方で水野氏は、「本当に宗教だけが原因だろうか」という冷静な視点も持ち合わせる。 「母は性的なことについて潔癖すぎるきらいがあり、恋愛についてもいい顔をしませんでした。たとえば、小学校のころに好きな子にラブレターを書いていたときのことです。それを発見した母は『なに、こんなものを書いて』と嫌悪感を露わにし、好意を持つことさえ否定しようとしました。また、たびたび体型のことを言われたり、第二次性徴の際には揶揄するような発言をやめなかったり、子どもの成長を喜ぶ母親像からは程遠いものがありました。 性的なものを忌み嫌うのは宗教の戒律なども無関係ではないかもしれませんが、それを差し引いても、彼女の深層に関わるような“重大事項”だったのではないかと今では思います」
母は性的虐待の被害者だった?
母との関係に悩み抜いた水野氏は、さまざまな文献を読むなかで、その“重大事項”の正体と思われるものを見つけた。 「母の母親(水野氏の祖母)は家庭を不在にしがちでした。推測でしかありませんが、祖父の性的な虐待の被害者になっていたのではないかと思います。ある文献には、母親が性的虐待の被害者である場合に、その子どもが自分の被虐待年齢に達すると、どのように世話をしていいかわからず養育が困難になることがある旨が報告されていました。私という存在を持て余したのも、あるいは無関係ではないかもしれません」 文献頼みの根も葉もない憶測だと一笑に付せないのは、水野氏自身にこんな経験があるからだ。 「私が小学校高学年になったころだと記憶していますが、母方の祖父とふざけてプロレスごっこのような遊びをしていました。すると、私の腰のあたりに祖父が股間を長いあいだ押し付けてきて、違和感を持ちました。当然、父ともそうした遊びをすることはありましたが、そうした行為は一切なかったからです」
たびたび「男の子に生まれたらよかったのにね」と…
「祖父の家庭内暴力などが原因で祖母は出ていったと聞いていますが、歪な性癖を持っていた可能性は否定できないと思います。また人格的にも、祖父は嫁をいびって鬱病にさせるなど、問題のある人だったとのちにわかりました。祖父はすでに他界していますが、私は見舞いにも葬式にも行っていません。 祖父からの性的いやがらせと思われる行為については、母を信用していなかったので報告していませんが、私のなかでずっと解決しないまま杭のように心から抜けない出来事のひとつです。そういえば、母が私にたびたび『男の子に生まれたらよかったのにね』とこぼしていたのも、意味があるように思えます」
子供を持つ選択肢を排除したのは“後遺症”
家族の姿から目を背けるように信仰に身を捧げ、絶縁した母親。一時は宗教の存在を憎しみ続けたという水野氏は、現在このように考えているという。 「私にとって家庭は安心感を得られる場所ではなく、母から愛情と呼べるものを受けた自覚もないまま育ちました。ずっとその根源には宗教があって、宗教によって私たちの家族は不幸になったと思っていましたし、そういう側面はあるでしょう。しかし、より根本には、母自身が宗教に頼らなければ生きていけないほどの傷を負って生活してきた歴史があると思います。 母は私にとっては加害者ですが、別の誰かの被害者かもしれない。そして何より、宗教2世が世間の耳目を集めるにつれ、似た思いを持つ人が大勢いることもわかりました。 こうした環境で育ったことが原因のすべてではないかもしれないけど、私は結婚はしているものの、子どもを持つ選択肢は最初から排除しました。自分と同じような子を増やしてしまうのではないかという不安が大きいからです。それは私の後遺症だと思うんです」 懊悩した過去を理性的に分析し、自分を翻弄した母親や宗教の背景にまで手を伸ばして向き合う女性の、強靭にも脆弱にもみえる本音がそこにはあった。 <取材・文/黒島暁生>
ライター、エッセイスト。可視化されにくいマイノリティに寄り添い、活字化することをライフワークとする。『潮』『サンデー毎日』『週刊金曜日』などでも執筆中。Twitter:@kuroshimaaki


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













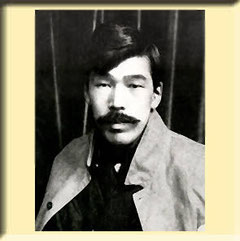














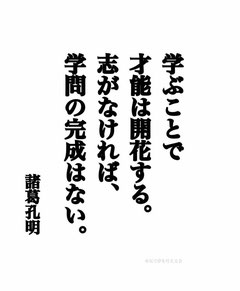

コメントをお書きください