「これまで、人を3人殺そうと試みました。両親と、それから……」 静かな口ぶりでそう話すのは、丘咲つぐみ氏。“虐待サバイバー”を支援する一般社団法人Onaraの代表にして、自らも虐待された過去を持つサバイバーだ。 Onaraに込めた意味は、オナラ。我慢を重ねれば病気になる可能性もあるが、かといって場所を選ばず放って良い性質のものではない。さしずめ、吐き出す場所の少ない感情の放屁、ということになろう。 3本のナイフを購入し、「刺し違えてやろうと構えていた」という冒頭の相手は、意外な人物だ。
生活保護のケースワーカーに暴言を吐かれ…
「当時住んでいた自治体の生活保護のケースワーカーです。30代に差し掛かったころ、生活保護を申請しました。しかしその方は『しっかりしたご両親がいるから、まずはご家庭でなんとかしてください』の一点張り。両親からの仕打ちを話しても、聞く耳を持ちませんでした」 生活保護の申請にあたって、親族による扶養が可能かどうかを確認されるのはさほど珍しくない。だがこのケースワーカーのやり方はその域を超えていた。 「役所のなかにある個室に連れて行かれ、机を叩かれました。椅子を蹴られて、『お前みたいなのが生活保護を受ける権利があるわけないだろ』『虐待されているのは、全部お前が悪いんだ』と責められました。 もちろん、生活保護の認否をそのケースワーカーが決めるわけではないので、『まぁそうは言っても申請は通ると思うけどな』と言ってその人は部屋を出ていきました。その後も、事あるごとにそのケースワーカーと関わらねばならず、暴言を浴びせられたのです」
「鍋で沸かしていたお湯」を母にかけられた
こうした体験が丘咲氏の根底にある諦めを根付かせた。 「かつて、私はその自治体の名前を見聞きするだけで精神的に参っていました。出身地を聞かれることすら嫌で仕方ない時期もありました。両親からの虐待にくわえ、社会さえも自分を見捨てたのだと考え、当時は希望がまるで見えなかったのです」 丘咲氏が受けた虐待の程度はかなり酷い。幼少期の記憶をこう振り返る。 「小学校低学年くらいのときだと思います。他愛もないような会話をしたくて、台所にいる母に『お母さん』と話しかけました。何度か呼んでも一向に振り向いてくれないと思ったら、いきなり鍋で沸かしていたお湯を肩にかけられたのです。熱いのとショックで何が何だかわからなくなりました。その後、『お前なんか産むんじゃなかった』と罵倒されました。幼稚園くらいのころから時折、『私の人生はお前のせいでめちゃくちゃになった』『お前のことは、奴隷にするために産んだんだ』などの罵声は浴びせられてきました」
重度身体障害者の伯父の存在は“秘め事”だった
それ以降もフライパンで殴打されるなどの虐待を日常的に受けた一方で、母親は丘咲氏に中学受験をさせるなど教養を身に付けさせようとした。 「中学受験以前も、3歳くらいから漢字の練習をするなど、教育への熱は高かったと思います。幼い頃からピアノのレッスンもしていました」 だがいずれも、母親が叶えられなかったことを代行している側面があった。 「母には重度身体障害者の兄がいたようです。私が生まれたときにはすでに他界していたその伯父の存在は、母の家族においての“秘め事”でした。したがって母は友達と遊ぶこともできないし、家に友達を呼ぶなどもってのほかで、ずいぶん制限された子ども時代を過ごしたようです。 また、母自身が、その伯父の面倒を見るために作られたような部分があって、本当は勉強がしたかったのに中学校も満足に通わせてもらえなかったと聞いています」
虐待を繰り返す母だったが…
丘咲氏と母親の関係が奇異なのは、虐待を繰り返しながらも、誰にも打ち明けられない事情や気持ちを丘咲氏だけに吐露している点だ。 「母は義両親から『女は家の中にいるべき』という価値観を押し付けられ、外で働くことを阻止されていました。それでも社会と繋がっていたかった母は、私が小さいころは家で内職をしていました。結婚前、いくつか職を渡り歩いたようでしたが、なかでもある時期まで公務員として勤務していたことを彼女はとても誇りに思っていました。私が中学生になったころ、母は再び任期つきの公務員に採用されましたが、見違えるほど溌剌としていました。 反対に、任期の終わりがみえてくるころには目に見えて元気を失い、彼女にとっていかに“働くこと”が大切だったのかわかりました。『家族さえいなければ、今で言うキャリアウーマンになれたのに……』という気持ちがずっとあったのだと思います。思えば、3つ年上の私の姉は、こうした話をほとんど知らないと思います。その代わり虐待も受けていないのですが」
母と向き合うつもりが、「記憶にない」と言われ…
高校生になったころ、丘咲氏は摂食障害になり、現在も完治はしていない。 「あるとき突然、食べることができなくなりました。過去にも心身症などで入院した経験がありますが、気持ちは元気なつもりでも、恒常的に家族関係に悩んできたため精神はボロボロだったのだと思います。ピーク時は体重が23キロまで落ち込み、生命活動も危ぶまれました」 渦中にいた丘咲氏が、物心ついたときから続く“しんどさ”の正体に向き合えたきっかけは難病による痛みだった。 「高校生のころから、脊髄のあたりに痛みを感じるようになりました。20代半ばになってから、数多くの医療機関を受診してやっとそれが脊髄の希少難病だとわかるのですが、当時は身体に異常が見当たらないために精神科を受診させられることがありました。そこで出会ったカウンセラーのおかげで、摂食障害が家族関係に起因していることに気づくことができました。 以前も母との関係を何とかしなければならないと思って、自分の気持ちを彼女に伝えたことはありました。しかし過去の虐待の話になると、母は『記憶にない』と白を切りました。 カウンセラーからの『お母さんに話したいことを伝える機会を作ろう』という提案で、母との対話を試みましたが、母は部屋を無言で出て行ってしまいました。自らの加害に向き合わない母をみて、アプローチしても傷つくだけだとはっきり自覚しました」
病状が進行し、寝たきり状態に
…
23歳で結婚をし、出産を経てシングルマザーとなった丘咲氏は、脊髄の希少難病によって、徐々に立つことすらままならなくなっていく。一日の大半を寝た状態で過ごさざるを得ないこともあった。手術によってある程度治癒するものの、そこに至るまでの日々は険しいものだった。 現在では当時より症状が和らぎ、少しの距離であれば補助具なしに歩くことができているものの、常に痛みと痺れにつきまとわれる生活は変わっていない。病気の発症当時、手術に至るまで心労は絶えなかった。 「病気が猛威を奮い始めた20代後半、介護ヘルパーの資格を持つ母に介助をお願いすることがありました。しかしかけられた言葉は、『車椅子なんてみっともないから外に出ないで』『近所の人には見られないようにして』というものでした。 30歳に差し掛かって生活保護を受けるようになると、母には助けを求めなくなりました。そのころの私は、自力でトイレに行くこともできず、尿も便も垂れ流し。それでも、母に頼るよりは気が楽でした。買い物もほとんどはネットスーパーを使っていましたが、まだ幼かった子どもにお使いを頼むこともあったので、いわゆるヤングケアラーだったと思います。 困ったことは多数ありますが、生活保護受給者は原則として車の所有が認められていないのが痛手でした。当時、両足が不自由な方でも運転できる仕様に改造した車を所有していましたが、これも手放さざるを得ず、最終的には通院もできなくなってしまったのです」
ナイフを握りしめ「1時間ほど自動ドアの前に立っていた」
自助も壊滅し、さりとて公助にも期待はできなかった。 「ある日、これ以上痛みを我慢できないという限界まで耐えて救急車で運び込まれました。結果としてはそこで入院し、治療を再開することができました。例のケースワーカーが来て、『あんたはどうなっても良いんだけど、子どもがいるからな』とぶつぶつ言っていたのを覚えています。私の手を握っていた子どもをケースワーカーが無理矢理引き剥がしたため、子どもは大声で泣いていました」 すべてから見放された。すべてが敵なのだ――丘咲氏がそう感じたところで、冒頭に戻る。気がつけば、ナイフを握りしめて役所の前に立っていた。 「ケースワーカーを殺して自分も死のうと思い、1時間ほど自動ドアの前に立っていました。しかしニュースになったとき、私がただの悪者になって終わるんだなと思うと、悲しい気持ちになり思いとどまりました。また両親を絶対に刺してやろうと実家に向かったはずなのに、見慣れた光景がしんどかった日々に重なって、断念しました。今があるのは、そのときのフラッシュバックのおかげだと現在では思えます」
闘病中に税理士の資格取得を決意
丘咲氏は闘病中、28歳で資格試験の取得を目指した。雑誌を購入し、右も左もわからないまま、数多ある資格から選んだのは税理士。在宅での仕事が可能で、子どもを育てられるだけの収入が決め手だ。 「当初、大手税理士事務所に所属していましたが、自分がやりたかった虐待サバイバーの支援活動をしていくうちにNPO法人などからも仕事をいただくようになりました。一般企業とNPO法人などは会計の手法がまったく異なります。不思議な縁で、私はどちらも扱える税理士になることができました」
虐待サバイバーでも「幸せな家庭を築くことはできる」
現在、丘咲氏はかつて自分を虐待した両親を恨んでいないという。 「私は両親が好きで、コミュニケーションをしたくて、けれども両親は残念ながら子どもに愛情を傾けることのできない人たちでした。母は自分が思うように生きられない原因のすべてを家族にしたがる人で、有形無形の暴力を受けて育った私は、いつしか彼女に怯えるようになりました。けれども、今なら母もまた母の家族のなかでの犠牲者だったんだなと思えます。案外、私の人格に母以上に影を落としたのは父のほうで、被害事実に向き合うまでに私もかなりの時間を要しました。 『虐待が連鎖する』というパワーワードが独り歩きし、虐待されて育った人のなかには結婚や出産をためらう人が少なくないと思います。しかし、きちんと被害事実を受け止めることができて、次の世代に波及しないようにしたいと心から願うことができれば、連鎖への抑止が期待できると思います。これらに加え、信頼できる支援者に繋がることができて、心理的ケアを受けることによってトラウマを回復させることができれば、虐待サバイバーであっても幸せな家庭を築くことはできると私は思っています」 握りしめた手のうちに刃物を忍ばせ、悲しげに殺意をにじませていた丘咲氏はもういない。声をあげ、社会と積極的に繋がることで得た、仲間や資格という武器。今度はその切っ先で、虐待支援の新境地を拓く。 <取材・文/黒島暁生>


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













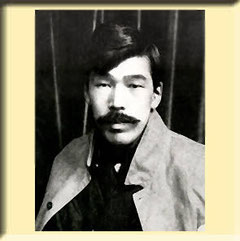














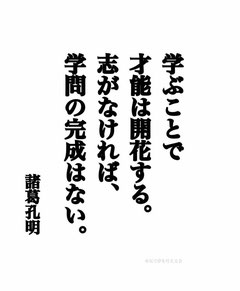



コメントをお書きください