
人呼んで「浅草の師匠」、昨今は「ビートたけしの師匠」として知られる浅草芸人・深見千三郎(1923~1983)とはいかなる芸人だったのか――。その訃報が伝えられた時、弟子のビートたけし(76)は秀逸なコメントを残しています。「バカだなぁ。もう少したてば他人が焼いてくれるのに、てめぇで焼いちまいやんの……」。朝日新聞編集委員・小泉信一さんが、様々なジャンルで活躍した人たちの人生の幕引きを前に抱いた諦念、無常観を探る連載「メメント・モリな人たち」。数多の伝説に包まれた「最後の浅草芸人」の素顔に迫ります。
最後の浅草芸人
華やかなテレビや映画の世界に転身し、有名になったコメディアンがいる。身を持ち崩し、孤独な末路を迎え、無名のまま終わった芸人もいる。
映画館や演芸場、ストリップ劇場が立ち並び、「大衆芸能の聖地」と言われた東京・台東区の浅草六区興行街。実に多くの芸人が、この街から巣立ち、さまざまな人生を歩んだ。
一方、かたくなに浅草にこだわり、浅草で生涯を終えた芸人もいる。伝説のコメディアン・深見千三郎もその一人である。無名時代の萩本欽一(82)を支え、コメディアンを目指していた青年・北野武(ビートたけし)をゼロから叩き上げた男だ。
マシンガンのように畳みかけていく話術のスピードとリズム感。都会的なオシャレ感覚とセンスの鋭さ。「飲む・打つ・買うは芸のこやし」と堂々と言ってのけ、それを実行する度胸の良さ。飲み屋でも、支払いは必ず、勘定の倍くらいのカネを払った。「それが芸人の粋だ」と心得ていたのだろう。
本名・久保七十二(くぼ・なそじ)。浅草芸人に関する「生き字引的な存在」でもあったライターの吉村平吉(1920~2005)が生前、私に語っていたのだが、深見こそが「最後の浅草芸人」だった。
たけしは著書「浅草キッド」(講談社文庫)の結びに書いている。
《有名になることでは師匠に勝てたものの、しかし最後まで芸人としての深見千三郎を超えられなかったことを、オイラはいまも自覚している》
師匠に対する尊敬の念は、今でも変わらないのだろう。
さて、「最後の浅草芸人」とは、実際どのような意味を持っているのか。
深見は浅草の名物ストリップ劇場「フランス座」(現・浅草フランス座演芸場東洋館)の経営者でもあったが、浅草の街は1960年代の高度成長期以降は斜陽化をたどっていた。新宿、渋谷、池袋などの歓楽街と比べると、若者向けの娯楽施設も少なく、取り残された感は否めなかった。
性産業も多様化する中で、古く暗いイメージがつきまとっていたストリップ劇場も閑古鳥が鳴く日々だ。
「俺ももう年」
深見は1981年6月に劇場経営から手をひくと同時に、芸人としても引退した。まだ58歳だった。
知人の元コメディアンが経営する化粧品会社に就職。と言っても、顧問のような仕事で、毎日出勤することはなかったようだ。愛弟子のたけしもだいぶ前に独立し、72年にビートきよし(73)と「ツービート」を結成。浅草から巣立っていった。

運命の夜
深見が引退して1年ほど経ったころ、奥さんがひっそり息を引き取る。踊り子時代から酒好きで、アルコール中毒になり、命を縮めたという。
奥さん、たけし……。身近な人たちが次から次へと離れていった。
深見に残ったのは「元芸人」という肩書だけである。道端で人と会えば、「師匠、元気ですか?」と誰からも声を掛けられたが、やはり現役で舞台に上がりたかったに違いない。
そして、「運命の夜」がやってくる。
83年2月2日の朝日新聞夕刊は「浅草コメディアンの師匠焼死」という見出しで、こう伝えている。
《二日午前六時半ごろ、東京都台東区浅草三丁目、第二松倉荘の四階四十六号室から出火、同室約十七平方メートルが全焼した。この火事で同室の会社員久保七十二さん(59)が焼死体で見つかった。
東京・浅草署の調べでは、久保さんは深見千三郎の芸名で、十七歳の時から浅草でコメディアンとして活躍、故堺駿二や東八郎らと一緒に舞台にも立った。四十五年から五十六年まで軽演劇、ストリップ劇場で知られた浅草フランス座社長。その後、ビートたけしを見いだし、育てるなどし、浅草育ちの芸人の面倒をよくみたという。(中略)
同署は、六畳間の真ん中に、焼けた石油ストーブがあったことなどから、たばこが原因ではないか、として調べている》
深見は愛妻を亡くしてから急激に酒量が増えたそうだ。浅草演芸ホールを運営する東洋興業会長の松倉久幸氏(87)は振り返る。
「『千さん、あんまり深酒はしないほうがいいよ』と何度か言った覚えがあります。でも、聞くような人じゃありませんでしたね」
おそらく、火事が起きた日も、あちこちの店をまわり、飲み歩いたのだろう。深い孤独の影が、最後の浅草芸人に忍び寄る。泥酔したのだろう。「歩いて帰れるだろうか」と心配した人もいたという。
深見はアパートまでたどり着き、4階の自分の部屋まで這うようにして上がっていったに違いない。先述した松倉会長は、こんな見方をしている。
「誰もいない真っ暗な部屋に入り、明かりもつけないまま座り込んで、酔いでふらつきながらたばこに火をつけたのだろう」
要するに、寝たばこの火が布団に燃え移ったという説である。取材を進めると、アパートの同じ階で暮らしていた男性がきな臭いにおいがするのに気づき、深見の部屋まで駆けつけたところ開いた状態のドアから炎が出ており、中から悲鳴が聞こえたため119番通報したという。
必死に逃げようとした深見。だが、外に逃げることはできなかった。警察によると、ドア近くで深見は焼死体となって見つかった。アパートには19世帯が入居していたが、他の入居者にけがなどはなかったという。
深見の焼死をフジテレビの「オレたちひょうきん族」の収録中の楽屋で聞かされたのがたけしである。全身が打ちのめされ、膝がワナワナと震えだしたという。「古き良き浅草を知る人がまた消えてしまった」と浅草の人たちは深見の最期を惜しんだ。

「バカヤロー」に込められた意味
さて、ここで遅ればせながら深見の経歴について触れたい。
北海道北部の漁村で1923(大正12)年に生まれた。屋根葺き職人の父は、元は一座を率いたこともある芸人だったという。その血が流れていたのか、姉は上京して「美ち奴」という名前の芸者歌手になり、「あゝそれなのに 」というレコードも出した。
その姉を頼り、1938~1939(昭和13~14)年ごろ、深見も上京。浅草に入り浸るようになった。姉の紹介で時代劇の大スター・片岡千恵蔵(1903~1983)に弟子入り。京都の太秦で役者修業のスタートを切る。
1年ほどで浅草に戻った深見は、浅草六区にあったオペラ館の青年部に入る。だが、戦争の影が忍び寄り、軍需工場に徴用。作業中の事故により機械に左手が巻き込まれ、4本の指の第2関節から先を切断。役者にとっては致命的な傷を負った。
1945(昭和20)年の敗戦を機に、深見は一座を旗揚げし、各地で巡業したという。けがをした左手は、観客に気づかれないよう相当神経を使ったに違いない。やがて時代モノであれ、現代モノであれ、自在にこなす役者になった。
だが、女性問題を起こしては、追われるようにそこを立ち去る。その繰り返しだったが、やがて浅草のストリップ劇場「ロック座」の座長となり、浅草に腰を落ち着けるようになった。そこで可愛がったのが東八郎(1936~1988)だったが、フランス座に移り、たけしを育てたのはもう少し先の話である。
いずれにしても、スピード感あふれる突っ込みと毒舌、客とケンカをしながら笑いをとる芸は、浅草芸人の誰からも一目を置かれるようになった。
その深見をNetflix映画「浅草キッド」(2021年12月配信)で、人情たっぷりに好演したのは大泉洋(50 )。深見の口癖の「バカヤロー」には肯定も否定もあり、さまざまなニュアンスがにじみ出ていた。大泉は言う。
「(深見さんは)照れ屋で滅多に人を褒めない。うれしくても『調子に乗るな、バヤカロー!』と怒鳴ってみたり、心とは逆のことを言ってしまう、まさに不器用な昭和の芸人さん。僕とは生き方がまったく違うけれど、『こんな風に言えたらかっこいいな』という憧れはありますね」
ダンディズムと言ったらいいのだろうか。渥美清(1928~1996)にしろ、萩本欽一にしろ、浅草出身の芸人は、どこかしら爽やかな格好良さというのを身にまとっていた。浅草を笑いのるつぼとし、駆け抜けていった先人たちの息づかいは、脈々と次世代に受け継がれていると言っていいだろう。
次回は全身白ずくめで横浜の街角に立っていた娼婦・ハマのメリーさん(1921?~2005)。姿を見かけた人は数え切れない。写真も残っている。だが、実像に迫ろうとするほど遠ざかってしまう謎に満ちた女性。通称「ヨコハマメリー」。故郷は中国地方だったというが、彼女は一体何者だったのか。




 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













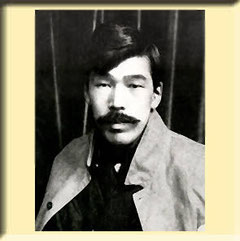














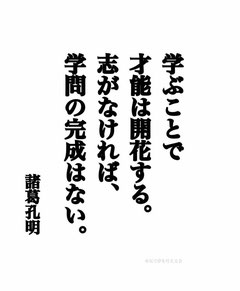

コメントをお書きください