落語家、桂二葉は女性の帯の締め方で、高座に上がる。女性なら当たり前のようだが、落語界では少数派だ。2021年、「NHK新人落語大賞」で大賞を受賞、一挙にブレイクしたのは、50年超の歴史で初めての女性だったから。その上、記者会見で口にしたのが、「ジジイども、見たか」だったから。そんな二葉の熱き落語愛、どうぞお見知り置きのほどを。

7月20日、有楽町朝日ホールでの落語会。前座に続いて登場した桂二葉(かつらによう・37)の1席目は「幽霊の辻(つじ)」、次いで笑福亭鶴瓶(しょうふくていつるべ)が登場、「芝浜」で仲入りとなり、明けて二葉の2席目。
「おい、らくだ、らく、いてへんのかいな」
上方落語を代表する大ネタ「らくだ」が始まった。その瞬間、会場から落語会では珍しいどよめきが起きた。観客一人ひとりの「おっ」が重なって「おー」となる。そんなどよめきだった。
「らくだ」という嫌われ者が長屋で死んでいるところから始まる噺(はなし)だ。見つけたのは、らくだに輪をかけたろくでなし「脳天の熊五郎」。通りがかった紙屑(かみくず)屋を使い、葬式の準備をする。ところが酒を飲んだ紙屑屋が、突然豹変(ひょうへん)し……。
この日は途中まででまとめたが、演じ切れば1時間近くなる。熊五郎の狼藉(ろうぜき)ぶりは飛び切りで、女性落語家が演じることはほとんどないネタだ。
初演は2023年2月、「桂二葉しごきの会」(ABCラジオ)だった。「しごきの会」は上方落語の未来を背負う若手を鍛えるという趣旨で、1972年に始まった。初回は桂小米(こよね・のちの枝雀(しじゃく))で、二葉は15人目にして初の女性。そんな経緯も含め、「おっ」となったというわけだ。
簡単に二葉の経歴を紹介する。
入門は11年、師匠は桂米二(よねじ)(65)。米二は桂米朝(べいちょう・人間国宝、15年没)の弟子だから、米朝の孫弟子だ。上方落語には真打制度がないが、大賞を取った「NHK新人落語大賞」の出場資格は「二つ目(大阪の場合は同程度の芸歴)」だ。東京の大賞受賞者を見ると、受賞から数年で真打になっている。

ちなみに「NHK新人落語大賞」は何度か名前を変えているが、ルーツは72年。二葉は21年、天狗(てんぐ)をつかまえてすき焼き屋をしようと思いつくアホが活躍する噺「天狗さし」を演じ、大賞を受賞した。受賞後の記者会見の最後の方で「ジジイども、見たかっていう気持ちです」と言った。本人によれば「可愛い感じ」で言ったそうだが、ニューヨーク・タイムズにも取り上げられた。そこからは破竹の勢い。今年3月には「探偵!ナイトスクープ」(ABCテレビ)の探偵にも選ばれた。
大人の感覚に敏感な子ども 母は「アホやなー」とほめた
さて、冒頭の落語会に戻る。演芸写真家・橘蓮二がプロデュースする「桂二葉チャレンジ!!」シリーズの4回目だった。22年10月にスタート、初回の相手は春風亭一之輔(しゅんぷうていいちのすけ)、次が春風亭昇太(しょうた)、柳家喬太郎(やなぎやきょうたろう)、そして鶴瓶で「最終章」。4回すべて満席でこの日、大入り袋も配られた。動員数は延べ3千人になる。
二葉の武器は明るく高い声。自然で自在な声にのせ、得意ネタは「アホ、子ども、酔っ払い」。入門からしばらくアフロヘアにしていたのは、「女性落語家」と思われるより先に「アホっぽい」と思われたいからで、一門の集まりで対面した米朝に「はやってんのか?」と尋ねられたという伝説も持つ。その上「ジジイども、見たか」だから、根っから大胆な人物に違いない──。
ところが二葉、大人の感覚に敏感で、話すのが苦手な子だったという。例えば保育園の卒園アルバムの「将来の夢」。「あるわけないやろ」と思ったが「ケーキ屋さん」が正解だとわかっていたからそう言った。ランドセルも黒がよかったが、赤を選んだ。その点、3歳下の弟は将来の夢を「忍者」と言い、茶色で横型のランドセルを選んだ。「男の子ってアホやから、余計なこと考えずに言ったり選んだり、えらいなって思ってました」
二葉の両親が事実婚だということは、「ジジイども、見たか」と共に有名になった。二葉が弟に「男のくせに泣いてる」と言うと、「男も女も泣くやろー」と言った母。勉強が苦手で「N」と「M」の区別がつかない二葉に「Mは1本、多いねんで」と根気よく教えてくれた。勉強が得意だった弟の西井開(34)は臨床心理士になり、『「非モテ」からはじめる男性学』などの著書もある。
西井によれば、58年生まれの母はウーマンリブやフェミニズムに触発され、「規範」から解放されることに肯定的、または促す人だった。優等生の西井が学校で「いい子」と評価されると「おもんない」と言い、連絡帳に書かれた先生の記述を消した二葉には「アホやなー」とほめた。父は学童保育の指導員で、2人はその学童に通っていた。
女性落語家への違和感 自分は嘘なくアホができる
西井の観察では、父の手前ヤンチャに振る舞えない二葉は、学童の“アホなお兄さん”への憧れを強く持っていた。その一方で身体能力が高く、学童で取り組んでいた和太鼓が群を抜いてうまく、発表のたびに圧倒的に目立ったのが二葉だった。
アホ=愛嬌(あいきょう)ある目立ちたがり屋への憧れに、和太鼓で注目された原体験があるから、「落語家になるって聞いた時、違和感はありませんでした」。
二葉を落語に結びつけたのは、実は鶴瓶だ。大学時代、「きらきらアフロ」というトーク番組を見て好きになり、追っかけになる。落語会にもすぐに行き、他の落語家も見るようになった。女性落語家を見ると違和感を覚え、その理由を知りたくて全員を見に行った。無理をしている、特にアホな人を演じると痛々しい。そうわかった。
「いけると思いました。自分がアホやという自信は子どもの時からあったけど、言えずに来た。でも落語でならできる。自分なら嘘(うそ)なくアホができる」。入門に備え貯金をしようと就職、師匠を探して米二にたどりついた。
毎日新聞大阪本社学芸部記者の山田夢留(むる)(46)は、駆け出しの頃の二葉の言葉にハッとさせられた。「女性というのは、アホと距離がある」。すごく腑(ふ)に落ちた。小さい頃から面白いことを言うのは男の子で、女の子は「しっかりしなさい」と育てられる。だから女性がシンプルに面白いことを言っても、見る側が「女性」というフィルターを通すから笑えない。今も「痩(や)せてる」「太ってる」をネタにしがちな女性お笑い芸人のことなども含め、「笑いとジェンダー」が氷解する一言だった。
目標としたら、がむしゃら 怒りをパワーにするタイプ
この人はすごい噺家(はなしか)になる。そう感じ、初めてインタビュー記事を載せたのが16年8月。19年4月からは「勝手に大阪弁案内」という二葉の連載を始めた。2回目に二葉が書いたのは「いちびり」。はしゃいだりふざけたりを堂々とできるけど愛嬌がある、アホな子どものことだ。
師匠の米二はなぜかアフロヘアで落語会に通ってくる二葉をおもしろいと思い、着物の着方も二葉に任せた。「彼女のアホは、ええアホやと思います。ほんまにいたら難儀やけど、見ててにこやかになれる。アホもいろいろいますから、極めていきたいんでしょうね」
米二が語る修業時代の二葉は、健気(けなげ)で可愛い。いわく、初めて稽古をつけたら何もわかっていなくて驚いた、あれだけ自分の落語会に来ていたのに、上手(かみて)も下手(しもて)も知らなかった、目の前の自分を真似(まね)るので左右が逆になるから、並んで稽古をすることにした、台詞(せりふ)覚えもすごく悪い、ところが覚えると、これがなんとなく落語になっている。
「なんとも言えないおかしみを感じました。我々の方ではそれを、フラがあるっていいますが」
1年ほどしたら、稽古中に泣くようになった、想定外だったが、それで女は面倒だとは思わなかった、悔しいからだとわかったし、泣きやんでもまた泣くから、稽古は「もう今日あかんな、今日やめとこな」と……温かい語り口が心に響く。
米二がほめるのが、二葉の根性だ。上方落語協会主催の「上方落語若手噺家グランプリ」、「上燗屋(じょうかんや)」で初めて決勝に残った18年、「どこがあきませんでしたか」とすぐに聞きに来た。
「目標としたら、がむしゃらにくらいつく。3人いてる弟子の中で、根性は一番です」
前出の山田も「若手噺家グランプリ」の二葉を覚えている。準優勝した21年、出場者全員が並ぶ結果発表でのことだ。舞台上の二葉はひとり、憮然(ぶぜん)とした表情で立っていた。気楽に話せるようになっていたので、客前であんな土気(つちけ)色の顔はどうだろうと言ってみた。「負けた時にニコニコできひん」と返ってきた。
二葉が賞レースへの思いを強めたのは、米二の語った「若手噺家グランプリ」だった。初めての予選通過がうれしかったし、自信がついた。
「女も落語できるんやでって証明したかったし、賞をとったら一つ認めてもらえる。いいきっかけになりました」
前出の西井に、二葉の人気はどこから来ると思うかと尋ねた。少し考え、「怒りみたいなものがあるような気がします」と返ってきた。女に落語ができるのか、女の落語家だから聞かなくていい。そういうことを言われると、時おり二葉は西井に電話をかけてきた。会話から彼女が女性差別への関心と、道を開いてきた先輩女性落語家へのリスペクトを高めていることが伝わってきた。
「アホをやりたいと落語家になったのに、『女性落語家』という薄い膜の中に閉じ込められている。そんな感覚があるのかなと思いました」
二葉はこう語る。
「確かに怒りをパワーにするタイプだと思います。何で自分の思ってる落語ができないのとか、なんでこんなおもろい落語やってんのに認めてくれへんねんとか。『女流』って言葉もすごく嫌やったけど、そういうことも勝ってから言おうと思いました。勝っても勝たなくても言うべきことは言うたらええと思うけども、やっぱり説得力は違うし、それは勝ってからやなって」
賞をとるための戦略を、ある時からすごく考えるようになったと二葉。「私の研究によると」と照れたように言って、NHK新人落語大賞の「傾向と対策」を語ってくれた。
(1)お行儀の悪い感じは嫌い→酔っ払いネタはダメ(2)“正しい”ものが好き→夜這(よば)いなどのネタはペケ(3)長い話を上手にまとめるのは好き→20年、「佐々木裁き」で決勝進出、力及ばず(4)予選はNHKの人が相手→牧村史陽著『大阪ことば事典』に触れる(5)決勝はウケたもん勝ち→事典ははずし、言いたいことを言う。
二葉の戦略は、懸命さの表れでもある。
動楽亭は米朝一門の桂ざこばが席亭をする寄席(よせ)小屋だ。毎日6人の落語家が日替わりで出る昼席に、弟弟子の桂二豆(にまめ)が出るようになっても二葉には声がかからなかった。女性の先輩も出演したことがあったようだが、長く「男性のみ」になっていた。「もうええわって思てたんですけど、途中でええわちゃうなって思って」。出番はなくても動楽亭に通い、楽屋仕事を一生懸命やった。
続けていると1人の先輩がざこばに、「二葉も出してはどうか」と言ってくれた。ざこばは電話を取り出して、一門の落語家が多く所属する米朝事務所の社長と相談を始めた。「ここは押さな」と思った二葉、「頑張ります」と横から言った。電話が終わり、出演が決まった。
「ありがとうございますって、泣きましたね。うれしいっていうのか、悔しいっていうのか、小さい薄い壁やけど、なんかちょっと壊せたみたいに思ったから」
20年1月、初出演。22年9月に米朝事務所を辞めるまで出演した。
毎週火曜日放送の「ま~ぶる!桂二葉と梶原誠のご陽気に」(KBS京都ラジオ)は二葉にとって初の看板番組だ。ディレクターの大坪右弥(26)は、ラジオでの二葉の魅力は「嘘をつかないこと」だという。みんながうなずく場面でも、違うと思えばうなずかない。だから信頼され、全国からメールが来る。
NHK新人落語大賞受賞後、「私の周りのジジイども!」のコーナーを作った。二葉の声は「怒り」をポップに柔らかくする、大賞受賞で自信と解放感が増したように見える、と大坪。
「らくだ」の話に戻る。「しごきの会」と「チャレンジ!!」で、二葉は台詞を変えている。一つは紙屑屋が酔って自分語りをする台詞。道具屋を構えていたが、酒のせいで紙屑屋になった。最初の妻は「いいところ」から嫁に来たという場面。
「前のかか、女一通りの道、みんなできた。縫い針、茶、花。けど貧乏慣れしてなかった」
それをこう変えた。
「前のかか、縫い針、茶、花、みんなできた。けど貧乏慣れしてなかった」
ずっとメラメラしている 毎朝、米朝の写真に感謝
「女一通り」をなくした。最初は教わった師匠通りにするのが礼儀だから、すべて忠実に演じた。それを2回目から外したのは、「なんか引っかかるし、別に言わんでもいいかなと思って。引っかかったままやると、嘘っぽくなるので」。気になる言葉は他にもある。「『嫁はん』とか言いたくないんです。『奥さん』もあまり言いたくない。できるだけお名前で呼んだりしてるんですけど」
登場人物に「お名前」と言う二葉。「お玄関」に「お師匠はん」「おネギ」も聞いた。母の話は「身内の話であれですが」と言ってからし、「米二師匠が『らくだ』をほめていました」と言うと、「親バカみたいですみません」と反応した。そんな品の良さが落語ににじむ。という話はさて置いて。
噺ごと腑に落ちないものもある。たとえば「立ち切れ線香」。芸妓(げいこ)に入れ上げた大店の若旦那が仕置きとして蔵に閉じ込められ、来なくなった若旦那を待ち焦がれた芸妓が死んでしまうという噺。ツッコミどころ満載のようだが、今も演じる落語家は多い。米朝が語り、枝雀が舞台袖で涙したというエピソードもある。
二葉は、「どの辺に心が動いたのか、聞いてみたいです。不思議やわ」と言いつつ、「ちょっと挑戦してみたくなるんです」と言う。「立ち切れ線香は上方落語屈指の人情話」、そう聞くと心が揺れる。こういう「古典」を、どう残していくのか難しい。それでも古典落語にこだわっている。
「古典がうんとうまい女の人って、あまりいないじゃないですか。そこへの欲があるんです。醍醐味(だいごみ)があります。たまらなくワクワクします」
かつては朝まで飲んでいたという二葉だが、もう2年以上、飲んでいない。「なんかもう、飲もうって思わへんのです。酔っ払ってる暇がない。ずっと考えていて、なんかメラメラしてます」
目下の悩みは忙しさだ。大阪より東京で落語の仕事が増えている。上方落語が大好きだし、盛り上げたいのに「本末転倒」だとジレンマを口にする。自転車操業になっている、ネタがたくさんあるわけではないから、「あかんなと思ってます。ほんまに地道に覚えなあかん」。
二葉の自宅玄関には、米朝の写真が飾られている。だってスーパースターですから、と。たくさん話を復活させて、今につなげてくれた、各地で独演会をして、お客さんを育ててくれた、すごいことです、毎朝「ありがとうございますっ!」と言って家を出ます。そう息急き切ったように話す。
二葉にこれからのことを聞くと、「5年、10年後はわからへんけど、90ぐらいの自分は」見えているという。点滴をしながら高座に上がり、最後まで滑稽な噺をして死んでいきたい、と。
「もっとうまくなりたいです。自分の言葉で、まっすぐに声が出る。そういう落語ができたらなって思います。伸び代が、えげつなくあります。それがわかってきたから、すごく楽しみです」
高く明るい声だった。(文中敬称略)(文・矢部万紀子)
※AERA 2023年9月11日号
矢部万紀子
矢部万紀子(やべまきこ)1961年三重県生まれ、横浜育ち。コラムニスト。1983年朝日新聞社に入社、宇都宮支局、学芸部を経て「AERA」、経済部、「週刊朝日」に所属。週刊朝日で担当した松本人志著『遺書』『松本』がミリオンセラーに。「AERA」編集長代理、書籍編集部長をつとめ、2011年退社。同年シニア女性誌「いきいき(現「ハルメク」)」編集長に。2017年に(株)ハルメクを退社、フリーに。著書に『朝ドラには働く女子の本音が詰まってる』、『美智子さまという奇跡』。


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













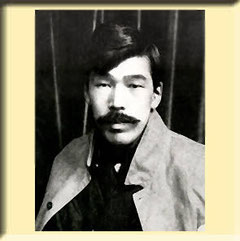














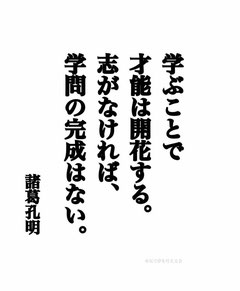



コメントをお書きください