社会風俗・民俗、放浪芸に造詣が深い、朝日新聞編集委員の小泉信一氏が、正統な歴史書に出てこない昭和史を大衆の視点からひもとく。今回は、口上と芸で稼ぐ職能人「テキヤ」。
1928(昭和3)年、東京の下町で生まれた故・渥美清(本名=田所康雄)は戦後の混乱期、闇市が並んだ上野の「アメヤ横丁」かいわいでよく遊んだ。祭りや縁日があると、テキヤのタンカバイ(啖呵売)を一つひとつノートに書き写し、頭にたたき込んだそうである。
たとえば「黒い、黒いはナニ見てわかる。色が黒くて、もらい手なけりゃ、山のカラスは後家ばかり……」。少々品がないが、こんな口上もあった。
「四谷赤坂麹町、チャラチャラ流れるお茶の水、粋な姐ちゃん立ち小便……」
トントントンと、たたみかけるような七五調のリズム。意味がわからなくても心地よくすーっと耳に入ってしまい、思わず財布のひもをゆるめてしまう。見るからにあやしげなのに、どこか愛敬のあるテキヤが昭和の街にはあちこちにいたのである。
私が育った門前町の川崎大師(川崎市)でも、祭りや縁日ともなると、そこだけが「異界」のような空間が現れた。
「人か獣か?」
「胴体一つに頭が二つ」
たしかそんな言葉が書かれていたような気がする。看板には、大蛇と絡む半裸の女性や、毒々しい轆轤(ろくろ)首の絵が描かれていた。腰を抜かすほど驚いてしまったのは、鼻から口へ生きたヘビを通す女性が、裸電球が照らす舞台にいたことだ。通称「ヘビ女」。着物姿で腰掛けたまま動かない「タコ娘」も、あやしげなショーを演じていた。
「ホラホラホラホラホラ。お坊ちゃん。お代は見てのお帰りだヨ~」
木戸口のおばちゃんに誘われたが、怖くて中に入れなかった。翌朝、境内を訪ねると、小屋は手品のように消えていた。
「テキヤ」は「香具師」と書いて「やし」とも呼ぶ。単なる露天商ではない。道端での口上や芸をもってカネを稼ぐ職能人である。
諸説あるが、仏教の教えをわかりやすく説きながら香や仏具を売り歩いた武士が「香具師」や「野士(やし)」と呼ばれるようになったのが始まりとされる。薬の行商人が「薬師(やくし)」といわれ、縮まって「やし」になったともされる。
それが「テキヤ」と呼ばれるようになったのは明治以降らしい。「やし」が「ヤー的(てき)」という隠語として使われるうちに逆さになったという。当たれば大きな利益を得ることから、的に矢が当たることになぞらえ「的屋」になったという説もある。「目の前の通行人はすべて敵と思って商売せよ」との意味から生まれた、という説もなかなか説得力がある。
佐賀に住む古参のテキヤは、バナナの競り売りで財を成した。色つきや形を見せながら「サァサァ買(こ)うた、サァ買うた」などと七五調の節をつけ、競るようにして売ったのである。大卒初任給が月1万円強だった昭和30年代、1日2トンのバナナを売り、2万円稼いだこともあった。8時間立ちっぱなしで800~1千房も売ったそうである。
だが雨が降れば雨に泣き、風が吹けば風に泣く。失業保険も退職金もない。明日をも知れぬ人生。そんなテキヤの守り神は、『香具師の生活』(添田知道著)によると、中国の神話上の存在「神農」である。百草をなめて医薬を知り、路傍に市を開いて交易を民衆に教えたとされる。同書が出たのは、東京五輪が開催された64(昭和39)年。都会で暮らす人々にとってテキヤのような生活は「古くさい」とみられていたのではないか。
とはいえ、舌先三寸で人の足を止めさせるテキヤのすごみに、のちに「フーテンの寅さん」で国民的な人気者になる渥美は魅せられた。私が子どものころに見た「ヘビ女」たちもテキヤの世界では階級が高かった。「タカモノ(高物)」と呼ばれる仮設興行の世界に属し、多くの人を集めるので祭りの花形とされていたのだ。
「因果もの」とも呼ばれ、「マムシの執念、報いまして……、出来た子どもがこの子でござい。いらはい、いらはい」という口上もあった。「大イタチ」という見世物は、大きな板に赤いペンキ(血)でイタチの絵を描いてあるだけだった。馬鹿馬鹿しい、というなかれ。昭和というのは、おおらかな時代だったのだ。
寅さん映画にも出てくるが、「ネンマン(万年筆)売り」という商いもあった。路上に並べられた泥だらけの万年筆。勤め先の工場が火事で倒産し、焼け跡から使える万年筆を掘り出してきたという経緯を語り、妻や子を抱えて生活が苦しいという窮状を切々と訴える。客の同情を買い、モノを売るという手段だ。万年筆は粗悪品が多く、すぐに使えなくなった。
角帽に詰め襟の学生服姿でしくしく泣いていたテキヤもいた。「どうしたんだ?」と通行人が心配して声をかけると、「ハハキトク」と書かれた電報をポケットから取り出す。「切符を買うゼニ」をせしめるニセ学生である。
「千里眼」という占いのような商売もあった。紙に質問を書かせる。「私はなぜ女にもてないのか」。その紙をロウソクであぶると「鏡をよく見ろ」と文字が浮かぶ。実は、あらかじめ言葉が刷り込んであった。
「そんな遊びを楽しむ心のゆとり、いまのニッポンに必要なんじゃないですか」
私にそう教えてくれたのは、俳優の故・小沢昭一だった。「だまし」「だまされるのは」のは織り込み済み。悪質きわまりない「オレオレ詐欺」とは違う。
ところで最近、テキヤの花形である見世物小屋を見かけない。昨年11月の「酉(とり)の市」。東京・新宿の花園神社で会った興行主は「人権侵害だ、動物虐待だとたたかれ、できないのです」と言っていた。お化け屋敷なら開くことができるが、人形を置いておくだけ。実際の人間が演じる「ヘビ女」や「タコ娘」はいない。
見世物小屋は、様々な事情で働き先が見つからない人や身寄りがない人、体に障害のある人たちにとっての職場でもあった。「自分の体を使って商売するのに何の問題があるのですか」。興行主の訴えが胸に響く。
あやしげな昭和の風景も、私たちの記憶のかなたに去ってしまうのだろうか。
※週刊朝日 2016年6月10日号
最後の"見世物小屋"を追ったドキュメンタリー『ニッポンの、みせものやさん』予告
香具師(やし)とは何か?

灯籠売り
かつて、東京でもっとも人が集まった市は、日本橋で開かれた「べったら市」でした。これは10月19日に、日本橋通旅籠(はたご)町、人形町、小伝馬町、通油町(とおりあぶらちょう)へかけて立った浅漬大根の市のことです(現存)。本来は翌日の夷講(えびすこう)に必要な土製・木製の恵比寿大黒、打出の小槌、懸鯛(かけだい)、切山椒などを売っていたのですが、いつの間にか浅漬大根の店ばかりになってしまいました。
明治44年(1911)に刊行された『東京年中行事』に、市の様子が次のように記録されています。
《この浅漬売と言うのは、いずれも白シャツ紺の腹掛けに向う鉢巻と言う威勢のいいいでたちで、町の両側にずらりと店を並べ、粕のべったりついたままを売るので、糸織りの小袖を着た立派な商人も、高島田に結った年頃の娘でも、皆このむき出しの浅漬を縄にしばったままで、平生ならとても出来ない真似だが、この日に限って平気の平左で、だらりぶらりとさげて帰る》
あまりに人出が多かったため、特に夜になると人々は自然に浮かれだし、子供や酔っぱらいが、わざと女性の方に寄っては、むき出しの大根をぶらぶらと振り廻すいたずらが頻繁に見られました。当然、相手はキャーキャー言いながら逃げようとするわけで、なんかずいぶん楽しそうな様子です。
この市では朝漬けの売り買いはこんな感じでおこなわれていました。
《試みに『さあいらっしゃい、いらっしゃい、安くてうまいの』と元気よく呼んでいる店先に立って、3本選り出して幾らだと聞くと、45銭だと言う。まあと驚いて逃げ出そうとすると、粕のついた汚ない手で容捨もなく人の袖を引っ捕えて、『旦那、旦那、これから負かすのが旦那の腕だ』と言う。こうしてたいていが1本6、7銭くらいまでは負けてしまう。年により大根の出来に従って値段の相違はあれど、先(ま)ず5、6銭くらいが安い時の相場である》

べったら市(以下すべて1911年)
江戸時代、夏には「盂蘭盆(うらぼん)の草市」が開かれ、江戸各地に露店が並びました。そこでどんなものが売っていたかというと、
《7月12日の昼より夜へかけて、諸商人露店を張り出す。その商う所の物いみじき種類なれども、まず間瀬垣(ませがき)、菰(こも)、莚(むしろ)、竹、苧殻(おがら)、粟穂、赤茄子、白茄子、紅の花、榧(かや)の実、青柿、青栗、味噌萩、蓮の葉、蓮華、鶏頭(けいとう)、瓢箪、菰造りの牛馬、灯籠、盆灯籠、線香、土器(かわらけ)、ヘギ盆など、市場の主なる売物なり。この日数珠造り、仏師、仏壇の漆器類を商う店は殊の外の繁昌なり》( 『絵本江戸風俗往来』)
といった感じです。草市なので草花ばかりなのは当然ですが、想像以上にいろいろなものが売られていたことがわかりますね。

両国の川開き
一方、明治38年の7月5日におこなわれた両国の川開きでは、
《例年の花火は、今年は上流と下流との2箇所で打揚げて、盛況を呈した。その夜の露店で売っていた品々は、5厘のアイスクリーム、氷水、鮨、おもちゃ、扇、ほおずきなど、声を嗄らして客を呼んだが、群集は空の花火にばかり気を取られて、それほどには売れず、ただ玉蜀黍(とうもろこし)の焼き立が、恐ろしく売れていた》(『風俗画報』明治38年9月10日号)
とあって、ずいぶん現代に近くなっています。

藪入りの浅草観音
鶯亭金升という人物が、昭和になって明治時代を振り返った『明治のおもかげ』という本があって、その「縁日の遊び」には、縁日の吹き矢でどうやって儲けるかが書いてあります。
《縁日になくてならぬものの吹矢(ふきや)も今はないが吹矢の流行した時分は、茹玉子(ゆでたまご)、菓子、果物を取らせるように並べていた。5厘の菓子を棚に並べて吹矢で取らせるのに3本の矢の代が1銭である。肩を並べている的(まと)だから3本の矢がみんな菓子に当るので、1銭で1銭5厘の菓子を貰う事になるのだが、その実は菓子の問屋から3つ1銭で買出して来る。故に上手な客が来ても損をせず、下手(へた)が来れば1回に5厘や1銭の利のあるようになっている。
茄(ゆ)でた玉子を並べて置いて3本10銭で吹かせる。これは矢の先をよく削り、当ってもツルリと滑って外(そ)れるように仕組んである。それを呑(の)み込んで研究した男が矢を受取る時にそっと爪(つめ)の先で矢の先を折り、玉子の真ン中をねらって吹くと殻(から)へ命中した。僕もその秘伝を聞いて吹矢の店を困らせた事がある》
つまり、問屋から大量購入で安く買ったものを、高く売るわけ。当たり前ですが、これが商売の基本ですな。

年末の釈尊降誕会
さて、ここまで、いろいろな資料を並べて市や祭の風景を書き出してみました。そこに並ぶ露店や屋台の商売人は、「香具師(やし)」とか「テキ屋」と呼ばれています。
しかし、こうしたテキヤの正体はこれまでほとんど明らかになっていません。どうしてかというと、テキヤは親分と乾児(子分)の「仁義」で結ばれた特殊な関係だからです。
こうした関係性を「やくざ」と一言で言っては語弊があるでしょう。
いったい、露店の裏側とはどんな世界なのか? 探検コムの別館に当たる本サイトでは、テキヤに関する資料を集大成してみました。
知られざる香具師の世界、一挙公開です。
「人体」見世物の世界鬼娘、蛇娘、熊娘らの「奇形」という人生

徒然草の第50段に、「鬼娘」の話が出てきます。
《応長の頃、伊勢の国より、女の鬼になりたるを率(い)て上りたりといふ事ありて、その頃20日ばかり、日ごとに、京・白川の人、鬼見にとて出で惑ふ。
「昨日は西園寺に参りたりし」、「今日は院へ参るべし」、「ただ今はそこそこに」など言ひ合へり。まさしく見たりといふ人もなく、虚言と言ふ人もなし。上下、ただ鬼の事のみ言ひ止まず》
応長というのは短くて、1311、1312年の2年しかありません。京都では、このころ伊勢からやってきたという鬼娘の話題で持ちきりだったのです。
ある日、「一條室町に鬼がいる」という噂が広がって、兼好法師も人をやって見に行かせます。結局、その日は夜まで騒ぎが続き、ついには争いごとまで起きてしまいましたが、誰も鬼娘を見ることはできませんでした。
こんな昔から、人々は「鬼娘」が大好きでした。伝説だってたくさんあります。
たとえば960年頃の戸隠山には「紅葉」という鬼女が住んでいて、平維茂(たいらのこれもち)に退治されました。これが「紅葉狩り」で、その場所は、以後「鬼の無い里」鬼無里(きなさ)という地名になりました。
また、1340年頃、領地に向かおうとしていた大森彦七は、楠木正成の怨霊の化身「鬼女」に出くわし、殺されそうになります。
これほど庶民に愛された「鬼娘」は、江戸時代になると、ついに見世物に登場します。
滝沢馬琴の師匠である戯作者・山東京伝(さんとうきょうでん)の黄表紙(=絵本)『這奇的見勢物語』(こはめづらしみせものがたり)は、当時のさまざまな見世物を描いた作品ですが、そのなかに「鬼娘」が出てきます。
その見世物の口上はこんな感じです。
《東西、東西、おめどほり(お目通り)にひかえましたる娘、きりやう(器量)は十人にすぐれましたれど、悋気(=ケチ)深き報ひによりて、心の鬼となり、さつまいものやうな角が生へ、西瓜(すいか)の種のやうな歯をむき出し、下は梅づけの大根の如く、背中には焼き飯のやうな鱗形の苔が生じ、肌は鳥肌にて、唐もろこしのやうにござります、よなよな(夜な夜な)やけ酒を飲み、うば(乳母)や、子をも喰ひます。大酒にては大丼(おほどんぶり)でお目にかけました。評判、評判》
ちなみに最後の「大酒にては大丼」は「大阪にては道頓堀」のもじりなんですが、こんな感じで見世物にされていたわけです。

これが『這奇的見勢物語』の鬼娘
(『猟奇画報・天変地妖人異』号、1930年より転載)
この「鬼女」が実在したとすれば、恐らくは病気か何かで畸形になってしまった女性なわけで、可哀想としか言いようがありませんが、今と違って人権なんてないので、仕方ありません。
で、本題はここからです。
実は、江戸時代には、ほかにもたくさんの畸形女や奇形男が見世物にされていました。このあたり、「人権問題」のおかげで歴史から抹殺されているため、本サイトが取り上げてみたいと思います。
(なお、当たり前ですが、差別の助長や奇形を揶揄するのが目的ではありません。すべての歴史は等しく語られるべきという立場に立っているだけです)
まず、もっともすごい奇形芸の持ち主はこの男。天保12年(1841)に江戸で興行した若松出目太郎。当時15歳の彼は、文字通り眼が飛び出しており、眼で醤油樽や米俵を持ち上げたと言います。

目力持(大阪出身)
また、江戸末期にもっとも有名だった足芸女はこちら。天保7年、江戸、京都、大阪の3都で喝采をあびた早咲小桜太夫。手がなく、足で三味線を弾いたり生け花をしました。
(なお、ネットで検索すると彼女の名前は小桜ではなく小梅になっています。どちらが正しいのかちょっと手元の資料だけでは確認できないので、両方併記しときます。当時の刷り物に書かれたオリジナルの文字はこちら)。

足芸女
このように奇形を売りにした見世物はたくさんあるんですが、なかでも一番ありがちなのが、現在でも行われている蛇女(蛇娘)。いくら手習いや縫い物を教えても、蛇ばかり使ってまるで覚えないという少女ですな。この蛇女は一番手軽で、また盛り場にはなくてはならない興行でした。
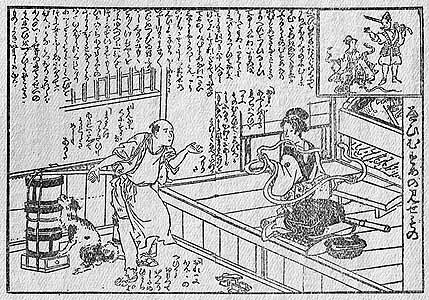
油売りの嫁だった「蛇娘」
一方、これに比べて「熊女」は珍しかったようです。黒人との混血児などを熊女(熊童子)と呼ぶことがありましたが、見世物の場合は一般に多毛症の人間のことを指しました。『見世雑誌』には、天保6年(1835)、名古屋で“展示”された4歳の熊娘について、次のように解説されています。
《越の国(北陸)なにがし村なる猟人の子なれ、殺生の罪の、子に報いて、斯(か)く怪しき身とは生れにけり……顔より手足まで、一面の黒き毛生ひつづけて眼鼻のつきどころさへわからず》
目鼻がどこについているかわからないほど毛深くなった理由は、父親の殺生のせい。このように、たいていの奇形は「親の因果が子に報い」とされました。本来、「因果応報」とは、自分自身の行いが将来の幸不幸を決めるというもので、親は関係ないはずなのに……展示された人は可哀想としか言いようがありません。
ちなみに、場合によってはこうした奇形が仏教の信仰で治癒したという伝説となって広がることもありました。こうして、奇形という「因果応報」は、布教の手だてとしても重要な役割を演じたのでした。

右上の「熊女」は、顔には毛がなかったみたい
最後に、前出の『這奇的見勢物語』にあるトリの見世物を紹介しておきます。それは「人の心の見世物」。

人の心の見世物
《人の心は移りやすく、油断できない。一本足の心は進むことも引くこともできず、一生立ちすくむ。両頭の心は、どちらに行こうか、あれこれと心が定まらない。顔は人で、4本足の(獣のような)心もある。心の独楽(コマ)の心棒が定まらなければ、世の中を自由にはできない……》
という非常に含蓄のある見世物なのでした。
<おまけ>
『這奇的見勢物語』には、奇形以外の見せ物として、軽業、からくり、中国の名鳥、猿の狂言、ウソの霊宝などがあります。あんまりおもしろくないんですが、目を引くのはやっぱり人魚です。

江戸時代にはたくさんの人魚やら天狗の見せ物がありました。国立科学博物館で開催された「化け物の文化誌」展では、人魚と天狗のミイラが展示されていました。
実物は長さ30cmくらいでこじんまりしてるんですが、科学的な調査によると、天狗の頭はネコの頭蓋骨で、人魚の下半身はシュロらしき木を利用して作ったようです。江戸時代の人って創意工夫にあふれてますな!
日本最後の見世物小屋

2005年現在、日本には常に興行している見世物小屋は1つしかないそうです。それが大寅興行社で、東京では新宿・花園神社の酉の市で見ることができます。
そこで2005年11月8日、久しぶりに見に行ってみました。すると、毎年のように「今年で最後」と言われていた小屋に、なんと新人の若い女の子が参加してるではありませんか。赤い和服を着て、長い黒髪の小雪ちゃんは、ヘビの頭をかみ切り、生き血を吸い、そのままむしゃむしゃ食べるという……強烈なキャラでした。入団のきっかけは「私もヘビ食いたい」だって。
いやー、これでしばらく見世物小屋も安泰ですな。
さて、実は今回、内部の写真撮影が禁止されていたため、残念ながら外観しか画像は公開できません。そこで、本サイトでは1999年7月15日の靖国神社での興行写真を公開しておきます(当時は写真はOKでした)。
ちなみに大寅興行社の田村由三郎氏は、『自然と文化 見世物』のインタビューで次のように答えています。
「大寅の小屋掛けは宮城のように立派でした。屋根を張り出し、軒下に提灯をぶら下げ、欄干をつける。魔宮殿と言っていました。(中略)移動動物園の後が今の見世物になったのですが、現在も引き継いでいる大蛇とか犬の芸、マジックショーは、大野寅次郎さんの時代の産物です」
このように、ここは犬をジャンプさせたり蛇を鼻から口に出したり、トランクを使ったマジックが売り。一押しは火吹き女です。現在の入場料は800円ですが、1999年は600円でした。
すでに靖国神社では興行していないようですが、どこぞで見つけたら、とりあえず1度くらい入ってみよう!

小屋にかかった看板

入口では小男が客を誘う

ヘビを体に巻き付けた蛇女(おみねさん)

溶けたロウソクを口に流し込み……
↓

一気に火を吹く! スゲー!!
なお、小屋にかかっていた「見世物今昔物語り」を全文公開しておきます(以下すべて原文のまま)。
そもそも見世物の始まりは勧進を名目に放下(ほうか)や蜘舞(くもまい)を興行した、室町時代にはじまると言ってよかろうが江戸時代に入ってから盛行をきわめたという。
まず京都の四条河原がその発祥地としてすでに慶長期(1596-1615年)ころに蜘舞、大女、クジャク、クマ、などの見世物が歌舞伎(かぶき)や人形浄瑠璃(じょうるり)などにまじって小屋掛けで興行していた。かご抜け、まくら返しからくりなどが寛文期(1661-1673年)前後に流行しそのころ<べらぼう>という言葉の語源になった。
<べらぼう>という奇(き)人の見世物がかかった生人形、小男、ヘビ使い芸などもあった。
享保期(1716-1736年)以後には曲馬、人馬、八人芸、女角力(おんなすもう)綱渡りなど明和安永期(1764-1781年)には火喰坊主、蘇鉄(そてつ)男、馬男、熊女、曲屁(へ)福平、鬼娘、ろくろ首など寛政(1789-1801年)以後には唐人蛇(へび)踊り、山男、金玉娘、蛇娘また福招きの人形として知られている。
<叶(かのう)福助>の流行に乗って1804年(文化1)春は<福助>の見世物が最も人気があったそうな。お祭りの風物史として皆様に親しまれ愛されてきた見世物小屋も明治、大正昭和と平成に至り昔は300軒もあった見世物小屋も現在は、2軒になってしまいました。大人の思い出、子供の夢、皆々様でお楽しみ下さい。
館主

 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













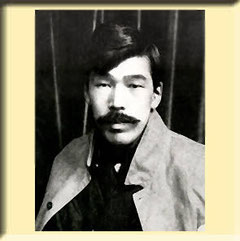














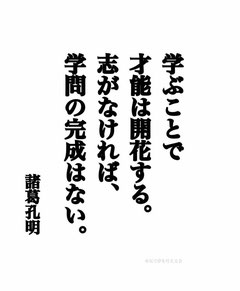

コメントをお書きください