※このプロフィールは、著者が日経ビジネス電子版に記事を最後に執筆した時点のものです。

答えなき悩みの一つとして、「老いや死」との向き合い方があります。どんなに成功して権力を得ても、悩んでしまうその事象。ある不老不死の昔話を軸に、人間の「生への渇望」に対する向き合い方を考え直してみませんか。

老いを感じると死にたくないと感じる
尿の切れが悪くなった、本や新聞の文字が読みにくくなった、白髪やシワが増えた。
誰もが老いを感じる瞬間です。
私たちは若い頃から、自分にも老いが来ることを知っていました。けれども、老いについて知っていることと、実際に老いることを受け入れられるかどうかは別ものです。
ついに、その時がやってきたと感じる。「老い」に気付き、ショックを受けた瞬間から、心は次のような感情にとらわれます。
「老いは嫌だ」「病気は嫌だ」「俺が死んだらこの会社はどうなるんだ」「とにもかくにも、死ぬのは嫌だ」と。
そして、「いつまでも長生きしたい」という、かなわぬ夢を見始める。
社会的な地位が高い人であったとしても、成功者としてあがめ立てられている人であったとしても、その幻想に取りつかれてしまう人は少なくありません。かくして、古今東西、人々は不老不死を目指して、さまざまな「あがき」を繰り返してきました。
とくに、秦の始皇帝の「生への執着」は有名です。
『史記』によれば、紀元前219年、始皇帝は、徐福という道教の術士に命じて不老不死の薬を求める旅に出させます。徐福は、童男童女3000人を従えて山東省から出航しますが、再び戻ることはありませんでした。
諦めきれぬ始皇帝は、臣下を国内外に派遣して、不老不死の仙薬を研究させていましたが、ついに丹薬(たんやく)と呼ばれる秘薬を作り上げました。
しかし、丹薬の主原料となった辰砂(しんしゃ)には、猛毒である水銀が硫黄と結びついた「硫化水銀」が含まれていたのです。
誰よりも「不老不死」を望み、誰よりも「不老不死」に金をつぎ込んだ始皇帝は、皮肉にも「不老不死」の秘薬と信じて飲み続けた、猛毒によって49歳という若さで死去します。長生きを望まずに丹薬を飲まない方が、もしかしたら長生きできたかもしれませんね。
秦の始皇帝ほどの絶対的権力と富を手に入れた王でさえ、最後に執着するものは「生」なのです。
始皇帝の死から2200年。ヒトゲノムが解読され、肝細胞技術による再生医療が進展する現代においてなお、いまだ不老不死の秘薬やその道筋すら開発されていません。もちろん、今後さらなる研究が進むことで、いつかその方法が出現して、「不老不死」が実現するかもしれません。
しかし、「死から逃れること」や「老いなくなること」は、本当に幸福なことなのでしょうか。
ある昔話から生を考える
その問いに対する一つの答えとして、私の地元・愛知県の春日井地方に伝わる『八百比丘尼(やおびくに)』という昔話をご紹介しましょう。
昔々、まだこの地域のすぐそばまでが海であった頃のこと。嵐が去った翌日、浜辺に人魚が打ち上げられます。
上半身は人間の姿。でも、下半身は魚の姿とえたいの知れない存在です。漁師たちは扱いに困って、とりあえず神社に人魚を運び込みます。
「見たことがない、不思議な魚」が浜辺に打ち上げられたとの噂は、瞬く間に村中に広まりました。
村人たちは、一目その人魚なる魚を見ようと、こぞって神社に集まってきました。
そのやじ馬の中に、おばあさんに連れられてやって来た、一人の女の子がいました。
女の子は、大人たちが人魚について「気持ち悪い」だの、「不思議」だの話し込んでいる隙に、何と人魚の肉を一口摘んで、食べてしまったのです。
しばらくの間、村では人魚の話で持ちきりでしたが、騒動は時間とともに鎮まり、人魚のことも忘れ去られていきます。
時が過ぎ、人魚の肉を食べた女の子は、それはそれは美しい女性へと成長します。そして彼女が18歳になったとき、村の内外から、求婚話が次々と舞い込んだのでした。
彼女は結婚し、子どもを授かります。彼女を射止めた夫は、誰からも羨ましがられました。夫もまた、自慢の妻を大切にし、夫婦仲は円満。彼女は幸せでした。
ところが、50歳、60歳、70歳と年を重ねるごとに、羨ましがられていた彼女の美貌が周囲からは気持ち悪がられるようになっていきます。
なぜなら、家族は皆、老いて容姿が変わってゆくにもかかわらず、彼女の顔や体は18歳のままだったからです。
さらに時が過ぎると、夫は死に、子どもたちも死に、親戚も友達も、近所の人たちも死んでしまいます。それでも、彼女は年老いませんでした。
彼女は、人魚の肉を食べたことで、不老不死の肉体を手に入れてしまったのです。
村人たちの世代が入れ替わっても、彼女だけは永遠の18歳。若い世代の村人たちは、彼女について噂をし始めます。
「おみゃあさん、知っとりゃーすか。あそこの奥さんな、18歳言っとりゃーすけど、本当は100歳だがね」
そんな噂があちこちで耳に入れば、当然、村には居づらくなります。彼女は村を出て、遠く離れた場所に移り住んだのでした。
ところが、移り住んだ先でも同じことが起こります。
よそからやってきた18歳の若き美女を、男たちが放っておくはずがありません。移り住んだ先でも、求婚者が絶えず、彼女としても、新天地での寂しさゆえに、結婚して子どもができる。
ひとときの幸せはあれど、また夫が死に、子どもも死に、友人が死に、ご近所が死に、そしてまた別の場所に移る。
そんな悲劇を幾度繰り返したことでしょう。
彼女は800歳になったとき、自ら頭を丸めて尼僧になります。そして、山奥の洞窟に入ったきり、二度と姿を現すことはありませんでした。
この不老不死を手に入れた比丘尼の話は、福井県の小浜、福島県会津、新潟県佐渡などの海辺の地域はもちろん、春日井や栃木市西方町真名子のような内陸部にも、全国各地に分布しています。
誰もが憧れる「永遠の18歳」。
自分から望んでそうなったわけではないとは言え、彼女はまさに憧れの肉体を手にして、永遠の幸福を手にしたはずでした。
ところが、800歳になった彼女が取った行動は、世俗の幸せを捨てて、比丘尼(尼僧)になることでした。
あなたはそれでも不老不死を求めるのか
老い、病気、そして死は真理です。人は必ず老います。老いて病を患います。そして必ず死ぬのです。
そのように聞くと、死がものすごく恐ろしいことのように感じます。また、死ぬことが、不幸の極みのように感じられます。
しかし、800歳まで生きた彼女は悟ったのでしょう。老死が決して恐ろしいことではなく、また不幸ではないことを。そして、永遠に老いず、永遠に死なないことが、決して幸せでないということを。
比丘尼が最後に取った決断は、二度と洞窟から出ないこと。つまり、終わりなき生に自ら終止符を打つことでした。
もちろんこの昔話が実話という確証はありません。
けれども、仮に私たちが不老不死を手にしたならば、どうでしょうか。多かれ少なかれ、この比丘尼のような生涯を感じ、老いや死からむやみに解放させることは良いことではないと気付かされることは、想像に難くありません。
経営者として成功し、会社は順風満帆。しかし、老いていく自分に不安を感じてしまう。そういった気持ちを、老いたタイミングでしばし持つことは否定しません。ですが、若い人へ嫉妬してしまったり、受け入れられずに沈んだ気持ちで居続けたりすることは正常な思考を阻害します。老いを受け入れる気持ちに、いつかはシフトしていくことが大切です。
それでも不安や納得ができないと思ってしまったら、比丘尼の昔話を思い出し、本当に老いないことや死なないことが幸せかどうかを考えてみてください。
この昔話は「飽くなき生」を渇望する私たちに、「不老不死は、本当に幸せなのか」を、時代を超えて問い続けてくれているのです。

著者
仏教から学ぶ 部下を褒めるべきか叱るべきか
仕事によって社会活動を行う中で、マネジャー以上になると悩む「褒める」と「叱る」の問題。今回は仏教を軸に「正しい部下との接し方」を解説いたします。
経営者として社員や部下を叱るシーンは当然存在するでしょう。
私がYouTubeで配信しているお悩み相談の番組、『大愚和尚の一問一答』には、現在2500件を超える相談が届いています。その中には経営者からの相談も少なくありません。特によくあるのが、「社員や部下を褒めたほうがいいのか、叱ったほうがいいのか」という質問です。
この質問に対する私の結論は、「どっちでもいい」となります。
なぜ「どっちでもいい」のか?
それは「褒める」「叱る」よりも「誰に叱られるか、誰に褒められるか」という点が大切だからです。
社員の立場になって考えてみれば分かります。尊敬できない経営者に叱られても、反発しか感じませんが、尊敬する経営者に叱られれば、社員はその原因や失敗をしないよう肝に銘じます。
褒められるときも一緒、尊敬する経営者に褒められれば、社員は褒められたことを魂に銘じます。社員は、尊敬する経営者には認められたいと思っていますから、社員を認めた上での「褒め」や「叱り」は、どちらであっても社員に響くのです。
問題は「褒めるか、叱るか」ではなく、前提として「どうしたら尊敬される経営者になれるのか」ということを考える必要があります。
経営者自身には「自分が本当に尊敬されているか否か」は分かりませんし、いまどきの社員は、「肩書」だけで経営者を尊敬するわけではありません。
では、どうしたら「社員から尊敬される経営者」になれるのでしょうか。
教育の達人
今から2600年前のインドで、自ら悟りを開き、また多くの弟子たちを悟りに導いた人物がいます。
それは、お釈迦(しゃか)さまです。お釈迦さまには、その備わった多くの徳を形容するための別名がついています。10個の別名で、「如来の十号(にょらいのじゅうごう)」と呼ばれています。
これら10個の人徳が、お釈迦さまを尊敬される人たらしめているわけですが、注目していただきたいのは8番目の「調御丈夫」という呼称。
この調御丈夫とは、「人を指導することに巧みな人」という意味です。
そう、お釈迦さまは、教育の達人でもあったのです。
お釈迦さまの「叱り方」
では、お釈迦さまは、どのように弟子たちを導き、叱ったのでしょうか。
経典の一つである「増一阿含経(ぞういつあごんきょう)」に、お釈迦さまが弟子のアヌルッダを叱ったときのエピソードが記されています。
あるとき、お釈迦さまが祇園精舎で大勢の人を前に説法をしておられると、弟子のアヌルッダがウトウトと居眠りを始めました。
それを見たお釈迦さまは、「みなさんここに来るまでの道中で疲れている人もいるでしょう。けれども、仏の説法を聞くということは並大抵のことではないし、祇園精舎に参詣することも、非常に難しい。たとえ法話中、居眠りをしていても大変な仏縁になる」とおっしゃいました。
ところが説法の後、お釈迦さまはアヌルッダを呼び出して「あなたは何が目的で、仏道修行をしているのか」と尋ねます。アヌルッダは「四苦八苦を思い知り、苦しみを解決するためです」と答えます。お釈迦さまはさらに問います。「あなたは良家の出身でありながら、道を求めようとするしっかりとした意思がある。それなのにどうして居眠りなどしたのか」と。
アヌルッダはお釈迦さまの前に平身低頭し「申し訳ありませんでした。今後、二度と居眠りはいたしません」と深く懺悔(ざんげ)したのでした。
その日を境にアヌルッダは、猛烈な修行に打ち込み、眠ることをしませんでした。そしてそれがたたって、ついに視力を失ってしまうのです。
そのことを知ったお釈迦さまは、「琴の糸のように張るべきときは張り、緩むべきときは緩めなければならない。精進も行き過ぎれば後悔となり、怠ければ煩悩が起きる。中道を歩むがよい」と諭されたのでした。
お釈迦さまの勧めによって医師にかかり、休眠を指導されたアヌルッダですが、自らの誓いを破ることなく完全に失明してしまいます。
しかし、同時に心眼を開いて悟りに至ったのでした。
お釈迦さまは、解脱を妨げる心の作用として、五蓋(ごがい)を挙げておられます。
お釈迦さまは、五蓋の1つ、眠気を叱られたのです。
本来の目的に気づかせる
たった一度のお師匠さまの叱咤(しった)を肝に銘じ、徹底して教えを守り通すことで本来の目的(悟り)を得たアヌルッダもすごい人です。それだけでなく、このエピソードには、お釈迦さまの巧みな叱り方のポイントが3つ秘められています。
1.弟子の失態を大衆面前では叱らず、個別に呼び出して諭したこと
2.感情的に叱らずに、冷静に修行の目的を問い、本人の口から語らせたこと(再認識させたこと)
3.もともと素直で真面目なアヌルッダの性格に配慮し、叱った後も優しくフォローしていること
お釈迦さまは「話を聞いていなかった」とか、「私に恥をかかせた」とか、アヌルッダを「責める」ために叱ったのではありません。「なぜ修行しているのか」という、アヌルッダ自身の本来の目的に「気づかせる」ために叱ったのでした。
この話には、後日談があります。視力を失ったアヌルッダが、ほつれた衣を縫うため針に糸を通そうとして苦心しているのを見て、お釈迦さまが直々にアヌルッダの針に糸を通されたというのです。
どこまでも弟子たちの成長を願うお釈迦さまの、慈悲深く、熱く、冷静な姿勢が垣間見られる話です。
さいごに
叱る側は、叱ることで単なる服従を求めるのではなく、叱られる側がどういう立場で聞いているかを観察していくことが重要です。
この作法を身につけたならば、古今東西、どんな職場においても重宝されるでしょう。
そのような姿勢で接する社員を、まっとうな経営者や上司が、大切にしないはずはないのですから。
曖昧な「やさしさ」では、経営者は決して成功しない
成功する経営者と失敗する経営者。両者の間にはある違いが存在します。それは、明確な「やさしさ」を持つか否か。定義の難しいやさしさについて解説していきます。
成功する経営者の共通点
成功する経営者。多くの人はある共通点を持っています。それは、「明確さ」です。
逆に、低迷する経営者には「曖昧さ」という共通点を持っています。
明確さは、事業を成功に導き、曖昧さは低迷や失敗につながります。なぜなら、人間は言葉で自分の考えを他人に伝え、生きているからです。会社の目的、目標、望ましい言動などを、明確な言葉で伝えられる経営者は、事業を成功に導きやすくなります。
「明確な言葉」はプラスの力となって経営を支え、「曖昧な言葉」はマイナスの力となって経営を挫(くじ)きます。
仕事も、遊びも、家庭も、いいかげんで曖昧な言葉を使えば、うまくいきません。そのことを知る経営者は、言葉の意味や言葉遣いにも気を配ります。
さて、もう一つ補足すると成功する経営者は、明確さを持つだけでなく他に共通点を持っています。それは、「やさしさ」という点です。
好かれる経営者や上司の条件には、必ず「やさしい」が、ランクインしています。ところが「やさしい」のに失敗してしまう経営者もいます。やさしすぎるから失敗したのだ、厳しさも必要だと嘯(うそぶ)く経営者さえいます。
しかしそれは違います。
普段から明確さを求め、言葉の真意を深く問う経営者は、知らず知らずのうちにやさしさの定義を問い続けています。付け焼き刃のやさしさで行動を決めたりしません。
だから、「やさしさ」の本質に近づいていくのです。
カリカリしがちな経営者
一方、失敗する経営者はやはり、やさしさの定義に明確さがなく曖昧です。
やさしさの定義が曖昧であるがゆえに、自分ではやさしくありたいと思っているのに、ついカリカリしてしまうのです。
表面的な、偽物のやさしさを身に付けて、自らをやさしいと嘯いてしまうのです。
もともと持つ性格ではなく、曖昧さが問題です。
よくよく考えてみると、誰もが求めているやさしさについて、明確に定義できる人は少ないと思います。
もし、やさしさの定義を問われたならば、どこか言葉を濁したくなってしまうのではないでしょうか。定義が曖昧すぎる人ほど、実践できないのです。
やさしさの9割はエゴ
では本当のやさしさとは何か。
そして、どうすれば本当のやさしさが身に付くのか。
その問いに、明確な答えと具体的な練習ステップを示した人がいます。
それはお釈迦様です。
具体的な練習ステップに入る前に、陥りがちなやさしさの誤解を紹介します。
私たちは皆、やさしい人が好きです。
やさしく振る舞うことが、いいことだと信じています。
では、私たちはどのようなときに、この人はやさしいと思い、どのようなとき、この人はやさしくないと感じるのでしょうか。
その判断は、相手が自分にとって好ましい言動をしたかどうかによってなされます。
相手が自分の期待通り、あるいは期待以上の態度を取ればやさしい人となり、期待を下回る場合、あるいは期待に応えてくれない場合は、やさしくない人だと判断します。
やさしい人かやさしくない人かは、客観性に基づくものではなく、完全に「私」というエゴを喜ばせたか否かによって、決められるのです。
相手が私の望む時に望み通りに欲求を満たしてくれる場合は「やさしい人」となり、相手が「私」の欲求を満たしてくれない場合は、「やさしくない人」と評価する。それどころか、恨みや罵りさえしてしまうのです。
さらにエゴは、相手から「やさしさ」を受けるときだけではなく、自分が相手に「やさしさ」を与えるときにも、その身勝手さを発揮します。
だから「自分はやさしくされたい」けれど、「人にやさしくするのは疲れるし、面倒くさい」。
それがやけに積極的にやさしさを発しているときには、「自分が相手にやさしくしてほしいから」だったり、「自分が相手を自分のものにしたいから」だったりと、必ず裏があります。
結局、私たちが考えるやさしさは、エゴなのです。自分都合で相手にレッテルを貼り、自分勝手に「好き嫌い」や「善しあし」の感情を抱いている。
そういうことなのです。
お釈迦様が説かれた本当の「やさしさ」とは?
お金を手にすると「独りでも生きていける」と勘違いする人があります。
ですがそれは、思い上がりです。この世に、単独で生きられる生命はありません。
水も、酸素も、食事も、私たちは外から入ってくるもののおかげで生きています。
歯ブラシも、歯磨き粉も、せっけんも、髭剃(ひげそ)りシェーバーも、パンツも、シャツも、スーツも、車も、電車も、スマホも、パソコンも、タバコも、枕も、ベッドも、布団も。
24時間365日、起きていても寝ていても、大自然からその原材料をもらって、誰かの手を経て生成され、誰かの手を経て成形され、誰かの手を経て運搬されたものを、誰かにもらったお金で買って、使用しながら生きています。
さらにそれは物質的なものに限らず、陽の光や、木々の緑や、風のゆらぎ、犬猫のかわいらしい仕草(しぐさ)、誰かの言葉や振る舞いなど、人間関係を超えて、他の生命との関わりを通して受ける、あらゆる刺激や情報などに触れながら生きています。
それらとの関わりが一瞬でも途絶えれば、生命は生きていくことができません。
私たち生命は、絶え間なく外から入ってくるものたちとの関係の上に成り立っているのです。
お釈迦様は、私たち生命がこのジャーラの上に成り立っていることを悟られました。「私」という生命は、ジャーラの中の点であり、中継点であり、絶え間なく受け取り、発信しながら相互に扶助し合うことによって成り立っているのです。
ですから、もし「私」が、「他の生命など自分とは関係ない」と、エゴを振りかざしてワガママに生きれば、どこかで行き詰まり、排除されてしまいます。
しかし、ジャーラを理解し、エゴを離れて、「本当のやさしさ」を育んで他を尊べば、今よりずっと、無理なく、自然に、互いを傷つけることなく、楽しんで生きることができるようになります。
お釈迦様はこのジャーラの中で、いかに他と調和して生きるか、という具体的な生き方を教えられたのです。
経営者が「本当のやさしさ」を身に付ける4つのステップ
ではどうすれば、エゴを離れて「本当のやさしさ」を身に付けることができるのでしょうか。
お釈迦様は、エゴを離れるためには、まず「エゴを認めよ」と説かれました。
矛盾しているように思えますが、エゴを離れるためには認めることが大事なのです。私たちは単独では生きられません。完璧には生きられません。誰かに助けてもらったり、慰めてもらったりしたいのです。それが生命の本能であり、成り立ちですから、必要に応じて誰かに期待することが悪いわけではないのです。
自分独りで生きていると思い上がったり、カッコつけたりせず、自分の期待や希望を素直に認めるのです。すると、他の生命も同じように、助けや慰めを期待していると分かるのです。
すると、「私」というエゴを客観的に見て、エゴの暴走を抑えることができるようになるのです。
次にお釈迦様は、4つの心を育てるよう、説かれました。
4つの心とは、(1)慈(じ)、(2)悲(ひ)、(3)喜(き)、(4)捨(しゃ)です。
(1)慈:あらゆる生命を「友」として慈しむ心
「生命は単独では生きられず、相互扶助の関係を生きている」と正しく観察したならば、他の生命に対して取るべきは、友を慈しみ、友と楽しもうとする態度だと分かるはずです。経営者と社員の関係は、支配者と奴隷ではありません。立場の違いはあっても、人としては平等です。目的に向かってチームを組み、与え、与えてもらう、ギブ&テークの関係です。「おはよう」「元気?」「先日の仕事はどうだった?」「一緒に食事しましょう」「楽しかったね」「ありがとう」。そんな気持ちの良い関係を、社員さんとも、パートさんとも、外注先とも、顧客とも、あらゆる人、生命との間に育てたい。それが慈の心です。
(2)悲:苦しんでいる人を「助けたい」と思う心
悲の⼼は、抜苦(ばっく)の⼼とも呼ばれます。私たちは、人に対して友情だけを求めているわけではありません。悲しいとき、つらいとき、苦しいときには、助けてほしい。また、慰めてほしいと理解を期待します。
⽣命は平等ですが、それ以外の物事は均等ではありません。⼀⽣遊んで暮らせる資産がある⼈もいれば、今⽇⾷べるものがなく、飢え死にしてしまう⼈もいます。⽣まれ育った国、環境、親、境遇、など努⼒だけでは埋まらない差も存在します。そうした世界において、⾃分さえよければ他は関係ないという⽣き⽅は、エゴです。「やさしくない」のです。
(3)喜:他人の幸福を、共に喜ぶ心
悲の⼼と同様に、ここでも⽣命は平等、しかしその他の事象が均等ではないことに⾔及する必要があります。生命の中には、環境や、運や、能力に恵まれて大成功するものがあります。頑張って成果を上げた、試験に合格した、結婚した、子どもが生まれた、と喜んでいる生命もたくさんあります。
それを見て、「何で自分じゃないんだ」と落ち込んだり、「ちくしょー!」と嫉妬したり、挑戦しようとしたり、足を引っ張ろうとするのは、エゴです。他人の幸せを妬み、他人の不幸を喜ぶ人は多く、他人の成功や幸せを手放しで喜べる人は少ない。喜んでいる生命に、楽しんでいる生命に、素直に拍手やエールを送ることができる人が「やさしい人」なのです。
(4)捨:生きとし生けるすべての生命の、幸福を願う心
捨は、インドの言葉で「ウペッカー」と言います。ウペッカーには「平等」という意味があります。先に見てきた慈悲喜の心は、友情、苦しみ、喜びと、対象を限定して「やさしさ」を育てる方法でした。
捨では、視点を上げて、より深く、広く「やさしさ」を育てます。生命をより高い視点から俯瞰(ふかん)して観察すると、そこには、友も、まだ友でないものも、苦しんでいるものも、喜んでいるものも、幸福でも不幸でもないものもいます。それらすべてを平等に見て、それぞれがそれぞれに「幸せであれ」と願う心。それが捨の心です。
今日から本当のやさしさを備えてみませんか
お釈迦様が説いた、「本当のやさしさ」の定義と育て方。いかがでしたでしょうか。「エゴを捨てよ」とか、「慈悲喜捨」とか、一見難しいお説教のように捉えられがちな内容だったかもしれません。
しかし私は、これほど詳細かつ繊細に、「やさしさ」を考察して示された教えを他に見たことがありません。
慈悲喜捨の4つの心。その心を一言で表すならば「生命の悩み苦しみに寄り添い、喜びを与えていく」心に他なりません。
いかがでしょうか。
古今東西、成功者と呼ばれる人は、まさにそのような心を持って事業を起こし、発展させてきたのではないでしょうか。
成功する経営者には、運や能力、知識や情報などが備わっています。けれども、彼らはそのもっと根底に、「やさしさ」を備えているのです。







 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













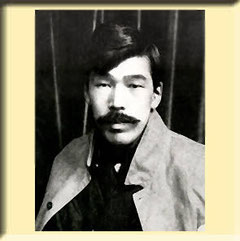














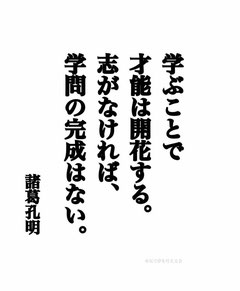

コメントをお書きください