
ビッグモーターの不祥事が世間を騒がせています。兼重宏行前社長が「ゴルフを愛する人に対する冒涜」云々と発言したというので、クルマ屋だけにてっきりフォルクスワーゲン・ゴルフがどうかしたのかと思いきや、ゴルフボールで顧客の車を故意に傷つけていたというのですから、想像の斜め上を行く話でした。
保険金の不正請求に加え、除草剤を用いた店舗前街路樹の破壊の疑惑も濃厚になってきています。ワンマン社長の支配の下、社員は無理なノルマを強要され、違法な命令も受けていたと見られますから、ビッグモーターは典型的なブラック企業であると言えるでしょう。
いまさら驚く話なのか
しかしまあ、こうした話に私たちはいまさら驚くでしょうか? SDGsだのダイバーシティだの、この世の中を倫理的に向上させようという掛け声が四六時中鳴り響いている一方で、企業の不祥事は後を絶ちません。

「チャレンジ」と称した粉飾決算によりボロボロになった東芝は、部門の切り売りを繰り返すなかで再建の目途は立っておらず、かつ粉飾決算を引き起こした旧経営陣のうち、逮捕された者は誰もいません。あるいは、創業者の性加害問題に揺れるジャニーズ事務所にしても、組織ぐるみでジャニー喜多川氏の乱行を許容・助長してきたことは明らかであるにもかかわらず、所属タレントは何事もなかったかのごとくに仕事を続けています。そして、津波対策を怠って大量の放射能をブチ撒いたにもかかわらず、旧経営陣の誰もいまのところ有罪宣告されてない東京電力こそ、企業不祥事番付の横綱です。ビジネス倫理だのコンプライアンスだのといった言葉は、ただひたすら空しいとしか言いようがありません。
だから、ビッグモーターの件も、せいぜい五十歩百歩にしか見えないのです。不正行為を社会的にもみ消すことができるほど大きな権力を持つ企業と、それほどの力を持たない企業があるだけだ、と考えるべきではないでしょうか。してみれば、企業の不祥事とは例外的な嘆かわしい現象なのではなく、資本主義的に運営される企業とは、本質的に倫理的ではあり得ない存在なのであって、繰り返される不祥事は必然的な現象なのではないでしょうか。
セオドア・ルーズベルトも朝食を吐き出す
現に、『ザ・コーポレーション』を書いたカナダの法学者、ジョエル・ベイカンは、企業を人間に例えるならばサイコパスである、と言い切っています。いわく、「精神を病む生き物である企業は、他者を傷つけないように道徳に従って行動することも、そうした道徳を理解することもできない」(『ザ・コーポレーション』早川書房、81頁)。ゆえに、企業には内在的な遵法意識はないのであって、法を守ることは費用対効果の問題になります。法を破ることによって得られる利益が、それがもたらす損害を上回るならば、企業自身に法を尊重する動機はないのです。
なぜこうなってしまうのか。それをカール・マルクスは、疾うの昔に見抜いていました。難解をもって知られる『資本論』ですが、実は生産の現場に関するかなり具体的な記述を豊富に含んでいます。「労働日」の章は、当時のイギリスの労働者がいかに過酷な搾取を受けているかを詳しく描き出していますが、それに加えて企業がいかに不正な製造を行っているのかを描き出しています。当時のパン製造業者は、原料を節約するためにパンのなかに混ぜ物を入れていた。その中身はなんと、明礬(みょうばん)や砂、さらには「腫物の膿や蜘蛛の巣や油虫の死骸や腐ったドイツ酵母」(『資本論』岩波文庫、第二分冊、124頁)だったというのです。
このスキャンダルは当時のイギリス議会でも取り上げられ大いに問題視されたようですが、20世紀に入っても、アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトが、ハム工場の状況を告発したルポルタージュを読みながら朝食を摂っていたところ、口にしていたハムを思わず吐き出して、食肉加工工場の衛生状態に対する規制の強化を即決した、というエピソードがあるくらいですから、資本主義的に運営される食品工場が、法による監視と規制を逃れればどんなものになりがちなのか、明らかではないでしょうか。
そうなる理由は、マルクスの「資本」の概念から容易に理解できます。資本とは際限のない価値増殖運動にほかなりません。価値増殖すること以外に、資本には何の目的も関心もありません。ゆえに資本は、人間の幸福やあるべき道徳に対して完全に無関心です。私は、資本のこの性格を「資本の他者性」と名づけました(『マルクス 生を呑み込む資本主義』講談社現代新書、2023年)。だから、「ブラック企業」という言葉はおそらく不適切なのです。企業は利潤の最大化、すなわち価値増殖を至上の目的としている限り、そもそも「ブラック」に決まっているのです。
それでも、こうした企業の反社会的性格を抑制するために、経営者たちはさまざまに企業倫理を考え出してきました。それは、利潤の追求だけでなく、社会貢献や労働者の雇用を守るといった目標を追求しなければならないという考え方でした。しかし、この30年余り、新自由主義化が進むなかで、「株主主権」とか「ストックホルダー資本主義」といった概念が強調され、受け入れられるようになりました。
株主=資本家ですから、要するにこれは、企業のサイコパス的・反社会的性格を全面開花させよ、というそれ自体きわめて反社会的な主張です。この主張によれば、企業はブラックであればあるほど、ただひたすらに価値増殖を追求しているので、「正しい」ということになります。
ブラック企業「潜入取材」のすすめ
いよいよ凄まじい世の中になりました。だからあえて言いたい。若者は、ブラック企業で働くべきだと。無論、これはブラック企業でも頑張って働いて根性を鍛えるべきだとか、何とか内部で改革を試みて企業体質を変えるべきだ、などと言いたいのではありません。そんなことを志すと身体か心、あるいはその両方が壊れます。

あくまで、いつでも辞められる身分で、文化人類学者のように観察するつもりでブラック企業に身を置いてみれば、資本主義の何たるかを最も明瞭に理解できるはずです。いくら理不尽な目に遭おうが、「いつでも辞められる」ならば、何も怖くはありません。ハラスメントや法令違反の命令については、しっかり証拠を残すために、仕事中は常時録音機を作動させておくとよいでしょう。
そして、もう一つの重要なメリットとして挙げられるのは、最初から「ブラック企業でいいや」と思っていれば、大学生が就職活動というつまらないゲームをしなくて済むことです。ブラック企業は大量退職を見越して大量採用しますから、就職するのは容易なはずです。私が早稲田大学に在籍していた当時、就活したくない学生がいまは亡き某大手消費者金融に電話を掛けて「採ってくれませんか」と言ったら、「なに? 早稲田? とりあえず採っておけ!」と話すのが受話器の向こうで聞こえた、という伝説がありました。
他方、いわゆるエリート予備軍を気取る「意識高い」若者は、「いい会社」に就職しようと願い、そうした会社のビジネスは「真っ当な」ものだと信じます。何という愚かしさでしょうか。資本主義社会には、不祥事をもみ消せないビッグモーターともみ消せるビッグモーターがあるだけなのに。そして、後者のビッグモーターは我が手を汚さないで済ませるために、「ブラック」な部分を前者にアウトソーシングすることができるだけなのに。
もちろん「あえてブラック企業で働く」を実行するには、「いつでも辞める」ことができる余裕がなければならないでしょう。ですが、余裕のある者が先頭に立って正確な社会認識を持つこと、これが世の中を変えるためのはじめの一歩を刻むことになるのです。


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













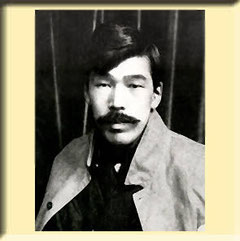














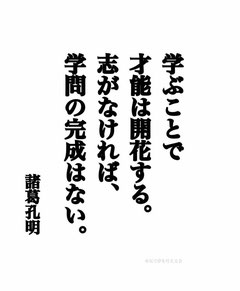

コメントをお書きください