
新聞の存在感が、すごい勢いで世の中から失われている。
5,400万部を記録した1997年の総発行部数は2022年に3,000万部にまで落ち込み、44%もの減少になったほどだ。
当然、主要各社の売上も大幅に落ち込んでおり、今なお底が見えない。
その理由について、メディアはどこも判で押したようにこんな分析をしている。
「インターネットやスマホの普及で、新聞が読まれなくなったからだ」と。
紙媒体としての新聞については、確かにその通りだろう。
しかし断言できるが、新聞各社の売上が減少し続けているのは決して、インターネットやスマホが普及したからではない。
単に経営陣が世間の感覚からずれていて、今もなお間違っているからである。
なぜそんなことを、断言できるのか。
“常に新しい老舗企業”
話は変わるが、グンゼという社名を聞いてどのようなイメージが思い浮かぶだろう。
40代以上の世代であれば、オジサンや子ども向けブリーフのイメージだろうか。
もう少し若い世代の女性であれば、レギンスやストッキングのメーカーとして馴染みがあるかもしれない。
令和の今、グンゼはそういったインナー・レッグウェアはもちろん、プラスティック製品や省エネ素材、さらにタッチパネルやスポーツクラブの運営など幅広い分野に進出している会社だ。
売上高は1,200億円にのぼり、従業員も5,000名を数える大企業である。
では一体なぜ、“子ども向けパンツメーカー”だった同社が最先端素材や不動産まで扱っているのか。
グンゼはもともと、明治19年(1886年)に京都府北部の寒村・何鹿(いかるが)郡で、生糸生産を手掛ける会社として誕生している。
現在の京都府綾部市だが、登記上の本社は今もこの創業の地のままだ。
京都駅から嵯峨野線で特急に乗り、1時間以上も揺られて綾部駅で降りると、何もない駅前に驚くほど小さくて静かな街である。
なお明治19年といえば、日本にこれといった産業もなく国全体がまだまだ貧しかった時代である。
富国強兵の掛け声の下、お茶や海産物などを輸出して外貨を稼ごうとするも、なかなか上手くいかない。
そんな中、日本政府は生糸の輸出で外貨を稼ごうとするが、日本の生糸はとにかく質が悪く特に欧州で悪評だった。

さらに何鹿産の生糸は、国内からも「品質粗悪」と酷評されていたというのだから、寒村の貧しい暮らしぶりが目に浮かぶだろう。
そんな中、縁あってこの地で生糸の生産を手掛けることになったグンゼの創業者・波多野鶴吉は、どうすれば生糸の品質を向上させられるか悩む。
そして出した結論は、こうだ。
「善い人が良い糸をつくり、信用される人が信用される糸をつくる」
良いものを作るには、先に善い人を育てなければならないという、当然の出発点である。
さらに、信用される人でなければ信用される製品など作れないという原点も見出した。
そして工場内に従業員向けの寄宿舎を置くと、多くの教室まで設置し、人材育成に多額の先行投資を行うことになる。
このような経営は決して、奇をてらったものではないだろう。
目新しさは何もなく、おもしろい話ですらない。
しかし現実の会社経営ではそのような、凡事を徹底するリーダーこそが結果を出すものだ。
実際にグンゼの生糸はその後、極めて短期間のうちに「精良優美」という最高の品質評価を、世界で勝ち取ることになる。
さらに1900年に開かれたパリの万国博覧会では金牌を受賞し、翌1901年にはアメリカ向け高品質生糸の輸出が本格的に始まるなど、外貨の貴重な稼ぎ頭に成長し国策に貢献する。
「品質粗悪」と敬遠された寒村の生糸は、わずか15年で世界最高の製品に変貌を遂げたのである。
しかしここでお伝えしたいグンゼの凄いところは、実はそれではない。
1918年(大正7年)、創業者の波多野は60歳で急逝するのだが、彼が育てた後継の経営陣の優秀さこそが同社の、そして日本の宝だった。
昭和初期、米国でレーヨンの生産が盛んになると日本の生糸生産は大打撃を受ける。
生糸よりも安価な繊維素材が普及してしまい、経営環境が根底から覆ってしまったのである。
するとこの経営危機にあってグンゼは、大量の在庫と化した生糸をもとに最終製品の製造・販売に進出する決断を下した。
生糸を生糸のままで売っていては二束三文で買い叩(たた)かれるが、最終製品にまで仕上げてしまえば十分利益が出ると踏んだのである。
さらにこの時グンゼは、原材料から自社で手掛けている強みを活かし、最終製品の品質に徹底的にこだわった。
令和の今でいうところの高級路線を志向し、安い繊維素材では出せない質感と満足感で、消費者の支持獲得を目指すのである。
その価格帯は他社製品に比べ2割ほど高かったというが、「金の品質、銀の価格」と呼ばれブランド化し、1950年代には揺るぎない地位を確立する。
さらに1960年代には時代の変化に合わせ女性向けパンティストッキングを、1970年代のベビーブーム期にあってはベビー用品を手掛けるようになり、アパレル事業の基礎を築いた。
このようにして今日、年配世代がイメージするグンゼ製品が、私たちの日常に浸透していったのである。
他方、同社の経営陣は起死回生の成功体験にも決して、安住することはなかった。
大きな時代の流れはやはり、天然素材から化合繊に移り変わりつつあるのは明白だ。
そのため1950年代には新たな繊維素材の研究を始め、1970年代には本格的に化繊の製造・販売を開始する。
さらにその過程で化学製品の取り扱いノウハウを得て、包装資材の内製化を果たすと、さまざまな石油化学製品の製造にも乗り出す。
このようにして、プラスティック、塩ビ、特殊フィルムと事業領域の拡大を続け、令和の今ではタッチパネル素材の製造まで手掛ける総合メーカーにまで、成長を果たしたということだ。
常に10年20年先の時代を取り込み、強みを活かした横展開で変化に適応し続ける同社の経営は、呆れるほどに逞(たくま)しい。
成功とは衰退の始まりであり、順調だからこそ危機意識を持たなければならない重要性をも、私たちに突きつけてくれている。
137年続くこの“常に新しい老舗企業”から私たちが学べることは、余りにも多い。
美味しいラーメンであっても…
話は冒頭の、新聞の衰退についてだ。
なぜ、新聞各社の売上減は単に経営陣が世間の感覚からずれており、今もなお間違っているからだと言い切れるのか。
新聞社の本質的な強みとは本来、「知性ある記者・編集者」が「取材やエビデンス」に基づき、「信用できる情報」を届けてくれることにあったはずだ。
だからこそ戦後、新聞人は知識人とされ、多くの政治家まで輩出し、「第四の権力」と言われるほど国民の強い支持を得続けてきた。
であれば、これこそが、いい加減な情報が流布するインターネットメディアの時代にあって、形を変えながらも守るべき存在意義ではなかったのか。
グンゼが磨き上げた最高品質の生糸を横展開し、絶望的な環境の変化をチャンスに変えたように。
にもかかわらず、発行部数が減少傾向になると経営陣は各社とも浮足立ち、この一番大事な本質を見失った。
そして自社のコア読者層に迎合し、言説の先鋭化が進み、客観性を失い続けている。
このような本質を放棄した方法で、発行部数も売上も維持・回復できるはずなど無いではないか。
もちろん全ての会社、全ての記事・紙面がそういうわけではない。
今もなお、会社により高い志で紙面づくりに尽力している素晴らしい記者がいることも、私は知っている。
しかし「悪貨は良貨を駆逐す」のことわざ通り、ファクトの疑わしい恣意的な言説が僅かに混入するだけで、もうその紙面は全てが台無しになってしまう。
できたての美味しいラーメンにたった1滴の泥水を垂らすだけで、もうそれは誰も食べられない生ゴミになるということだ。
「善い人が良い糸をつくり、信用される人が信用される糸をつくる」
グンゼの創業者・波多野鶴吉が定めたこの創業の原点をみて、新聞各社の経営者は今、何を思うだろうか。
「善い記者が良い紙面をつくり、信用される記者が信用される紙面をつくる」
という想いで、自社の社員を大事に育てているだろうか。
環境の激変を乗り越え137年、強く逞しく成長を続けるグンゼの歴史からぜひ、多くのことを学んで欲しいと願っている。
余談だが、同社は1987年(昭和62年)、祖業である生糸の製造から完全に撤退し91年の歴史に幕を下ろしている。
では今のグンゼは、波多野がつくった会社とは別物なのだろうか。
私は決して、そう思わない。
経営者が創造するものは“本質的な価値”であり、創業の理念は今もなお、経営陣によって墨守され続けているのだから。
グンゼの歴史や経営陣のこのような決断は、創業の地・京都府綾部市に所在する「グンゼ博物苑」を訪れれば、より肌感覚で体験できる。
明治時代の社屋が今もそのままに博物館になっており、訪れるだけでも楽しめる場所だ。
京都駅から特急で1時間以上かかる長旅になるが、それだけの価値がある場所である。
ぜひ企業や組織のリーダー、リーダーを志す人には一度、足を運んでもらいたいと願っている。

「置かれた場所で咲きなさい」と言うリーダーは無責任 必要なのは「便所のネズミ」話

『置かれた場所で咲きなさい』という、累計200万部の国民的ベストセラーになった1冊の本がある。
修道女でもある故・渡辺和子さんが2012年に著した作品で、宣教師から渡された
「Bloom where God has planted you(神が植えたところで咲きなさい)」
というメモに救われた体験を元にした、自叙伝的なエッセイである。
” 置かれたところこそが、今のあなたの居場所なのです”
という印象的な言葉とともに紡がれる文章は美しく、多くの悩める人を勇気づけたのだろう。
ネット上での書籍レビューは概ね高評価で、多くの人に愛される理由の一端を垣間見ることができる。

しかし私は、誰かをエンカレッジする時に正直、この言葉をとても使う気にはなれない。
さらにいえば、この言葉は無責任であり卑怯であるとすら思っている。
国民的な大ベストセラー相手に異論を投げかけるなど我ながらいい度胸だと思うが、以下少しお付き合い願いたい。
”採用詐欺”
話は変わるが、私はかつて地方の中堅メーカーで、経営の立て直しに携わっていたことがある。
債務超過に陥り、キャッシュフローベースでも出血が続く、時間の問題で法的整理が視野に入っているような会社だ。
売れるものはすべて売り、また金融機関にはリスケ(債務の繰り延べ)を申し入れ、大株主には資本援助を依頼するなど、とにかく資金手当に奔走するのが役割のような仕事である。
そんな中、規模は縮小してでも新卒採用だけは続けることを決めた時のこと。10名ほどの採用枠に、最終の役員面接まで20名ほどが残っていただろうか。
候補者は皆が優秀で、そのことは書類上からも十分にうかがい知ることができた。
そして特に目を引く一人の女性がいた。
その女性はいわゆる“一流”の国立大学を卒業見込みで、成績も最上位の評価ばかりが並ぶ。
海外留学経験にTOEIC900点、中国語もビジネスレベルで話せるなど、“地方の中堅企業ていど”に応募してくるとは、とても想定できないような学生さんである。
そんなこともあり、彼女が入室すると私は一通りの書類確認を終えた後に、率直にこう切り出した。
「あなたの能力・成績は素晴らしいものだと、大変評価しています。逆に、ウチを志望して下さった理由がわからないほどです。弊社のどのようなところに、興味を持ってくださったのでしょうか」
すると彼女は、自社が保有する特許、事業展開予定を引用しながら、その際に語学力を生かしリーダー的なポジションを任されたいといったような、野心あふれる想いを語ってくれた。
さらに、大きな会社で小さな仕事から積み上げるほど気が長くないので、中堅クラスの会社で最初から大きな仕事を任されたいというような意欲も話してくれた。
なるほど、それらは自社の会社案内などで公開している情報であり、説明に矛盾はない。
しかし実はそれは、もう3年は前のものであった。
今となってはそれどころではなく、積極的な投資は全て中止し、まずは手段を選ばず出血を止めるのが最優先の局面に変わっている。
つまり、彼女のやりたい仕事や夢を実現できるフィールドは、当社にはもはや存在していないのである。
事業の立て直しがまだ見通せない中で、彼女が当社に入ればきっと「こんなはずじゃなかった」と、不幸になるだけだろう。
そう判断した私は結局、迷いに迷ったが彼女に内定を出さなかった。
すると驚いたのが、一つ前の面接を担当した管理職や、当然採用するであろうと思っていた経営トップである。
確かに、いろいろな能力に優れているであろう彼女がもし本当に当社に定着してくれたら、大きな戦力になったかもしれないので、当然の反応だ。
しかしもし彼女に内定を出し入社をしてくれていたとしても、程なくして退社を選んでいたことは目に見えている。
というよりも、「実現できない夢」をエサに入社をさせるなど”採用詐欺”というものであり、人としても会社としても間違っているというものだ。
しかしそれを説明しても理解してもらえると思わなかったので、私はただ一言、
「能力はあると思いますが、当社にふさわしい人材ではありません」
と、内定を出さなかった理由を皆に説明した。

「どうかお力を貸して下さい」
与えられた職責で決めたこととは言え、このような判断は批判されて当然のことであると、当時も今も思っている。
その上で私がこの判断をしたことには、実は伏線があった。
最終面接の、おそらく1週間ほど前だろうか。
中堅クラスの社員に会議室に呼び出され、こんな抗議を受けることがあった。
「なんでこんなに頑張っているのに、給料を減らされるんですか!」
実は私はこの時、経営立て直しの最終手段として、従業員の一律5%の給与カットを通知していた。
6カ月の時限的な措置ではあるが、これは本当に従業員の士気を崩壊寸前まで追い込む悪手である。
他に方法が無いとはいえ、これほどやるべきではない施策はないだろう。
十二分にわかってはいたが、ネガティブな反応は予想以上だった。
「お客様のために誠実に仕事をしているのに、納得できません…もう私、会社のために頑張れません…」
そういうと彼女は、大粒の涙をボロボロと流した。そして、仕事に責任が持てないので転職を考えているということも、素直に話してくれた。
私はそれに対し、反論ができなかった。
「今はどうか、耐えて下さい。必ず何とかしますので、私を信じて下さい」ということすら、言えなかった。
実はこの時、私の選択肢の中にはすでに、事業売却や会社全体の身売りも視野に入っていた。
であれば、その場しのぎで「今は耐えてほしい」「私を信じてほしい」などとは、とても言えなかったということだ。
彼女も、資格や経験をいかし転職したほうが、充実したキャリアを積むことができるだろう。
そのためただ、「本当に申し訳ございません。宜しければどうか、お力を貸して下さい」と、頭を下げることしかできなかった。
人として誠実であることと、企業の役員あるいはリーダーとして職務に忠実であることは、時に矛盾する。
その意味で、私のこの時の態度は役員として失格であったのかもしれないが、しかし同じ状況になれば何度でも、同じように行動するだろう。
「嘘をつかないこと」
「人として誠実であること」
はリーダーとして絶対に欠いてはならない最低限の品位であり、“信頼”を得る上で何よりも大事な守るべき価値観なのだから。
便所のネズミ
話は冒頭の、『置かれた場所で咲きなさい』についてだ。
なぜ私が、”置かれたところこそが、今のあなたの居場所です”などと口にすることは無責任であり、卑怯であるとまで思っているのか。
もし私が、自社では明らかに夢を叶えられないあの時の学生を採用し、その後、退職を悩み始めた彼女に対しこの言葉で説得をしようものなら、きっとぶん殴られていただろう。
転職を考えていると大粒の涙を流した社員に、「置かれた場所で咲きなさい」などと説教したら、「お前が言うな!!」と、お茶をぶっ掛けられていたかもしれない。
つまりこの言葉は、「相手の人生に対して、責任がない人」しか使ってはいけない言葉ということである。
言い換えれば、「問題の解決を、本人の意識・考え方に丸投げする言葉」と言っても良いかもしれない。
唯一、この言葉を本当に相手の心に届けられる人がいるとすれば、それは渡辺和子さんがそうであったように宗教家や学校の先生など、道徳的な指導を期待されている人に限られる。

少なくとも、企業経営者やリーダーが部下に使えば、それは精神論であり、問題のすり替えにほかならないだろう。
だから私は、この言葉を無責任であり卑怯であると思っているということだ。
最後に、こんな話がある。
秦の始皇帝に仕え、その天下統一を補佐した李斯は元々、田舎の小役人であった。
そして「自分はこのまま、こんなつまらない人生を過ごしても良いのか」と悩んでいたある日、便所の片隅で人に怯えながら汚物を食べ生きる痩せネズミを見かけ、嘆息した。
「俺もこのネズミのような、つまらない存在だ」と。
またある日、穀倉の中でもネズミを見かけるのだが、そのネズミはあり余る穀物を食べて肥え太り、人間の姿にも全く怯えることがなかったそうだ。
その姿を見た時に、彼は悟った。
「人生もネズミの生き方も、生きる場所次第ではないか」と。

そして彼は一念発起し勉学に励み、始皇帝に見い出され、歴史に名を残す大人物になっていくことになる。
もし彼が、“生きる場所”を変える努力をしなければきっと、田舎の小役人のまま、悲嘆の中で一生を終えていただろう。
「石の上にも三年」
「置かれた場所で咲きなさい」
といった価値観が尊いことは、論を俟たない。どんなことでも、自分の力が及ぶ限り努力し、必死になって喰らいついていくべきだろう。
しかしその上でどうにもならなければ、李斯のように生き方や環境を変えてしまうことも、決して迷うべきではない。
人生をやり直し、新たなチャレンジに踏み出すことは決して逃げることではないのだから。
「置かれた場所で咲きなさい」という言葉を重く感じたら、きっと心が疲れているはずだ。
そんな時にはぜひ「便所のネズミ」の話も思い出して、人生でベターな選択をする参考にして欲しいと願っている。
プロレスは”八百長”ではない それがわかればビジネスリーダーに必要な資質が見える

プロレスは真剣勝負か八百長か。
そう聞かれたら、おそらくほとんどの人が八百長と答えるのではないだろうか。
実際に、プロレスが真剣勝負であろうはずなどない。
ドロップキックはジャブほどしか効かないはずなのに、十六文キックが人を失神させるほどのダメージがあるなど、どうなっているのか。
アントニオ猪木の引退試合は55歳の時だったが、33歳のドン・フライにコブラツイストで完勝するなど、社長だからといってやり過ぎというものである。
プロボクサー上がりのドン・フライが本気でぶん殴ったら、還暦間際の猪木は秒で病院送りになっていただろう。
にもかかわらず、観客は猪木の“最後のファイト”に酔いしれ、「行けばわかるさ」の引退スピーチは伝説になった。
ではなぜ、昔の子どもたちは「何かおかしい…?」と思いながらもプロレスにあそこまでアツくなったのか。
それはきっと、プロレスが“八百長”ではないからだ。
それどころか、プロレス人気の盛衰と日本経済の盛衰は時期を一にしており、「プロレス的価値観」を失ったことが、日本の大人をダメにした原因ではないかとすら思っている。
それはどういうことか。

「暇と思われたらどうしよう」
話は変わるが、私はかつてある会社でCFOを務めていたことがある。
とはいえCFOとは名ばかりで、数カ月後には潰れるような会社をなんとかして延命させ、可能であれば立て直すか身売りするというのが、株主から期待された役割だった。
そんなある日、思いつめた表情の若手社員が私の席まで来ると、時間を取って欲しいとリクエストしてきた。
紅潮した頬、潤んだ両目からはあまり放置すべきでない空気を感じさせる。
そのためすぐに会議室に場を移すと、彼は怒りに任せて話し始めた。
「ウチのバカ部長をなんとかして下さい!」
聞けば営業部には、「P(プライオリティ)マトリックス」なるものを付けさせる習慣があるとのこと。
仕事を「重要」「緊急」のマトリックスシートに箇条書きで書き出し、それに時間予算を割り振って、毎日の仕事を15分単位で管理するというものだそうだ。
しかもそれは毎朝チェックされ、夜にはその通りに動いたかどうかの事後チェックまでされるという。
なるほど、むかし何かの経営本で読んだような考え方である。
デタラメながらも行動が“可視化”されるので、上司が「しっかり管理していますアピール」をするにはうってつけなのだろう。
される方はたまったものではないが。
「ストレスを感じるのはよくわかります。私だってこんなことされたら、発狂します」
「ですよね、あいつ頭おかしいんですよ!」
「それはそうとして、一つ教えて下さい。毎日15分単位で計画を立てて動くほど、本当に忙しいですか?」
「…え?」
「14~18時、暇だからオンライン将棋と書いたら、なんて言われますか?」
「メチャメチャ怒られると思います」
「なるほど…」
「…はぁ」
キョトンとしている彼にはお礼を伝え、この無意味な作業は一度、部長と話し合うことを約束すると仕事に戻らせた。
実はこのとき、私は既にその会社の「潰れそうな理由」について、確信に近い原因に行き当たっていた。
それは人が多すぎることだ。労務費率は同業他社水準を大きく上回っていたが、特に営業部門と間接部門では仕事量に対して、明らかに人が多い。
にもかかわらず、皆が忙しいとパソコンにしがみつき、管理職は眉間にシワを寄せ画面を凝視している。数字の上からは、人員に余裕があることはほぼ間違いないにもかかわらずだ。
ではいったい、皆なぜそんなに“忙しい”のか。
その元凶は、この「Pマトリックス」なるおかしな習慣が、他の部門にも形を変えて全社的に存在していることだった。
つまりその会社には、「9時から18時まで形ばかりの予定を詰め込み忙しそうにしないと怒られる」という文化が、仕組みとして強固に存在していたということである。
こんな仕組みで一日の予定を”可視化“されたら、誰だって2時間で終わる仕事を4時間かかることにするだろう。
それだけならまだマシで、人によっては就業時間に合わせ、無意味な仕事を作り出すことすらやってしまう。
コピーが曲がっているといってはやり直させ、仕入先に些細なクレーム電話を入れひたすら時間を潰しだす。
そんなことをしていたら組織も人の心も歪み、会社がもつわけがない。
状況を理解した私は、役員会に一つの提案をすることにした。
それは、選択的週休3日制の導入と、週休3日を選んだ社員とは雇用契約を結び直し、10%程度の年収減を提示することだ。万が一、間接部門の全員が週休3日を選んでも業務量は100%、完全に遂行できるだろう。
一人も解雇すること無く、希望する従業員のワークライフバランスは向上し、なおかつ労務費を相当程度削減できるのだから、これ以上はない打ち手であろうと思われた。
しかしこの提案は、役員会でほぼ全員に反対され却下される。
特に経営トップの意志は明確で、
「労働基準法の上限まで働かすことができる雇用契約を結んでいるのに、なぜそんなことをするのか」
というものであった。
「給料を払っているのに、使い切らないともったいない」
という趣旨のことも言った。
なるほど、だから「Pマトリックス」のようなものが存在し、皆が忙しいフリをする企業文化が根付いたのか。
全ては経営者の考え方であり、だから皆が「暇と思われたらどうしよう」と恐れ、次々と無駄な仕事を作り出して労務費が肥大化していったということだ。
結局この会社で私は再建を諦め、経営トップには事業を売却し経営から降りるよう勧めた。
そしてその通りの結末でイグジットしたが、新しい経営者の下で無意味な習慣は全て廃止され、利益率も大幅に改善したと聞いている。
従業員1,000名近い中堅規模の会社だったが、それでも経営トップたった一人の哲学で、組織はここまで変わってしまうことを思い知った出来事になった。
◇ ◇ ◇
本来、経営者やリーダーの仕事とは、「短い時間で多くの成果を上げること」である。
やるべき仕事が終わったのなら「午前中で帰っていいよ」と言えるようなリーダーこそ、本当は評価されなければならない。
同じ仕事量なら短時間で仕上げるほうがエライのだから、当たり前ではないか。
それを、「時間いっぱい使い切らないともったいない」などと考える経営者は、控えめにいってかなり頭が悪い。
そんなことをすれば従業員も「就業時間に合わせて仕事を引き伸ばす」に決まっているのに、なぜその程度のこともわからないのか。
そしてこのような「同じ仕事量なら、長い時間をかけて働く従業員こそエライ」という狂った感性を持つ経営者は、決して少なくないのが実情だ。
そんな状況に苦しむ、あるいは思い当たるビジネスパーソンも、きっと多いのではないだろうか。
”意識の高い人”が、組織をぶっ壊す
話は冒頭の、「プロレスは八百長ではない」についてだ。
プロレスは確かに、持病を持っていそうな50~60代のベテランが、屈強な20~30代の若者をKOしてしまう不思議な“格闘技”である。
正直、令和のプロレスについてはよく知らないが、昭和のプロレスとはそういうものであった。
そして私はそんなプロレスを、 “八百長”ではなく「戦闘シミュレーション」であったと思っている。
自衛隊にはバトラーと呼ばれるレーザー交戦装置があり、敵味方に分かれた実戦さながらの模擬戦闘訓練を行うが、あれと同じだ。
勝敗は誇りであり、部隊の精強さをそのまま示すが、実弾を撃ち合うわけではない。
しかし実弾でやりあった前提で、被弾した部隊や個人はそのように振る舞い、戦いを進めていくことになる。
このような、プロレスや自衛隊の「シミュレーション能力」は、本当にスゴイものだ。
見ている人を本気で興奮させ、あるいは国の安全保障を託すほどの信頼性で仮想現実を作り出すのだから。
実は先にお話した「Pマトリックス」では、経営トップ以上に困ったのは、間違った指導をする管理職だった。
「資料作成3時間」などと書かれていた場合、「この資料作成に3時間もかかるわけ無いだろう!1時間でできることを俺が証明してやる!」などと言って実際にやってみせ、部下を理詰めで凹ませるものもいた。
しかしそんなことをしても全く無意味なことは、少し考えれば容易にわかるだろう。
本質的に暇なのだから、部下は簡単に論破されない予定を代わりに入れて埋めるだけである。
無能なリーダーはこのように、自分の言動がどのように組織に影響を与えるのかを全くシミュレーションできず、ひたすら無駄な仕事を生み出して組織を破壊していく。

時代は令和になり、昭和に比べ世の中にはさまざまな「経営ノウハウ」が溢れるようになった。
頭のいい人が考えた「Pマトリックス」のようなロジックも生まれ、それを自社に取り入れる“意識の高い人”もたくさんいる。
しかしそれでも経営状況が良くならないのであれば、それは「運用をするリーダーが、基本的に頭が悪い」からである。
全体最適を考えずに、どこかの会社で成功したシステムや考え方を中途半端に導入したところで、成功するわけがない。
そんなリーダーに溢れる令和の世の中よりも、十六文キックで失神してみせた昭和のレスラーたちのほうがよほど、仕事というものをわかっていた。
全体を俯瞰し、ロールを演じられるというのはそれほどに難しく、そして令和の今こそ昭和のプロレスから学び直すべき価値観である。
まあ、「昭和は良かった」って言いたいだけなんですけどね。
マスクを着けたら別人格 人生を大逆転させたプロレスラーの話

マスクは何かを隠す消極的なアイテムとは限らない。マスクが心身に力を与え、人生が大逆転することもある。
「山田ってこんなに強かったっけ」。元号が昭和から平成に変わった1989年、プロレス雑誌を読んでいた高校生の私は驚いた。長髪をたなびかせる独特のマスクをかぶり、獣神ライガー(現獣神サンダー・ライガー)に変身した山田恵一が、初代タイガーマスクの好敵手、小林邦昭を撃破し、快進撃を演じたのだ。

私は小学生のとき、漫画「キン肉マン」でプロレスにはまった。二つ年下の弟をバックドロップでマットにたたきつけ、プロレス名鑑でレスラーの身長と体重を見比べて大きさや強さを想像する熱烈なマニアだった。
名鑑のなかにとびきり小さいレスラーがいた。山田だ。身長170センチ、体重は90キロ台。掲載された数百人のレスラーの中で、山田と同じぐらい小柄なのは「小さな巨人」グラン浜田か「鬼軍曹」山本小鉄らわずか。あどけなさが残るベビーフェースも華やかさを欠いた。
同世代には、スター候補として売り出された闘魂三銃士(武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也)らがひしめいていた。
そんな山田に転機が訪れた。89年の英国遠征の際、所属する新日本プロレスから覆面レスラーへの転身を打診された。永井豪原作のアニメとのタイアップだ。「マスクマンにあこがれていたのでOKの二つ返事でした」。山田は書面インタビューにそう答えた。
「俺は一生、このキャラクターでやっていきます」。30年ほど前、週刊ゴング編集長だった清水勉(64)は山田からこんな決意を聞かされた。清水は振り返る。「それまでもコツコツといい試合を続けていたが、どうしても地味な存在だった。自分に足りないものが分かっていたのではないか」

顔を入れ替えた山田は激しいファイトを武器に好勝負を繰り広げ、強烈なキャラクターに生まれ変わった。昨年1月に引退するまで、日本のジュニアヘビー級を代表するレジェンドとして君臨。「マスクをかぶると、完全にライガーとして違う人格になる」と山田は言う。
ライガーのほか、初代タイガーマスクらのマスクを製作してきた職人の中村之洋(54)は「人気レスラーの顔をお預かりし、身が引き締まる思いだ」と語る。

覆面レスラーにとって、マスクとはどんな存在なのか。初代タイガーマスクの佐山聡は中村を通して「ファンが自分を見て感激してくれたり、涙してくれたりする、すごい存在だ」とコメントした。佐山は現在、自律神経の病気を患い闘病中だ。
メキシコのスーパースター、ミル・マスカラスを覚えている中高年のファンも多いだろう。試合のたびにマスクを変えて「千の顔を持つ男」と呼ばれ、大ブームを巻き起こした。清水によれば若いころは俳優アラン・ドロン似で、80歳前後とされる現在はショーン・コネリーに近い。

「でもこの世界はイケメンだからといって成功するわけじゃない。マスクをかぶるとミステリアスな存在になる」。顔よりも、マスクがくれるキャラクターを私たちは愛したのだ。

ミッドウェー敗戦から学ぶビジネスリーダーの心得 戦略目標を曖昧に共有する危うさ

いきなりの不謹慎な話で恐縮だが、私は人生で一度だけ、人を本気でぶっ殺したいと思ったことがある。
30代の半ば頃で、地方の中堅メーカーでCFO(最高財務責任者)をしていた時のことだ。
私に期待されていた同社での役割は、経営不振に陥っていた事業の立て直しだった。
そして6年ほどの再建期間を経て、会社をM&Aマーケットに出した時のこと。
当初、2億円でも売れなかった会社をビッド(入札)にかけ交渉を重ねた私は、A社から10億円の、B社から5億円の応札を引き出すことに成功する。
当然のこと、A社を最終候補に決めると渋谷の本社に経営トップとともに出向き、最終的な合意が成立した。
「本日はありがとうございました。来週末にはこちらから大阪にご挨拶返しに行きます。その時に捺印した契約書もお持ちしますね」
「ありがとうございます。ではそのまま、夜は一席ご用意させて下さい」
「いいですね、楽しみにしています!」
そんな和やかな会話の中で全ての交渉が終わり、心地よい疲れの中で東京駅に向かう。
そして金曜日の最終で混み合うのぞみに乗ると、経営トップは冷えたビールとつまみを袋から取り出しながらこんな事を言った。
「桃ちゃんのおかげで、なんとかいい形で会社も俺もイグジット(出口に到達)できた。本当にありがとう」
この時の缶ビールは、人生で飲んだどんな酒よりも最高に美味かった。
大きな、そしていい仕事ができた自分にも、私は心から満足していた。
6年も掛かってしまったが、ストレスフルな仕事もいよいよ終わりかと緊張の糸が切れ、思わず涙ぐんでしまったことを今も良く覚えている。
そして私はデッキに出ると、その場でB社に正式に、交渉打ち切りの電話を入れた。

しかし翌月曜日、会社に行き経営トップから呼び出された私は、思いがけないことを告げられる。
「桃ちゃんごめん…!やっぱりB社を選ぶことにした、A社に断りの連絡を入れてくれ!」
「は…?何を言ってるんですか社長。口頭とはいえ、経営トップ同士で合意し法的拘束力もあるんですよ?」
「桃ちゃんには悪いと思ってるけど、そこを何とかするのが君の仕事やろ頼む!」
「社長、考え直して下さい。相手は一部上場企業で、財務・法務も総出で積み上げ、トップ同士で最終合意したんです。そんなもん通るわけないでしょう」
「ええからなんとかしてくれ!もう決めたんや!」
経営トップは結局、どれだけ説得しても私の言葉に耳を傾けなかった。
そして本当に私は、今度はA社に交渉打ち切りの電話を入れ、謝罪のため一人で渋谷に向かうことになったのである。
その時、東京行きの新幹線に放心状態で座りながら、私は本気で思った。
「あの野郎、マジでぶっ殺してえ」と。
しかしそれから20年近くの時間が経った今、私は当時のことを全く違う形で振り返っている。
「あの失敗は、自分の責任だった。恨まれるのはむしろ、自分の方だ」と。
”世界最強”はなぜ敗れたのか
話は変わるが、近現代史に詳しい人であれば誰もが、ミッドウェー海戦における日本の大敗には不思議な、あるいは複雑な思いを持っているのではないだろうか。
太平洋戦争の開戦から半年後、1942年6月に戦われたこの海戦では、日米両海軍の主力が正面から激突した。
そして日本は、この戦いで参加空母4隻全てが撃沈されるという、歴史的にも類がないほどの惨敗を喫している。
これ以降、日本は太平洋における戦いの主導権を失い、敗戦に向け坂を転がるように墜ちていくことになるのは、ご存知のとおりだ。
しかし実はこの戦い直前、客観的な戦力比で日本海軍は、圧倒的に優勢な状況にあった。
それどころか、当時の日本は瞬間的に、世界最強の空母機動部隊を擁していたといっても過言ではないだろう。
実際に、この戦いで指揮を執った米海軍のニミッツ提督は、日本軍の暗号を解読しその戦力・作戦の全容を把握した時のことを、後日こう振り返っている。
「それは不可避な惨事を事前に知ったようなものであった」(中央文庫:失敗の本質p78)
にもかかわらず、結果は日本海軍の一方的な惨敗に終わった。なぜか。
この戦闘は日本海軍が仕掛け生起したものだが、その目的は米軍のミッドウェー基地に攻撃を加えることで、米空母の誘出を図るものだった。
地図をご覧頂ければ明らかだが、ミッドウェー島が落ちれば米太平洋艦隊の本拠地であるハワイは外堀を埋められる形になり、危機に陥る。
そのため日本が同島を攻撃すれば、米海軍は空母を含め全力で反攻に出てくるに違いない。
そこを、戦力で上回る海軍主力で叩き殲滅をすれば米国は継戦の意志を失い、日本に有利な条件で講和を結べるのではないか。
それが日本海軍の立てたシナリオだった。
結果としてこの作戦で、米海軍は空母を含む太平洋艦隊の主力を釣り出されたので、日本の戦略そのものは正しかったといって良いだろう。
このようにして日本海軍は、ミッドウェー島への攻撃を開始し、米空母の誘い出しを図る。
するとまさにその瞬間、予期していなかったタイミングで空母を含む米海軍主力が現れたのである。
親熊はいないと思い込み、目の前の子グマを小突き始めたら、背後に立っていたような形だ。
しかしながら、ミッドウェー基地攻撃用の兵装と敵艦隊攻撃用の兵装は全く異なるため、攻撃目標の即時変更などできるものではない。
そのため日本海軍の攻撃隊指揮官・南雲忠一中将は急ぎ武器の換装を命じるのだが、時すでに遅しであった。
作戦の変更に伴う混乱で反撃能力を失っている日本空母に、米軍の空母を飛び立った艦載機が先制攻撃を仕掛け、次々に襲いかかってしまったのである。
そして甲板上に爆弾や魚雷などが無秩序に散らかっていた日本軍の空母は、敵の爆弾が一発命中しただけでも次々に大爆発を起こし、轟沈していった。
このようにして、日本海軍主力はあっけないほど一瞬で消滅し、熟練パイロット多数とともに戦争の主導権を失うことになったのである。

いったいなぜ、こんな事が起きてしまったのだろうか。
その原因の一つを、戦史の名著として知られる「失敗の本質 日本軍の組織論的研究」(戸部良一、野中郁次郎他共著)では、以下のように分析している。
「目的の単一化とそれに対する兵力の集中は作戦の基本であり、反対に目的が複数あり、そのため兵力が分散されるような状況はそれ自体で敗戦の条件になる」
要するに、日本海軍の戦略目標はミッドウェー島だったのか、それとも米海軍の空母だったのか、組織の意志統一が全くできていなかったということである。
この作戦の本来の目的は、米海軍の空母を中心とする主力の誘い出しと殲滅であった。
にもかかわらず、本末転倒にも日本の空母機動部隊はミッドウェー島にほぼ全ての戦力を投じ、攻撃を開始してしまった。
そこを米空母群に襲われたのだから、全滅して当然であろう。
敵将・ニミッツ提督はこれを「dual purpose(二重の目的)」と表現したが、戦術・戦闘において最悪とされる、軍事上の禁忌の一つだ。
どれほど優れた兵士と装備を準備しても、曖昧な目的と作戦で戦うと、組織はこれほどにあっけなく崩壊してしまう。
そんなことを改めて証明してしまった、取り返しようがない日本海軍の敗戦であった。
結局、誰のせいで敗れたのか
話は冒頭の、M&Aの話についてだ。
正式に合意をした契約をちゃぶ台返しするような経営トップの暴挙について、なぜ私は今、自分の責任だと感じているのか。
金曜日の夜、新幹線からB社に交渉打ち切りの電話を入れた私は、それで全ての仕事が終わったと思っていた。
しかし翌日の土曜日、実はB社の経営トップが急遽大阪まで来て当社の経営トップを訪問すると、こんなことを約束する一幕があったことを、後日知ることになる。
「社長、A社に売却したらあなたは会長に祭り上げられて終わりなんですよ。本当にそれでいいのですか?」
「ウチに売却してくれるなら、次の社長も息子さんにすることを約束します。一緒に頑張りましょう!」
嘘のように思われるだろうが、経営トップが翻意したのはたったこれだけの囁きによるものであった。
このようにして、10億円を提示したA社ではなく、5億円を提示したB社に会社を身売りすることが、本当に決まってしまったのである。
私はこの時、自社の経営トップの本心を全く見抜けていなかった。
彼にとっての戦略目標は、少しでも高く株を売ることで、穏やかに引退することだと思いこんでしまっていた。
しかし彼にとってそれは次善の策であり、最善はなんとかして社長であり続けることであって、願わくば自分が育てた会社を息子に継いでもらうことだったのである。
その後、程なくして私は同社を去ったが、無意味な口約束の多くが当然のように反故にされたことを、風の便りで聞いている。
私と経営トップは、戦略的な優先順位を曖昧に共有したまま作戦を進め、取り返しのつかない敗戦で社長自身を含め、多くの株主に多大な損失を与えてしまったということだ。
そして話は、ミッドウェー海戦についてだ。
先述のようにこの戦いでは、作戦を立案した連合艦隊司令部の戦略目標が、作戦の実行部隊である攻撃隊に曖昧な形でしか伝わっていなかった。
もし正しく共有されていたら、ミッドウェー島に全戦力を投じるような戦い方など到底、選択されていなかっただろう。
そうなれば、この戦いはニミッツ提督が予想したように、米軍にとってこそ悲惨な結果に終わっていたのかも知れない。
戦略を立案した山本五十六・連合艦隊司令長官、攻撃を指揮した南雲忠一・中将のどちらが悪いというものではない。
どちらも同じ重さで、敗戦に対し責任を負うべきリーダーである。

同様にもしあの時、私自身に僅かでも、創業経営者の心根や心情に思いを馳せるような人間力があれば、きっと経営トップにこう聞いていただろう。
「社長。A社への売却に際し最後に、個人的になにか付け足したい条件はありませんか?」と。
その程度のことさえできていれば、結果は全く違うものになっていたはずだ。
経営トップも私も同じ重さで、敗戦に対し責任を負うべきリーダーだったということである。
それにしても、ドイツ初代宰相のビスマルクは、
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」
と喝破したそうだが、本当にそんな賢者などいるのだろうか。
私はいつまで経っても、失敗の経験から学んだことを振り返ってみたら、歴史上に同じような教訓が転がっていることに後から気がつくことばかりだ。
この分だと、賢者になることは一生かかっても、無理そうである。

ティネクト(株)取締役CFO、(株)鹿せんべい代表取締役。大和証券をへて、中堅メーカーなどでCFOやTAMを歴任し独立。近現代史や経営論を中心に執筆中。大阪防衛協会賛助会員、習志野自衛隊協力会法人会員、日本国自衛隊データベース管理人。


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













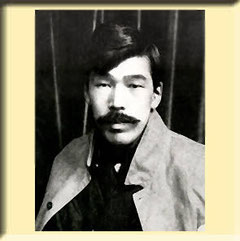














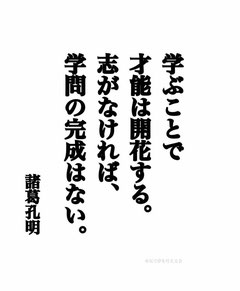

コメントをお書きください