百戦錬磨の営業マンが続々と入社する会社があった!
人手不足の時世にあって、百戦錬磨の営業マンたちが続々と入社してくるベンチャー企業がある。
2019年創業の新興ハウスメーカーの「タカマツハウス」(本社東京・高松コンストラクショングループの100%子会社)は、20年の営業開始以来、わずか4年目にして売上高が191億円(23年3月期)に達した。計画も野心的で、2025年3月期には2.6倍の500億円を目指している。

後発ハウスメーカーでありながら急成長を遂げることができたのは、優秀な営業マンが結集したことと、育成によって新米営業マンたちが育っているからだ。営業人員は現在75名。4年前にたった3名で立ち上げられた同社において注目すべきは、その成長力を担保する人材の吸収力と育成力だ。
21年度期初の営業マンは28名、これが期末には59名と倍増した。さらに今期には100名に達すると見込まれている。たった3年で3倍以上に膨れ上がるわけだ。
この人材吸収力の秘密は、過重ノルマですっかりブラック化した日本の営業現場に改めて「信頼の旗」を立てたことにあるだろう。
「クソどうでもいい仕事」からの解放
タカマツハウスのトップ営業マンで、営業所長を務める小山哲也(仮名)の前職は、同業の住宅メーカーでの営業だった。彼は転職の理由をこう語る。
「前の職場は、結果を残せる人間だけが重宝され、そうでなければ『ダメなヤツ』のレッテルを貼られた。私はそれなりに成績を上げていたけど、一時の営業結果で早々に見切りをつけられる環境が恐ろしかった。そんな会社では優秀な人材も倒れるまで走り続けるしかありませんからね」
同じ組織にいるのに周りは全て競争相手。会話も少なく、上司も部下もみんな数字しか見ていない。そこに血の通う人間関係など築けるはずもなく、いつしか仕事がむなしくなった。
ちょうど世間で「ブルシッド・ジョブ(クソどうでもいい仕事)」という言葉が流行り出したころ、自分の仕事が人の役に立っているという満足感がないことに疑問を抱くようになった。
「人を育てるという意識のない組織にいると息が詰まる。むしろ成績のいい人間は、その力を周りに振り分けたほうが働く環境として健全なはずだという思いが募っていった。案の定、会社の業績も停滞するようになってきて、そこで転職を考えました」
小山がタカマツハウスを選んだのは、面接をした社長の藤原元彦が信用に足る人間だと思ったからだった。
ライバルがビビりまくった「営業マンの実像」
藤原元彦もまた優秀な営業マンだった。前職は、積水ハウスの常務執行役員で、4年前、高松コンストラクショングループにタカマツハウスの創業社長として迎えられた。
藤原は、サッカーに明け暮れた大学時代を経て85年に積水ハウスに入社した。以来、戸建住宅の営業マンとして活躍し、年間契約棟数全国1位をはじめ数々の賞を受賞した。

1962年生まれの60歳。横浜生まれのシティボーイでイケメンの藤原は、女性や顧客にはよくモテたが、実力を支えたのはその容姿だけではない。
「当時はどうしたらお客さまに好かれるかをいつも考えていた。僕のファンになってもらおうと試行錯誤の連続でした。販売後のアフターメンテナンスはもちろん私が受け付けますし、家を買ってくれたお客さまとはそれぞれ半年に一度は、レストランに招待して食事をする。やがて信頼してくれた方が、次から次に新しいお客さまを紹介してくれるようになりました。やっていたことはシンプルで、誠意を尽くすこと。少しずつ、自分のネットワークが大きくなっていくのが何よりうれしかった」
誠意から始まる信頼関係は、強固なネットワークとなった。関係を深めたのは顧客だけではない。住宅を建てる工務店とも熱心に付き合い、どの工務店に頼めば顧客が納得する仕事をしてくれるかつぶさに調べ上げていた。
いつしか、藤原と契約すれば一流の大工が現場に入るようになっていた。
地道な人付き合いを積み重ねた成果は、キャリアとともに巨大な数字として表れる。藤原はなんと128ヵ月(10年と8ヵ月)連続で契約を取り続けたのだ。この逸話は積水ハウスだけでなく業界中の伝説となっている。
同じ在阪企業として最大のライバルだった大和ハウスの当時の営業マンは、128という数字を聞くと今も身震いがすると言う。
「まさに業界のイチローみたいな存在でした。ボクもそこそこ上位の成績を上げとった営業マンでしたが、それでも32ヵ月連続が限界だった。藤原さんはその4倍の実績を上げたわけです。天文学的な数字でホンマ考えられへん。
当時の注文住宅の営業は、積水ハウスとガチンコで競合しますから、施主様には必ず最初にこう尋ねました。『積水ハウスは誰が来てますか?』『まさか藤原やないですよね?』と。そこで『藤原さんだ』と言われたら、こちらは天を仰いで即撤退ですよ」
司令官の「やるじゃ〜ん」
そんな藤原だから、出世も速かった。
39歳で支店長になり、43歳で営業本部長。常務執行役員になったのは49歳のときで、いずれも同期でトップだった。ただし、その評価は何も営業マンとしての実績だけではない。部下の統率力が異様に優れていたからだ。藤原が凄腕の営業マンとなったのは、細やかすぎる心配りで「自分のファンを作る」という対人関係を心がけていたからだが、それは部下との関係でも変わらなかった。
当時の積水ハウスの部下が言う。
「営業で競合に負けたときはヒヤヒヤしながら藤原さんに報告の電話をするのですが、『しょうがない、つぎ頑張ろう』と慰められる。契約が取れずに叱られることなんて一度もなかった。『自分はこんなことをやった、あの時はこうだった』と武勇伝を長々と語って『だから、お前ももっとやれ』と脅してくる上司とはまったく違う。それでも藤原さんの支店は営業成績がピカイチでした」
別の積水ハウスの当時の部下はこう語る。
「私が20代後半のころでした。とある大型案件が成約できた。このとき藤原さんから電話をいただいたのですが、彼は当時300人も部下のいる本部長です。一兵卒に司令官から電話がかかってくるようなものだから、電話を受けたこちらは何かヤバいことでも起きたのかと身構えます。
すると『藤原だよ、やるじゃ~ん』と一言、それで電話が切れた。若い営業マンが本部長からこんな電話もらったら舞い上がってしまいますよ。藤原さんは一流の人たらしなんです」
タカマツハウスの社長となった今、藤原は部下たちを前にしてこんなことを言っている。
「スーパーマンが一人で10億円を稼ぐより、10人がそれぞれ1億円を稼げるようになったほうが実は儲かるんだ。おまえら、落ちこぼれをつくるんじゃない!」
競合他社から転職した前出の小山は、採用面接の際に藤原から同じことを言われてタカマツハウス入りを決めた。小山はいま、6人の部下を持つリーダーとして、業界未経験の営業マンの育成に力を注いでいる。
‟保身上司“と‟クソ成果主義”と決別した「全員営業」の恐るべき実力…!人手不足の世のなかで「社員が3年で3倍」になった会社があった!
「落ちこぼれを作るんじゃない!」
いま百戦錬磨の営業マンたちが続々と転職してくるベンチャー企業がある。
前編『ブラック企業の営業マンがこぞって転職する会社があった…!そのシンプルすぎてマネできない社員教育「圧巻の中身」』で紹介したように、2019年創業の新興ハウスメーカー「タカマツハウス」(本社東京・高松コンストラクショングループの100%子会社)は、20年の営業開始以来、わずか4年目にして売上高が191億円(23年3月期)に達した。

同社の注目すべき点は、その急成長ぶりよりも、人手不足の時世にあって、たった3年で営業マンが3倍以上に膨れ上がっていることだろう。
28名にすぎなかった21年度の期初の営業マンは、今期、100名に達すると見込まれている。後発ながらタカマツハウスが急成長した理由は、優秀な営業マンが結集したことと、彼らが新米営業マンたちを育てあげているからだ。
社長の藤原元彦は、部下たちにこう発破をかけている。
「おまえら、落ちこぼれを作るんじゃない!」
「ズルはカッコ悪い」
タカマツハウスは、ベンチャー企業らしく役員と社員の距離が極めて近い。
積水ハウスや大和ハウスなどの大手住宅メーカーから転職してきた元トップ営業マンが陣頭指揮を執る現場は、最高幹部の取締役といえども新人の営業の支援を怠らない。ベテランのノウハウを吸収しやすく、新米営業マンにとっては学び多き職場となっている。
一方で、社長の藤原は、おそらくサラリーマンたちにとって最も過酷なルールを課している。「どんなごまかしも許さない」のだ。
営業の現場をよく知らない人には、当たり前のことのように聞こえるかもしれない。しかし、様々な駆け引きのある不動産営業の現場では、白黒はっきりつけられないことばかり。
それでも藤原は、積水ハウスの営業マン時代から「シロはシロ」「クロはクロ」にこだわってきた。それは、数字の問題から生じる現場の軋轢をよく知っているからだ。
ノルマを課されると、サラリーマンは数字をよく見せたいという思いが常に先行する。現場を取り仕切る部長あるいは課長などは、常に粉飾の誘惑が付きまとうのだ。
たとえば、今期まだ成約していない契約でも上司に「数字をあげろ」と言われれば、原則を曲げても来期分の売上を今期に回すということが起こる。それを強制した上司も部下が数字に化粧をほどこしたことを承知で、得意げに幹部に報告する。
どんな職場にもある光景だ。
大手住宅メーカーから転職したタカマツハウスの幹部が言う。
「期末ギリギリの案件では、本来なら来期に入れるべき契約を今期の決算に入れるために手続きを急ぐことはあり得ることです。ところが、社長はそれでも『これは来期の契約分だろ』と原則通りに数字を切り分けていく。社長なのにこんな見栄を張らない人に会ったのは、正直、初めてです」
数字を盛りたい、決算をよく見せたいと思うのは経営者だけでなくサラリーマンの性だが、同時にそれは麻薬でもある。藤原が数字を‟机上でつくる”ことを許さないのは、それが些細なことでも後に腐敗として組織を蝕むことをよく知っているからだろう。
盛られた数字を信じた経営陣が「今期の売上は100だったから、来期は110で頼む」と予算を組めば、現場はさらに粉飾まがいの行為に手を染めなければならなくなる。同時に過大なノルマを押し付けることになり、その度に現場はモラルを失っていく。
ただでさえ甘くはない競争を戦っている現場は、たちどころにブラックとなり果てることだろう。
藤原が言う。
「数字が足りないのは上司の責任。それを部下に押し付けるのは許されない。どうしても足りないなら僕が営業に行ってとってくればいい。ズルいヤツはたくさん見てきたが、その目は必ず死んでいた。背伸びをしても、背は伸びない。そんな人間の生き方はたいていカッコ悪いものです」
プロキシファイトで見せた「社長の筋の通し方」
実は筆者が藤原を取材したのは、今回が初めてではない。知り合ったのは、タカマツハウスが創業したばかりの2019年の晩秋のことで、藤原がとある問題に心を揺さぶられていた時だった。
2017年、東京・西五反田のマンション用地をめぐり地面師詐欺に見舞われた積水ハウスは、当時の会長と社長の間で内紛が起きた。
2018年1月には、地面師事件の取引を決裁した当時の社長一派が、取締役会で会長を解任するクーデターに発展した。失脚した会長の和田勇は、2年後、積水ハウスに著しいガバナンス不全が生じているとして、クーデターを起こした社長一派の一掃を目指して株主提案する。事態は、すべての株主を巻き込んでプロキシファイト(委任状争奪戦)となった。
筆者は、その顛末を拙著『保身 積水ハウスクーデターの深層』(KADOKAWA)にまとめた。
2020年2月に行われた和田の株主提案の記者会見では、その壇上に藤原も立っていた。積水ハウスの経営陣の総入れ替えを求めた和田らは、新たな役員候補の一人として藤原を提案したのだ。
この提案が株主総会で通れば、藤原はタカマツハウスの社長を退任せざるを得ない状況だった。
藤原が和田から「一緒に戦ってくれ」と頭を下げられたのは、会見のおよそ半年前のこと。すでにタカマツハウスは創業し、社長として営業開始にむけて準備に取り掛かっていた。
忙しい最中に筆者の取材を受けた藤原の表情は、珍しく暗かった。
「積水ハウスの実力者だった和田会長は、営業マンとして私が最も尊敬する人物でした。筋を通そうとする恩師の戦いをどうしても手伝いたい。
しかし、高松名誉会長(タカマツハウスの親会社である高松コンストラクショングループの高松孝之名誉会長)もまた、私を見込んでタカマツハウスの創業を任せてくれた大恩人です。和田さんのプロキシファイトに加われば、その恩を裏切ることになる……」
しかし、藤原の決断は早かった。「どちらの恩師も裏切れない」と意を決した藤原は、名誉会長に意向を伝えるため大阪まで会いに行った。高松に面会した藤原は、事の次第をすべて打ち明ける。この時の藤原の行動を知る者の多くは「さすがに名誉会長は反対するだろう」と考えていた。しかし、話を聞いた高松の答えは、藤原の胸を熱くするものだった。
「和田さんを手伝うことは、藤原さんが今やるべきことだ。勝って積水ハウスを立て直してほしい。負ければ、すぐに戻ってきて全力でタカマツハウスを育ててほしい」
東京に戻った藤原は、涙を浮かべながら筆者に高松の言葉を教えてくれた。
藤原は、和田とともにプロキシファイトを戦い義理を果たす。2020年4月の積水ハウスの株主総会で和田の株主提案が敗れると、高松への恩義にこたえるためにタカマツハウスの仕事に集中した。
それからのタカマツハウスの躍進は、すでに業界中に知れわたっている。
創業間もない時期から藤原と行動を共にする、タカマツハウス取締役常務執行役員の金田健也は言う。
「藤原は、人への恩返しや仁義はどういうときに、どのようにして果たすべきなのか、よう知ってはる人やと感心します。彼の行動の一つ一つに、いま失われつつある本来の人との関係の在り方が現れている。人生の大きな買い物である家を売る仕事は、古くからこうした心意気と誠実さで成立していたはずです。その本質はこれからも変わらないと思います」
渾身の契約
大手住宅メーカーで経験を積み、タカマツハウスに転職した細田圭介(仮名)は、昨年、3億円規模の住宅用地の販売交渉を任されていた。
取引相手は中堅企業の社長。事前に社長の用地取得の目的と支払い能力、またどの金額だったら満足するのか、先方の相場感覚を詳細に分析して手ごたえを感じていた。さらに念を入れて交渉の段取りをバックアップするタカマツハウスの幹部たちと打ち合わせた。
最後の一押しとなる誠意を見せるため、交渉の席に役員と販売グループのメンバーを同席させるよう指示したのは、社長の藤原だった。組織の力を十分に引き出した細田は、見事に成約にこぎつけた。
人材育成機能が充実していることを決め手にタカマツハウスに転職してきたベテラン営業マンの小山哲也(仮名)は、異業種から転職してきた用地取得を担当する部下の最初の契約がなかなか決まらないことが気がかりだった。
コツをつかむまで厳しく指導してきたが、部下の打たれ強い性格や知らないことに向き合う姿勢には見どころがあった。
交渉をうまく運ぶノウハウは、社内で広く共有される。社長と現場の営業マンまで、ベンチャーならではの距離の近さと風通しの良さが、現場のモチベーションを支えていた。何より経験の蓄積が、新米営業マンの未来を希望あるものにしているだろう。
社長の藤原は、面接にやって来た若者の話に今日も耳を傾けている。


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













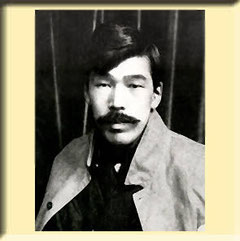














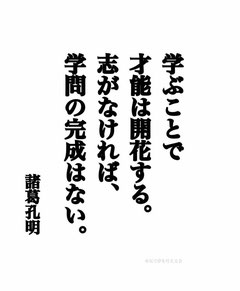

コメントをお書きください