ビート&アンビエント・プロデューサー/プレイリスターのTOMCさんが音楽家ならではの観点から、アーティストの知られざる魅力を読み解き、名作を深堀りしていく本連載〈ALT View〉。今回は、「J-POPの開祖」とも評されるレジェンドのひとり、吉田拓郎について、その活動初期から一般に知られる「フォーク」のイメージに留まらない音楽性を発揮していた事実を解説していただきます。

2022年いっぱいで、惜しまれつつも音楽活動から引退した吉田拓郎。1970年のデビュー後、フォークを青春の音楽として当時のメインストリームに押し上げ、1975年には井上陽水らとフォーライフ・レコードを設立、若者主体の音楽シーンを日本で初めて生み出した伝説的存在である。森進一やかまやつひろしからキャンディーズ、石野真子まで幅広く楽曲提供を行うヒットメーカーとしても広く知られ、90年代以降もKinKi Kidsへの書き下ろしやテレビ出演などを通じ、新しい世代にも親しまれていった。
そんな彼の音楽性は、とかく「フォーク」というキーワードで括られがちなところがある。言葉を畳み掛ける独特の字余り的な作詞・譜割りは日本語のポップスシーンにおいて非常に革新的であったが、アメリカのフォークシンガーであるボブ・ディランからの影響を本人が語っているように、この個性もフォークというキーワードに回収されてしまう。
このように「吉田拓郎といえばフォーク」というイメージが根強くあるが、実は吉田はレゲエ、ソウル、ボサノヴァなど、さまざまなリズム/グルーヴを軸にした音楽性を取り入れている。この事実はもっと多くの音楽ファンに知られるべきだろう。本稿は、そうした彼の音楽的冒険について、特に1981年までの初期の作品に光を当て、あまり世に知られていない名曲の数々を掘り起こす試みだ。
R&Bをルーツに持つ吉田拓郎のグルーヴ
1965年、地元・広島の大学に進学した吉田拓郎は、ザ・ダウンタウンズというロックバンドを結成する。このバンドは“ビートルズスタイル”とも称され、オリジナル曲のほかに、ザ・ドリフターズ(※アメリカのコーラスグループ)「渚のボードウォーク(Under the Boardwalk)」などのR&Bのカバーを広島のディスコや米軍基地で演奏していたという。さらに、吉田はこの活動以前にもザ・バチェラーズというバンドでドラマー兼シンガーとして活動しており、当時の日本語フォークの枠に留まらないリズム感・グルーヴへの意識を持ち合わせていたと思われる。
そのことを裏付けるように、ファーストアルバム『青春の詩』(‘70)にはボサノヴァの楽曲が2曲収録されている。華美な装飾を除いたソリッドな「灰色の世界I」と、ストリングスを配して歌謡曲的なロマンチシズムも湛えた「雪」。編曲を手がけたのは、デンプシー・ライトに弟子入りし、日本のジャズギタリストの草分け的存在として知られた沢田駿吾である。彼が率いるクインテットが参加したこれらの楽曲、特に「灰色の世界I」は、1970年というリリース年を考えると驚くほど洗練されているように思える。
セカンドアルバム『人間なんて』(‘71)では、ブラスセクションと強力なベースラインが牽引するソウル/R&B調のナンバー「笑えさとりし人ョ」を聴くことができる。演奏を務めたのは、伝説のロックバンドであるジャックスで活躍し、のちにかぐや姫「神田川」などのアレンジでも著名になる木田高介が率いる「木田高介とア・リトル・モア・ヘック」だ。こうした日本のロック黎明期を支えた人材の起用は『伽草子』(‘73)の「からっ風のブルース」でも同様で、柳田ヒロを中心とした演奏陣による激しいファンクロック~サイケデリック調のサウンドが楽しめる。また、この曲にも参加したベーシスト後藤次利は、のちの『ローリング30』(‘78)で煌びやかなファンクナンバー「裏街のマリア」を編曲している。
このファンクロック路線が最良の形で記録されているのが『よしだたくろうLIVE ’73』(‘73)だろう。ブラスやストリングスを従えた、当時の本邦最高峰とも称された本ライブのリズム隊を務めているのは、昨今海外で再評価が進んでいるファンクバンド「稲垣次郎とソウル・メディア」の田中清司(ドラム)、岡沢章(ベース)である。デビューシングル収録曲を超弩級のヘヴィ・ファンクにアップデートした「マークII’73」、ベースラインが光る高速ファンク「君が好き」をはじめ、彼のソウル/R&B的な音楽性の結晶と呼びたい名演揃いだ。
レゲエの奥底に“ソウル”を見出した吉田拓郎

吉田拓郎はボブ・マーリーの「I Shot The Sheriff」をライブで体験した感想として、「あの叫び、あのノリも、黒人のソウルだ。レゲエってリズムの形じゃない。ソウルだと思うね」という言葉を残している。ボブ・マーリーが来日した1979年は日本でもレゲエを取り入れたアレンジが流行しつつあったが、吉田はそうした日本化されたレゲエとは一線を画す魅力を感じ、のめり込んでいったと言われている(「平凡パンチ」昭和55年4月28日号より/平凡出版)
このレゲエへの思いが最初に作品に現れたのが、彼にとって初の海外レコーディング(ロサンゼルス)となった『Shangri-La』(‘80)である。
同作は、前述の米軍基地での演奏でもカバーしていたという憧れの人物、ブッカー・T・ジョーンズをプロデューサー兼アレンジャーに起用し、スタジオ・ミュージシャンには元ザ・バンドのガース・ハドソン等が参加。アルバムタイトルも、解散前のザ・バンドが愛用していたことでも有名なロサンゼルス郊外マリブのスタジオ「Shangri-La Studios」から取られている。結果として、ロサンゼルスという土地柄から連想される当時の爽やかなウェストコースト・サウンドとは一線を画す、アーシーでいぶし銀のサウンドが楽しめる名作となった。
中でもレゲエの影響が分かりやすく表出した楽曲としては、シングルカットもされたアップテンポの「いつか夜の雨が」、より重厚なグルーヴを持った「ハネムーンへ」が挙げられる。
ブッカーとの交流はアルバム完成後も続く。彼はリリース同年の吉田の日本武道館公演にも参加しており、翌年のアルバム『アジアの片隅で』(‘81)のタイトル曲は、この公演のライブテイクが収録されている。ブッカーも参加した12分を超える演奏の中で、岡本おさみ作詞の強烈な社会批評を繰り広げているが、数十年を経た現代の日本にも通じるメッセージを叫ぶ吉田の熱量は、彼がボブ・マーリーのステージから感じたという「ソウル(魂)」にまさしく通ずるものだろう。
ここまで、駆け足でデビュー期~1981年までの彼のリリースを、グルーヴを感じさせるアレンジの観点から振り返ってきた。ここで重要なのは、彼が表層的な編曲を取り入れるだけでなく、自身のメッセージや熱量をいかに込めるかという命題を持ち続けたことだろう。彼が長きに渡り多くのファンに愛され続けたのは、その一本筋が通った楽曲制作へのアティチュードゆえではないか。そしてこの姿勢こそ、さまざまなジャンル~テイストを取り入れた楽曲制作が非常に簡易になった現代において、ひときわ学ぶべき重要な姿勢に思えてならない。


 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します













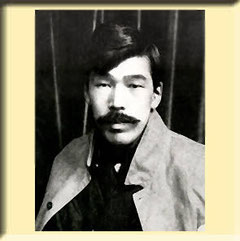














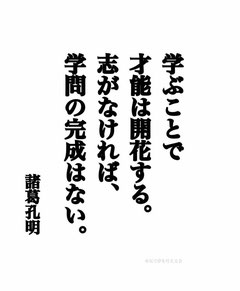

コメントをお書きください