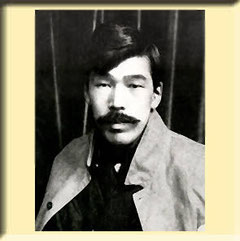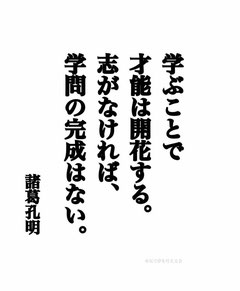准尉は、軍人らしからぬ人でした。
理想の上司、誠実な夫。
しかし、今から78年前の8月18日、終戦3日後のこと。
妻と生後間もないわが子とともに、命を絶ちました。
「我れにその力すでになし」
遺書には、悲劇の理由が記されていました。
(長野局記者 長山尚史)
ある一家の死
山の斜面を少し登ったところに、その名前は刻まれていました。遊佐卯之助 准尉 (ゆさ・うのすけ)」
遊佐卯之助 准尉
終戦から3日後の1945年8月18日。
“理想の上司” 遊佐准尉は殴らない
遊佐准尉はいったいどんな人物だったのでしょうか。
おいの森田敏彦さん 遊佐准尉は殴らない 』と有名だったそうです。しかも、殴らないからといって、教え子の腕が悪くなるわけではない。Aくんにあった教え方、Bくんにあった教え方をしていた。今の時代なら、理想の会社の上司だったと思います」
死の真相を探る人物
8月上旬、森田さんを訪ねたとき、私(記者)は村山隆さん(76)と一緒でした。
遊佐准尉を調べている村山隆さん
多くの関係者から話を聞いたり、資料を集めたり。
上田飛行場
遊佐准尉は昭和15年に教育隊に赴任し、少年飛行兵の指導にあたっていました。
約束と愛
これまでに、遊佐准尉の教え子たちの証言なども調べてきた村山さん。
村山さん 自分もあとで必ず逝く、君たちだけを死なすことはしない 』と話していました。結果的に生き残ったが、教え子たちとの約束に殉じたのではないでしょうか」
けれど、優しく誠実であった夫がなぜ、妻と幼子と死をともにしたのか。
野村信子さん
村山さんはこの日、秀子さんが両親にあてて書いた遺書を持ってきました。調査の過程で見つかり、預かったものでした。
「本当に泣ききれないくやしさ
戦わずして死す身の悲しき 卯之助と共に久子と共に参ります」
実は遊佐准尉は、みずからも特攻隊員として戦地に赴くことを志願していました。戦わずして死す身の悲しき卯之助と共に 」
遺書を読んだ信子さんは、姉にまつわる1つのエピソードを明かしつつ、一家でともに命を絶った理由を次のように推測しました。
秀子さんの妹・信子さん
「我れにその力すでになし」
3人が命を絶った現場には、遊佐准尉の手帳が落ちていました。
「決して血迷ったのでもなければ
皇統三千年の歴史を失ひて 今後の建設ちょう大なる事業はあれ共
我れにその力すでになし 」
従来の価値観が崩れ去り、焼け野原を見た遊佐准尉。
村山さん
戦後日本の姿を見ることなく、命を絶った一家の悲劇。
村山さん
8月18日、村山さんたちは慰霊碑の前にいました。
3人の命日である毎年8月18日に、この場所で「慰霊の集い」を開いていますが、年々、当時を知る人が少なくなってきました。
ことしは新たに遊佐一家の「慰霊の会」を立ち上げました。若い世代にも事実を伝えていきたいという思いからでした。
この日の集いには、遺族や地域住民など、50人ほどが集まってくれました。
中には、近所に住む女の子も来ていて、こんな言葉を口にしました。
中学生1年生の女の子
誠実さゆえに苦悩した特攻教官と、そんな夫を愛した妻。
“すぐにあの約束を思い出せていれば、母にもう一度会えたかもしれない”
最後の別れ
「母の心尽くしのお弁当を持って家を出たあの日の朝が、最後の別れになるとは、思いもしませんでした」
上田桂子さん
この体験記を書いたのは、94歳の上田桂子さん。
左から兄・父・上田さん・母
上田さんは広島市中心部にある広島女学院に通っていましたが、当時は勤労奉仕として毎日のように軍服や軍靴を製造していた陸軍被服支廠などで作業にあたり、ほとんど授業はなかったといいます。
8月6日の朝。
1945年 8月6日 午前8時15分
この日の勤労奉仕先の会社は、自宅から約3.5キロのところにある東洋工業、現在のマツダでした。
上田桂子さん
気が付くと、上田さんは建物の下敷きになっていました。
火の海になった広島
線路沿いに進んでやっとのことで東洋工業に到着すると、今度は担任の先生から「広島は大変なことになっているから、帰りなさい」と言われました。
猛烈な熱さでとても広島市中心部に入ることはできません。
上田桂子さん
翌朝、まだ火の手が収まらない中心部ではなく、現在の広島市郊外にあった祖母などの親戚が住む疎開先を目指しました。
地獄の中、母を探して
原爆投下から2日たって、母を探しに中心部へ入りました。
立ったまま黒焦げになった牛車を引く男性の死体。
思い出せなかった約束
母を見つけられないまま、1週間ほどたった頃のこと。
“いざというときには饒津神社で会おう”
上田桂子さん
母がいたという東練兵場に急いで向かうと、避難した人の名簿に『伊勢村時子』と母の名前が記されていました。
被爆後の東練兵場
ここに母がいると、喜んだのもつかの間。
上田桂子さん
上田さんの母 伊勢村時子さん
その後、広島に戻ってきた父や兄とともに母を探しましたが、しばらくして遺体もないまま母の葬式をあげました。
上田桂子さん
原爆投下から78年。
戦後も続く被爆の影響
原爆で相次いで広島の親戚を亡くした上田さんは戦後、父方の親戚を頼って県東部の神石高原町に移り住みました。
しかし、戦争から戻ってきた親族と結婚してからも、被爆の影響はつきまとったといいます。
上田桂子さん
結婚してはじめの5年間は流産を繰り返しましたが、4人の子どもに恵まれました。
上田さんと子どもたち
それでも母のことを思うたび、気分が落ち込み、眠れない日もありました。
戦争は、怖い
転機が訪れたのは、10年余り前のこと。
地元の小学校で証言活動をする上田さん
被爆体験を語れる人々が減っていく中で、「つらいことも苦しいこともすべて、自分たちが包み隠さず言うしかない」。
上田桂子さん
2時間近くに及ぶ取材も終わりにさしかかり、上田さんに若者たちに伝えたいメッセージを書いてもらった時のことでした。
『二度と戦争のない時代を作ってほしい 平和に感謝して生きる心を養う』
上田桂子さん
私たちこそが平和を維持していく“当事者”
最初にあいさつしたとき、笑顔のすてきな上田さんから受けた印象は「品の良い優しそうな方」でした。
広島放送局 記者
牧裕美子
意識が戻ると、体は崩れた建物の下。
慰霊碑に刻まれた親友の名
ことし8月。
鈴木郁江さん(95)。
娘と共に神奈川県の自宅から電車や新幹線を乗り継ぎ、4時間余りかけて訪れました。
鈴木郁江さん
はじめて見る十字架の形をした慰霊碑。
鈴木郁江さん
77年前 広島で
77年前のあの日、8月6日。鈴木さんはこの場所にいました。
看護学生時代の鈴木さん
戦争で人手が足りなくなると、病院では学生までもが医療の現場にかり出されました。
死の光
1945年8月6日。
鈴木郁江さん(左)と東シズヱさん(右)
疎開で広島に来ていた東さんとはよく一緒に外出し、東さんとそのお父さんと、食事をしたこともありました。
鈴木郁江さん
“人間の世界じゃない”
どのくらいの時間が経ったかはわかりません。
すると、がれきの隙間から一筋の光が見えました。
鈴木郁江さん
けがの痛みをこらえながら、夜まで東さんを探しましたが見つからず、その後、亡くなっていたと知らされました。
蓋をした記憶 長い年月を経て
戦後は、家族や仕事の都合で広島を離れました。
ビデオで話す鈴木さん
しかし、3年前に転機がおとずれます。
「戦争はとても恐ろしいものなんだと改めて感じました」
子どもたちの文章には、感想だけでなく、鈴木さんに共感しようとする気持ちや、自分も伝えていくという意志を示す言葉もありました。
鈴木郁江さん
ウクライナ情勢 重なる広島で見た光景
そうした中、ロシア軍がウクライナに侵攻を開始。
鈴木郁江さん
“もう立ち止まっていてはいけない”
77年前のあの悲劇を、二度と繰り返してはならない。
女子中学生
鈴木郁江さん
鈴木郁江さん
取材後記
ことしで95歳になった鈴木さん。
広島放送局記者
石川拳太朗 2018年入局
かつて太平洋戦争を敵として戦った2人。
78年前、船は沈んだ
アメリカ中西部のインディアナポリス市で開かれた追悼の集会です。
追悼の集会に集まった「インディアナポリス」の元乗組員の遺族や関係者
7月30日。
上:インディアナポリス 下:伊58
アメリカ海軍の重巡洋艦「インディアナポリス」。
「伊58」“最後の生存者”
愛媛県松前町に住む「伊58」の元乗組員、清積勲四郎さん(95)です。
清積勲四郎さん
海軍の学校の卒業写真
尋常小学校を卒業後、陸軍を経て海軍に入隊した清積さん。
清積勲四郎さん
当時16歳。「伊58」の100人近くいた乗組員のうち最年少だったと言います。
発射した魚雷は命中し、船はごう音とともに炎を上げて、7月30日の深夜、海に消えていきました。
1200人近くの乗組員の大半が犠牲となりました。
戦後、清積さんは愛媛に帰り民間企業で定年まで働きました。
もう1人の“最後の生存者”
ことし6月、清積さんの元を1人の女性が訪ねてきました。
左:ハリス田川泉さん
田川さんは偶然目にした新聞記事で清積さんのことを知りました。
親愛なる清積さんへ
清積勲四郎さん
ハロルド・ブレイさん
手紙を書いたハロルド・ブレイさん(96)です。
ハリス田川泉さん
田川さんが届けた手紙は合わせて5通。
親愛なる清積勲四郎様
78年たって伝える思い
この数日後、清積さんはハロルドさんたちに返事を書きました。
返事を書く清積さん
一文字一文字、自分の思いを丁寧に書きつづった清積さん。
親愛なるハロルド・ブレイ様 (※一部抜粋)
海を越えて届けられた手紙
清積さんの手紙は田川さんがアメリカに持ち帰り、追悼の集会で読み上げられました。
追悼集会で読み上げられた清積さんの手紙
集会には元乗組員の家族も多く出席しました。
貴方の様な若い方が平和を願いながら遠い異国に住む一老人に心をかけて下さる事に感謝しております。
マイケル・ウィリアム・エモリーさん
出席者から現地の映像を提供してもらい、私は集会の様子や出席者の反応を清積さんに伝えました。
清積勲四郎さん
“美談で終わらせてはいけない”生存者どうしの交流
取材を通じて、ハロルドさんの写真を優しい目で見つめる一方で「戦争は絶対にしてはいけない」と繰り返し話す清積さんの意志の強いまなざしが印象的でした。
戦争がなければ憎み合うこともなかった2人。
松山放送局 記者
木村 京
20万人を超える人たちが亡くなった沖縄戦。
元少年兵の濱崎清昌さん
「腹の中に破片が2つ入っているよ。何十年もケロイドが残っていた」
太平洋戦争中の昭和19年4月。
5日後の31日。濱崎さんは当時の学生たちで構成された「鉄血勤皇隊」と呼ばれる部隊に動員され、旧日本軍を指揮した第32軍司令部の管理下に置かれることになりました。
濱崎清昌さん
しかし、濱崎さんはその後、圧倒的な戦力の差があることを思い知ることになります。
沖縄での地上戦の様子
4月1日。アメリカ軍は沖縄本島中部に上陸し、本格的な地上戦が始まりました。
濱崎清昌さん
司令部壕の内部
アメリカ軍の激しい攻撃にさらされる中、少年兵たちは司令部壕内にたびたび招かれ、将校から「日本が勝っている」という話を聞かされていたといいます。濱崎さんはそのことばを信じ切っていました。
濱崎清昌さん
しかし、連合艦隊が来ることはありませんでした。
濱崎さんも仲間たちとともに司令部が移された本島南端の糸満市摩文仁に向かいましたが、たどりついたその場所で、死と隣り合わせの極限状態に追い込まれていきます。
「鉄の棒か何かで頭や体を殴られたような感じで、僕もばったり倒れたわけさ。雨あられみたいに血が流れて、頭がやられているわけよ。足は足で動けない。弾が耳の近くをピュシュってする時に目が覚めるけど、だんだん意識がもうろうとしてくるわけ」
意識が薄れつつある中、一緒にいた同級生のことが心配になり、何度も名前を呼びましたが返事はありませんでした。
近くの穴に転がってそのまま意識を失ったという濱崎さん。
濱崎清昌さん
「アメリカ軍の捕虜になったら殺されるか、一生奴隷にされるかどちらかだ」と教え込まれてきた濱崎さん。
沖縄戦から77年がたち濱崎さんは足腰が弱まり、自宅で過ごす時間が多くなりました。
濱崎清昌さん
「昔は統一してこれはだめ、はい右向け右、左向け左で上の言うことしかやらなかった。自分の国の政治家やそういう人たちが何を言ってるか。自分は本当にだまされてないか。本当に自分の国のために、この人は政治をやっているか。そういうものもよく見る必要があるんじゃないか。ただうのみにするんじゃなくて」
軍国少年だった過去を振り返り発せられた濱崎さんの物事の本質を見極めるということばは、私(記者)の心に重く響きました。
“司令部壕” 公開に向けて
沖縄では濱崎さんのような戦争体験者から直接話を聞くことが難しくなっています。県内のシンクタンクの調査によると、戦前や戦時中に生まれた世代が総人口に占める割合は、1割を下回っているとみられています。
司令部壕 保存公開の県の検討会
こうした中、県民の間で記憶を継承するための重要な戦争遺跡として第32軍司令部壕を活用していこうと、保存・公開に向けた機運が高まっています。県も今年度、関連予算として5000万円を計上し、司令部壕の一部について令和7年度中の公開を目指す考えを明らかにしました。
沖縄放送局記者
安座間マナ
広島で被爆した少年がたくましく生き抜く姿を描いた漫画「はだしのゲン」。
6歳のとき、広島に投下された原爆によって被爆した漫画家、中沢啓治さん。
ロシア語版の翻訳者 浅妻南海江さん
金沢市の浅妻南海江さん(80)は、学生のころから学んでいたロシア語を生かし、1994年から7年かけて「はだしのゲン」全10巻をロシア語に翻訳した。
ロシア語版の翻訳者 浅妻南海江さん
海外の人にも原爆のことを知ってもらいたい。
地域に住むロシアからの留学生たちと一緒に翻訳作業に取り組み、完成した漫画を海外の学校や図書館などへ寄贈する活動も行ってきた。
ウクライナからの感想
核大国であるロシアの人たちも、この漫画を通して、核兵器による被害を自分事として受け止めているようだった。
ロシアからの感想
ロシアからの感想
ロシア語版の「はだしのゲン」
自分が翻訳した漫画を通して、海外の人たちが原爆による悲劇を知り、同じことを二度と繰り返してはいけないと感じてもらえた。
平和の種まきをしても… そのロシアが軍事侵攻
しかし、浅妻さんが翻訳をし、作品を広めようとしていた国、ロシアは去年2月、ウクライナへ軍事侵攻を始めた。
浅妻南海江さん
漫画で戦った中沢さん
「はだしのゲン」の作者、中沢啓治さんは1961年、漫画家になることを夢見て上京した。東京に住んでからは、被爆者に対して差別や偏見を持つ人たちからの冷たい視線がいやになり、原爆のことは二度と話さないと決心していた。
中沢啓治さん (2005年放送)
妻のミサヨさんによると、葬儀のあと、広島から東京に帰る列車の中で、中沢さんはひと言も話さずじっと考え込んでいたという。
“草の根で翻訳広がる” 国境を越えたメッセージ
中沢さんの覚悟、戦争への怒り、平和への願いが詰まったこの漫画を読んでもらいたいと、浅妻さんはロシア語版を完成させた。
浅妻さんは、ロシア語版のために苦労して独自に制作したセリフ部分が空白のデータを提供するなど活動を後押しした。
浅妻南海江さん
浅妻さんと中沢さん
「はだしのゲン」が次々と外国語に翻訳され、世界に広がって行くことを、中沢さんはとても喜んでいたという。
浅妻南海江さん
浅妻さんは、仲間とともに「はだしのゲン」を広げるためのNPO法人を立ち上げた。
中沢さんからの手紙
連載が始まってことしで50年となる「はだしのゲン」。
ロシア語版の翻訳者 浅妻南海江さん
広島放送局 記者
石川拳太朗
始まりは父親の遺品から見つかったマフラーだった。
「振武隊特別攻撃隊 天翔隊」の文字が…
大阪市に住む建築士の山本一清さん(74)は、父親琢郎さんから戦争の話は一切聞いたことがなかったという。
山本一清さん
そんな父親は18年前に死去。
山本一清さん
父の経歴には空白の2年間
さらに名古屋市に住む妹が、父親の経歴が記された書類を保管していたことがわかった。
父の経歴が書かれた書類
しかし、戦時中の部分は
短期間の訓練で特攻隊員に
まず、山本さんは父親や部隊の名前を手がかりにインターネットで調べた。
サイトの運営者に問い合わせると、特別操縦見習士官=特操出身の隊員たちが寄稿する会報などの存在も判明。
山本一清さん
父は”遺書”を残していた
さらに調査を進めると、佐賀県吉野ヶ里町の「西往寺」という寺で父親が終戦間際まで過ごしていたことが分かった。
西往寺
寺によると、戦時中、ここは出撃する直前の特攻隊員たちの宿舎となっていて、53人の若者が戦地へ向かったという。
父が書いた言葉
そこに記されていたのは「後に続くを信ず」という言葉。
父の短歌
先に出撃した仲間たちを思い、自分もその後に続いていくという覚悟がつづられていた。
山本一清さん
少女に贈った父の自画像
この寺で、山本さんは父親の意外な一面も知ることになった。
父の書いたはがき
持ち主は、伊藤玲子さん(92)
伊藤玲子さん
父の写真
2人のやり取りから見えてきたのは、厳格だった父親とは異なる、やさしい、普通の青年の姿だった。
父は死に場所を求めていた
父親は戦後、知り合いを頼って移り住んだ長野県で山本さんの母親の洋子さんと出会って結婚。
父と母の結婚式
父親の足跡を調べる中、山本さんは、改めて母親の手記を読み進めたところ、戦後の父親の状況を記したページを見つけた。
「九州の基地で飛行訓練中に部下が墜落して亡くなった。翌日がくしくも敗戦宣言だったという。部下の死を目にして無念と責任感が錯綜し基地の周りの山野に死に場所を求めたという」
生き残ったこと自体が命を失った仲間たちを、そしてあの頃の自分を否定することになるとして、口を閉ざしたのかもしれない。山本さんはそう推測している。
山本一清さん
空白の2年を埋める旅を終えた山本さん。
World News部
天皇陛下は、体をクルリと向けて遺族の言葉に耳を澄ませた 戦争を知らない皇室の「祈り」の今後 © AERA
dot. 提供
終戦から78年となった8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が、東京都の日本武道館で開かれた。天皇陛下の「おことば」は、社会の情勢の変化を反映させつつ、これまでと変わらぬ平和への祈りと不戦の誓いが込められた。しかし、天皇陛下や皇后雅子さまもふくめ、皇室でも戦争を体験していない世代が増えている。上皇ご夫妻が始めた「慰霊の旅」、そして皇室の「祈り」の今後は――。
* * *
「『平和』の言葉を前に持ってきた。こまかな変化ですが、天皇陛下からのメッセージでは」
そう話すのは、象徴天皇制を研究する名古屋大の河西秀哉准教授だ。ロシアによるウクライナ侵攻など、世界情勢が落ち着いていない状況を指しているのだろうと分析する。
式典における天皇と皇后の滞在時間は、30分程度と長くはない。「おことば」も毎年ほぼ同じだが、社会情勢などを鑑みて、表現にわずかな変化が出る。
全国戦没者追悼式は政府が主催し、戦後7年の1952年に初めて、昭和天皇と香淳皇后を迎えて新宿御苑で開かれた。このときの昭和天皇による「おことば」は、戦争でもたらされた苦しみや悲しみの渦中に人々がまだいることが伝わるものだった。
「今次の相つぐ戦乱のため、戦陣に死し、職域に殉じ、また非命にたおれたものは、挙げて数うべくもない。衷心その人々を悼み、その遺族を想うて、常に憂心やくが如きものがある。本日この式に臨み、これを思い彼を想うて、哀傷の念新たなるを覚え、ここに厚く追悼の意を表する」
59年に2回目、63年の3回目以降、定期的に開催される国の行事となった。
1980年、天皇の「おことば」に変化が起きた。さまざまな式典などで述べられる天皇の「おことば」のうち、全国戦没者追悼式だけが唯一「である」調のままだったが、「です」「ます」調に変わったのだ。
「威圧的だ」という声の一方で「威厳がある」との意見もあり、宮内庁としても議論の末の決断だった。
そして平成へと移った89年の式典でも、「おことば」に変化が起きた。
昭和天皇が「終戦以来すでに41年、この間、国民の努力により国運の進展……」としていた表現が、「終戦以来すでに44年、国民のたゆみない努力によって築きあげられた今日の平和と繁栄」と改められた。また、昭和天皇が「今もなお、胸がいたみます」としていた表現が、人々に寄り添う「深い悲しみを新たにいたします」という言葉になった。
天皇陛下は、体をクルリと向けて遺族の言葉に耳を澄ませた 戦争を知らない皇室の「祈り」の今後 © AERA
dot. 提供
■「サイパンならばどうか」と上皇さま
小さく見えた変化は、上皇さまの強い決意の表れであり、戦争の犠牲者のために祈り、平和を希求する「慰霊の旅」を実現させる布石だった。
戦後50年にあたる95年、上皇ご夫妻の「慰霊の旅」が始まった。
おふたりは、長崎、広島、沖縄、東京大空襲の慰霊施設を訪問。さらに上皇さまは、激戦地のマーシャル諸島やミクロネシア連邦、パラオへの訪問を希望していると、当時の渡辺允侍従長へ伝えた。
交通手段や宿泊施設の問題から断念することになったが、それでも「慰霊の旅」への思いは強かった。
「では、サイパンならばどうか」
戦後60年の節目である2005年にサイパン、さらに10年を経て15年のパラオ訪問へとつながった。
天皇陛下は、体をクルリと向けて遺族の言葉に耳を澄ませた 戦争を知らない皇室の「祈り」の今後 © AERA
dot. 提供
太平洋戦争では1944年7月にサイパン、8月にグアムの守備隊が玉砕すると、米軍の攻撃目標はパラオ本島から南へ40キロに位置するペリリュー島へ。日米両軍の戦死者は1万2千人以上に及んだという。
ペリリュー島を訪れた上皇ご夫妻は、戦没者の碑に日本から持ってきた菊の花を捧げた。そして、海に浮かぶもう一つの激戦地、アンガウル島のほうへ歩を進めた。
「あそこね」
上皇さまが美智子さまに声をかける。静かに顔を見合わせ、島へ一礼した。
このときの情景を、上皇さまは和歌に詠んでいる。
《戦ひにあまたの人の失せしとふ島緑にて海に横たふ》
天皇陛下は、体をクルリと向けて遺族の言葉に耳を澄ませた 戦争を知らない皇室の「祈り」の今後 © AERA
dot. 提供
翌2016年の「慰霊の旅」は、フィリピンへ。フィリピン側の死者は110万人以上、日本側は50万人以上にのぼり、いまだ帰らぬ遺骨は30万人以上に及ぶ。
皇室医務主管を務めた故・金沢一郎氏は、かつて筆者にこう語った。
「昭和の惨劇で、命を落とした人々への鎮魂は、両陛下にとって生涯を通じた仕事なのでしょう」
■佳子さまが引き継いだ「祈り」
19年に令和の天皇陛下へと代替わりが行われた。皇室も高齢化が進み、式典で祈りを捧げる役目は、戦争を体験していない世代に引き継がれた。
天皇陛下は、体をクルリと向けて遺族の言葉に耳を澄ませた 戦争を知らない皇室の「祈り」の今後 © AERA
dot. 提供
先の大戦中に戦地で亡くなった身元不明の戦没者らを慰霊する千鳥ケ淵戦没者墓苑での秋季慰霊祭や拝礼式などは秋篠宮ご夫妻が引き継ぎ、今年は初めて次女・佳子さまが5月の拝礼式へ参列した。
出席した遺族からは、佳子さまが「祈り」を引き継ぐことに「嬉しい」といった感想が漏れた。一方で献花もなく、黙礼をして10分ほどで退場する流れに、さみしさを感じた遺族もいた。
そして8月15日の「終戦の日」の全国戦没者追悼式に出席した天皇陛下と皇后雅子さまも、戦争の実体験がない世代だ。
式典で、父親がソロモン諸島で戦死した尾辻秀久参議院議長は「参議院議長として、遺族の一人として、ここに立たせていただく」と前置きして、
「私たちは焼け野原の中、おなかを空かせて大きくなりました。一度でいいからおなかいっぱいご飯を食べたいと思っていました」
「私たちは、生きるか死ぬかという中を肩を寄せ合って生き抜いて参りました」
そう、自身の体験を交えながら追悼の辞を読み上げた。
中国で父親が戦死した遺族代表の横田輝雄さんは、ロシアによるウクライナ侵攻に触れ、こう訴えた。
「現地の惨状を目の当たりにするにつけ、かつての戦争を思い出さずにはいられません」
遺族たちが標柱の前に立つたびに、天皇陛下はクルリと体を向けて、追悼の辞に耳を傾けた。雅子さまも標柱と遺族らを見つめていた。この日、愛子さまも御所で黙とうを捧げていた。
■「慰霊の旅」は終わっていない
2年後には、戦後80年の節目を迎える。戦争の悲惨さを知る世代が表舞台から去り、次世代への歴史の継承は大きな課題となっている。
先の河西准教授は、皇室の「慰霊の旅」はまだ終わっていない、と話す。
「戦争を肌で知らない皇室の方々が、慰霊に向き合うのは難しいことです。戦争の犠牲者の魂と平和の希求のために祈りを捧げるとき、それが『儀式をなぞる作業になっていないだろうか』『内実を伴うものになっているだろうか』と、常に自問をする覚悟が必要だと思います。
戦争を知らない天皇、そして皇后、皇族方が慰霊を行う意味とは何か。それは、皇室自身、そして私たちが考えなければならない課題ではないでしょうか」
(AERA dot.編集部・永井貴子)

 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します