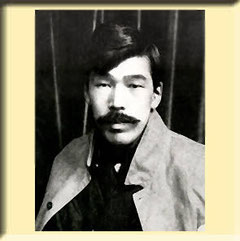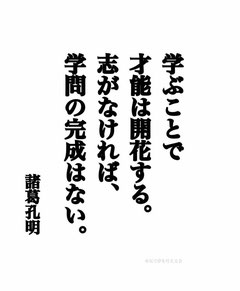【世界平和】人類はみんな家族!! Apex product ⑥
SDGsの目標16『平和と公正を全ての人に』
平和都市宣言
平和な日々を過ごすことは、全人類の共通の願いです。我が国の経済発展とともに本市は成長し、今日、全国でも有数の大都市に発展しました。こうした繁栄は、平和がもたらしたものであるといっても過言ではありません。
1989年(平成元年)2月28日、千葉市は世界の恒久平和を願い、「平和都市」を宣言しました。
平和都市宣言
|
平和都市宣言 |
「ちばSDGsパートナー」登録企業 Apex product
目標16のポイント
- みんなが安心して参加できる平和な社会をつくる
- 公正な法律に基づいた暮らしをみんなができる
- 地域・国・世界といったあらゆるレベルで公正な司法制度を利用できる
平和な社会づくりのため、世界中から、虐待、搾取、人身売買など、子どもに対する暴力を含む、あらゆる暴力と暴力による死を大幅になくすこと、政府や国の制度を公正にし、すべての人が平等に司法を利用することを目指す目標です。
違法な資金の取引や武器の取引、汚職を大幅に減らすこと、子どもや若者を含む人々の意見を意思決定に反映し、人々に対して情報を公開して説明ができる政府や制度にすることもこの目標に含まれます。また、グローバルなレベルでの決定に際し、途上国の参加を拡大、強化していくことも目指します。
SDGsの17番目の目標は、これまでの16の目標を達成するために、「具体的な実施手段を強化し、持続可能な開発に向けて世界の国々が協力すること」に関連するとても重要な目標です。
すべての国が目標達成に向けて国の予算を確保し、また先進国は途上国に必要な資金や技術を支援し、国同士の格差を生まない貿易ルールを実施することが掲げられています。
さまざまなステークホルダー(関係者)が連携することや、目標達成に向けてどのくらい進捗しているかを確認するため、データや統計をきちんと集めることもこの目標に含まれています。

争いは、やめましょう。世界の平和を願います!!
何故、今だに世界の至る所で揉め事や争いごとが絶えないのでしょう。政治や宗教での自国間の争い、差別、派閥、どうして起こるのですか。アジアの仲間同士どうして普通に暮らせないのですか。誰が、考えても平和な社会が良いに決まっています。小さな子供でも理解出来る事を分別のある大人や政治家が、何故、争うのでしょう。人は何故争わなければいけないのでしょう。欲を捨て本来の裸で生まれた人間同士うまくやっていけないのでしょうか。それぞれ、己が正義と思い事を成すでしょうが、少しだけ立ち止まり、力を抜いて音楽を聴いてみてはいかがですか。きっと心に響く1曲があるはずです。そして貴方の幼い頃。そうです。純粋だったあの頃。思い出して下さい。人前に出るのもおどおどして、母親の影に隠れていた優しい子。正義の旗の元、どんな理由があっても人殺しです。無差別に殺しあう戦争が、どんなに愚かな事でしょう。本来のあなたに戻って下さい。きっと戻れます。先人がどれだけ血を流し我々に生きて伝えたかった事でしょう。だからだから、お願い致します。下記に、あげる資料・画像を見て一人でも多くの人に伝えて下さい。いかに、平和が大切で、人の命が尊いのか。本気で考えて下さい。弊社は、真剣に取り組みます。誰に非難されても、私達は訴え続けます。一生を掛けて取り組む問題だからです。是非ご賛同頂き、少しでも悲しい人を作らないようにしましょう。
平和ほど、尊いものはない。
平和ほど、幸福なものはない。
平和こそ、人類の進むべき、
根本の第一歩であらねばならない。
【あたりまえ】
あたりまえの幸せが
ほんとはあたりまえなんかじゃなく
生きてることさえ、あたりまえじゃない!
明日があることがどんなに幸せなことか
だいすきな仕事ができる身体と心も
環境があることがどんなに幸せなことか
ちょっと疲れたら横になれる
ふかふかなベッドがあることがどんなに幸せなことか
朝起きたら、心臓が動いてて
伸びをして、深呼吸して
朝日を浴びることが
どんなに幸せなことか
何をするにも、必ず誰かの助けや支えがあることが
どーんなに幸せなことなのか。
とっくに気づいてるはずなのに
いちばん大切なことはおろそかにしがちなんだよね。
ほんとは
世界は地球は
もっともっと、愛にあふれてるんじゃないのかな
- 青空と向日葵の会 Apex product 社員一同 -


日本は戦争に負けたが、素晴らしい憲法が生まれた
..... 軍国少年だった僕の夢は、海軍兵学校を出てパイロットになり天皇のために名誉の戦死を遂げることでした。しかし、敗戦によって夢は打ち砕かれました。
一学期までは先生から「これは聖戦だ」と教えられていたのに、二学期からは(あの戦争は間違いだった)と言われ、訳がわか...らなかった。「もう大人の言うことは信用しないぞ)と心に刻みました。あれがジャーナリストを目指した原点になったのかもしれません。
..... 子供が自由に夢を抱けるのは幸せなことです。戦争だとこうはいきません。孫達には平和を作る人になってほしい。いったん戦争への流れができると、天皇だって反対できません。「正義のための戦争」という言葉ほど信用出来ないものはありません。
日本は戦争に負けたが、素晴らしい憲法が生まれた。
(20150705東京新聞)

19歳、夏、ススキノ、フリータ女子、高塚愛鳥(まお)、起つ。
「
戦争、したくなくて震える
」...
(北海道新聞 6月23日)
SEALDSの10代20代の若年層の抗議行動、デモが話題となっている中、呼応するようにこういう若い人の動きが出てきた。
「
戦争は怖い、イヤだと思いつつ、デモでは何も変わらないと思っていた。
友達と街を歩いてデモと出くわしても「うるさい」と思った。
それでも、もし戦争になったら駆り出されるのは自分たちの世代。無関心で遊んでばかりいていいのか―。少しずつ考え始めた。
」
デモは、ウルサイ、うざい、鬱陶しい、何も変わらない。
そう思っていた19歳女子は、ススキノの飲食店でバイトしていた。
「
19歳、フリーター。音楽とおしゃれが好きで、政治には関心がなかった。そんな女の子が発起人となって26日、安全保障関連法案に反対するデモが札幌で行われる。呼びかけたのは札幌市中央区の高塚愛鳥(まお)さん。「戦争は怖い。イヤだ。許せない。むかつく…。若い世代が自分たちの言葉で反対の声を上げたい」と力を込める。
」
デモの名は「戦争したくなくてふるえる」。
若者に人気の歌手
【西野カナさんの曲の「会いたくて震える」】
という歌詞にかけた。
<戦争が始まったら自由が奪われる。
バカな政治家たちに自由で楽しいあたし達の暮らしを奪われてたまるか!>。
インターネット上のデモの告知には、
自身の写真とともにそんなメッセージを載せた。
北海道、19歳、ススキノ、女子。
これはもう、最後の聖戦ではないか。
日本人全員が、それぞれのスタンスで、
<戦争が始まったら自由が奪われる。
バカな政治家たちにあたし達の暮らしを奪われてたまるか!>
と気付き始めている。
まだ気づいていないとすれば、あなたは、聞いてみると良い。
「
デモは許可が必要と知り、翌日、警察署に申請した。
」
なぜそんなことをするのか? と。答えは単純明快だ。
「
「だって、自分たちの未来にかかわる問題なんだから」
」
リスクはどちらも、重篤だが、アベシは放射能と違って、
見える、し、聞こえるし、何より、クサい。
戦争とアベシを入れ替えてみよう。
「「アベシはイヤだ。許せない。むかつく…。
若い世代が自分たちの言葉で反対の声を上げたい」と力を込める。」
一般女性に嫌われ(女性セブン嫌いな男性第1位)、戦争を知る世代、OBたちから嫌われ、若い世代に嫌われ・・・
働き盛りの男性は、アベシが大好き、なのだろうか・・・。
なぜか一番愚かな層は、放射能でも、アベシでも、感受性の飛び抜けて鈍い、このゾーンだ。
===============
後半全文:
「
19歳フリーター、デモ初企画 戦争怖くてふるえる 26日札幌
北海道新聞 6月23日(火)10時2分配信
中学時代、熱心な教師の影響で貧しいアフリカの子供を助ける仕事がしたいと夢見た。でも、高校時代は茶髪にピアス、短いスカートで、遊んでばかりいた。
「車いすの人権活動家」介助
昨年、半年で大学を中退し、札幌ススキノの飲食店などで働いた。今春、語学留学したフィリピンでは児童養護施設で子供たちと遊ぶボランティアをした。全盲の父は娘の顔を見たことがなく、子供のころはよく顔をさすってくれた。そのせいか、人と触れ合う仕事がしたいと、今は「車いすの人権活動家」として知られる安積遊歩(あさか・ゆうほ)さん(59)=札幌市西区=を介助するアルバイトをしている。
戦争は怖い、イヤだと思いつつ、デモでは何も変わらないと思っていた。友達と街を歩いてデモと出くわしても「うるさい」と思った。それでも、もし戦争になったら駆り出されるのは自分たちの世代。無関心で遊んでばかりいていいのか―。少しずつ考え始めた。
今月中旬、若者が「円山公園」でデモをすると知った。(札幌の)円山なら行こうかなと思ったら、京都の円山だった。その話を安積さんにすると、だったら自分でしたらいいと言われた。「誰かがやんなきゃ誰もしない、何も変わらない」。その日のうちに安保法案についてネットで調べ、若い友人たちにデモの企画をネットでぶち上げた。
行動力には自信がある。デモは許可が必要と知り、翌日、警察署に申請した。遊び仲間や大学生らに共感の輪が広がり、ネットの交流サイト、フェイスブックではデモへの「いいね!」が5日間で千を超えた。
ススキノまで行進
デモは26日午後5時半に大通西8丁目集合。ススキノまで行進する。事前申し込みなしで誰でも参加できるが、特に若い人たちに来てほしいと願っている。「ススキノで遊んでる友達とか、飲み会サークルの大学生とか、あんまり関心なさそうな若者にこそ法案の怖さを知ってほしい。反対の声を伝えたい」と話す。「だって、自分たちの未来にかかわる問題なんだから」
」
Source: 19歳フリータ、デモ初企画「戦争怖くてふるえる」26日札幌
http://headlines.yahoo.co.jp/hl…
【写真】19歳、夏、ススキノ、フリータ女子、高塚愛鳥、起つ。
(北海道新聞)

憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を可能にすることを盛り込んだ安全保障関連法案に反対する集会に、作家の瀬戸内寂聴さんが車いすで登場したが、立ち上がって「良い戦争はない。戦争はすべて人殺しです。二度と起こしてはならない」「最近の日本の情勢を見ると、怖い戦争にどんどん近づいているような気がする」と訴えました。
集会は、午後6時半から国会前で始まり、作家の瀬戸内寂聴さんが参加しました。
93歳となる瀬戸内さんは、集会で、「去年、病気になったが、最近のこの状態に寝ていられないほど心を痛めた。戦争の真っただ中に青春を過ごし、戦争がいかにひどくて大変なものか、身にしみて感じている。最近の日本の情勢を見ると、怖い戦争にどんどん近づいているような気がする」と訴えました。
集会には、主催者の発表でおよそ2000人が集まり、参加した人たちは、「憲法9条を壊すな」とか「戦争させない」などと訴えていました。
このうち、川崎市の32歳の女性は、「政府は法案について十分に説明をしていない。将来の世代に関わる問題なので反対の声にも耳を傾けてほしい」と話していました。
また、17歳の男子高校生は、「政府には、私たちが理解できるように説明してほしい」と話していました。
「殺すなかれ、殺させるなかれという言葉は大事」
国会前で、安全保障関連法案に反対する集会に参加した作家の瀬戸内寂聴さんは、報道陣の取材に対し、「今また戦争が起こりそうな気がしてならない。昭和16年から17年ごろの、表向きは平和だが、すぐ後ろに軍靴の音が聞こえていた雰囲気に似てきているように感じる」と指摘しました。
そのうえで、「殺すなかれ、殺させるなかれということばはいちばん大事なことだ。私の最後の力を出して法案に反対の行動を起こそうと思った。安倍総理大臣には、本当に国民の幸せのためになることを考えてほしい」と述べました。
『希望の同盟へ』米国連邦議会上下両院合同会議 安倍総理演説-平成27年4月29日
米国連邦議会の上下両院合同会議において演説を行いました。歴代の日本の総理大臣として初めてのことです。
是非多くの方にご覧いただきたいと思います。
【 安倍首相米議会演説 全文 】

私個人とアメリカとの出会いは、カリフォルニアで過ごした学生時代にさかのぼります。家に住まわせてくれたのは、キャサリン・デル・フランシア夫人、寡婦でした。亡くした夫のことを、いつもこう言いました、「ゲイリー・クーパーより男前だったのよ」と。心から信じていたようです。ギャラリーに、私の妻、昭恵がいます。彼女が日頃、私のことをどう言っているのかはあえて聞かないことにします。デル・フランシア夫人のイタリア料理は、世界一。彼女の明るさと親切は、たくさんの人をひきつけました。その人たちがなんと多様なこと。「アメリカは、すごい国だ」。驚いたものです。のち、鉄鋼メーカーに就職した私は、ニューヨーク勤務の機会を与えられました。上下関係にとらわれない実力主義。地位や長幼の差に関わりなく意見を戦わせ、正しい見方なら躊躇なく採用する。――この文化に毒されたのか、やがて政治家になったら、先輩大物議員たちに、アベは生意気だとずいぶん言われました。
私の名字ですが、「エイブ」ではありません。アメリカの方に時たまそう呼ばれると、悪い気はしません。民主主義の基礎を、日本人は、近代化を始めてこのかた、ゲティスバーグ演説の有名な一節に求めてきたからです。農民大工の息子が大統領になれる――、そういう国があることは、19世紀後半の日本を、民主主義に開眼させました。日本にとって、アメリカとの出会いとは、すなわち民主主義との遭遇でした。出会いは150年以上前にさかのぼり、年季を経ています。
先刻私は、第二次大戦メモリアルを訪れました。神殿を思わせる、静謐な場所でした。耳朶を打つのは、噴水の、水の砕ける音ばかり。一角にフリーダム・ウォールというものがあって、壁面には金色の、4000個を超す星が埋め込まれている。その星の一つ、ひとつが、倒れた兵士100人分の命を表すと聞いたときに、私を戦慄が襲いました。金色(こんじき)の星は、自由を守った代償として、誇りのシンボルに違いありません。しかしそこには、さもなければ幸福な人生を送っただろうアメリカの若者の、痛み、悲しみが宿っている。家族への愛も。真珠湾、バターン・コレヒドール、珊瑚海…、メモリアルに刻まれた戦場の名が心をよぎり、私はアメリカの若者の、失われた夢、未来を思いました。歴史とは実に取り返しのつかない、苛烈なものです。私は深い悔悟を胸に、しばしその場に立って、黙祷を捧げました。親愛なる、友人の皆さん、日本国と、日本国民を代表し、先の戦争に斃れた米国の人々の魂に、深い一礼を捧げます。とこしえの、哀悼を捧げます。
みなさま、いまギャラリーに、ローレンス・スノーデン海兵隊中将がお座りです。70年前の2月、23歳の海兵隊大尉として中隊を率い、硫黄島に上陸した方です。近年、中将は、硫黄島で開く日米合同の慰霊祭にしばしば参加してこられました。こう、仰っています。「硫黄島には、勝利を祝うため行ったのではない、行っているのでもない。その厳かなる目的は、双方の戦死者を追悼し、栄誉を称えることだ」。もうおひとかた、中将の隣にいるのは、新藤義孝国会議員。かつて私の内閣で閣僚を務めた方ですが、この方のお祖父さんこそ、勇猛がいまに伝わる栗林忠道大将・硫黄島守備隊司令官でした。これを歴史の奇跡と呼ばずして、何をそう呼ぶべきでしょう。熾烈に戦い合った敵は、心の紐帯が結ぶ友になりました。スノーデン中将、和解の努力を尊く思います。本当に、ありがとうございました。
戦後の日本は、先の大戦に対する痛切な反省を胸に、歩みを刻みました。みずからの行いが、アジア諸国民に苦しみを与えた事実から目をそむけてはならない。これらの点についての思いは、歴代総理と全く変わるものではありません。アジアの発展にどこまでも寄与し、地域の平和と、繁栄のため、力を惜しんではならない。みずからに言い聞かせ、歩んできました。この歩みを、私は、誇りに思います。焦土と化した日本に、子どもたちの飲むミルク、身につけるセーターが、毎月毎月、米国の市民から届きました。山羊も、2036頭、やってきました。米国がみずからの市場を開け放ち、世界経済に自由を求めて育てた戦後経済システムによって、最も早くから、最大の便益を得たのは、日本です。下って1980年代以降、韓国が、台湾が、ASEAN諸国が、やがて中国が勃興します。今度は日本も、資本と、技術を献身的に注ぎ、彼らの成長を支えました。一方米国で、日本は外国勢として2位、英国に次ぐ数の雇用を作り出しました。
こうして米国が、次いで日本が育てたものは、繁栄です。そして繁栄こそは、平和の苗床です。日本と米国がリードし、生い立ちの異なるアジア太平洋諸国に、いかなる国の恣意的な思惑にも左右されない、フェアで、ダイナミックで、持続可能な市場をつくりあげなければなりません。太平洋の市場では、知的財産がフリーライドされてはなりません。過酷な労働や、環境への負荷も見逃すわけにはいかない。許さずしてこそ、自由、民主主義、法の支配、私たちが奉じる共通の価値を、世界に広め、根づかせていくことができます。その営為こそが、TPPにほかなりません。しかもTPPには、単なる経済的利益を超えた、長期的な、安全保障上の大きな意義があることを、忘れてはなりません。経済規模で、世界の4割、貿易額で、世界の3分の1を占める一円に、私たちの子や、孫のために、永続的な「平和と繁栄の地域」をつくりあげていかなければなりません。日米間の交渉は、出口がすぐそこに見えています。米国と、日本のリーダーシップで、TPPを一緒に成し遂げましょう。
実は、いまだから言えることがあります。20年以上前、GATT農業分野交渉の頃です。血気盛んな若手議員だった私は、農業の開放に反対の立場をとり、農家の代表と一緒に、国会前で抗議活動をしました。ところがこの20年、日本の農業は衰えました。農民の平均年齢は10歳上がり、いまや66歳を超えました。日本の農業は、岐路にある。生き残るには、いま、変わらなければなりません。私たちは、長年続いた農業政策の大改革に立ち向かっています。60年も変わらずにきた農業協同組合の仕組みを、抜本的に改めます。世界標準に則って、コーポレート・ガバナンスを強めました。医療・エネルギーなどの分野で、岩盤のように固い規制を、私自身が槍の穂先となりこじあけてきました。人口減少を反転させるには、何でもやるつもりです。女性に力をつけ、もっと活躍してもらうため、古くからの慣習を改めようとしています。日本はいま、「クォンタム・リープ(量子的飛躍)」のさなかにあります。親愛なる、上院、下院議員の皆様、どうぞ、日本へ来て、改革の精神と速度を取り戻した新しい日本を見てください。日本は、どんな改革からも逃げません。ただ前だけを見て構造改革を進める。この道のほか、道なし。確信しています。
親愛なる、同僚の皆様、戦後世界の平和と安全は、アメリカのリーダーシップなくして、ありえませんでした。省みて私が心からよかったと思うのは、かつての日本が、明確な道を選んだことです。その道こそは、冒頭、祖父のことばにあったとおり、米国と組み、西側世界の一員となる選択にほかなりませんでした。日本は、米国、そして志を共にする民主主義諸国とともに、最後には冷戦に勝利しました。この道が、日本を成長させ、繁栄させました。そして今も、この道しかありません。
私たちは、アジア太平洋地域の平和と安全のため、米国の「リバランス」を支持します。徹頭徹尾支持するということを、ここに明言します。日本はオーストラリア、インドと、戦略的な関係を深めました。ASEANの国々や韓国と、多面にわたる協力を深めていきます。日米同盟を基軸とし、これらの仲間が加わると、私たちの地域は各段に安定します。日本は、将来における戦略的拠点の一つとして期待されるグアム基地整備事業に、28億ドルまで資金協力を実施します。アジアの海について、私がいう3つの原則をここで強調させてください。第一に、国家が何か主張をするときは、国際法にもとづいてなすこと。第二に、武力や威嚇は、自己の主張のため用いないこと。そして第三に、紛争の解決は、あくまで平和的手段によること。太平洋から、インド洋にかけての広い海を、自由で、法の支配が貫徹する平和の海にしなければなりません。そのためにこそ、日米同盟を強くしなくてはなりません。私たちには、その責任があります。日本はいま、安保法制の充実に取り組んでいます。実現のあかつき、日本は、危機の程度に応じ、切れ目のない対応が、はるかによくできるようになります。この法整備によって、自衛隊と米軍の協力関係は強化され、日米同盟は、より一層堅固になります。それは地域の平和のため、確かな抑止力をもたらすでしょう。戦後、初めての大改革です。この夏までに、成就させます。ここで皆様にご報告したいことがあります。一昨日、ケリー国務長官、カーター国防長官は、私たちの岸田外務大臣、中谷防衛大臣と会って、協議をしました。いま申し上げた法整備を前提として、日米がそのもてる力をよく合わせられるようにする仕組みができました。一層確実な平和を築くのに必要な枠組みです。それこそが、日米防衛協力の新しいガイドラインにほかなりません。きのう、オバマ大統領と私は、その意義について、互いに認め合いました。皆様、私たちは、真に歴史的な文書に合意をしたのです。
1990年代初め、日本の自衛隊は、ペルシャ湾で機雷の掃海に当たりました。後、インド洋では、テロリストや武器の流れを断つ洋上作戦を、10年にわたって支援しました。その間、5万人にのぼる自衛隊員が、人道支援や平和維持活動に従事しました。カンボジア、ゴラン高原、イラク、ハイチや南スーダンといった国や、地域においてです。これら実績をもとに、日本は、世界の平和と安定のため、これまで以上に責任を果たしていく。そう決意しています。そのために必要な法案の成立を、この夏までに、必ず実現します。国家安全保障に加え、人間の安全保障を確かにしなくてはならないというのが、日本の不動の信念です。人間一人一人に、教育の機会を保障し、医療を提供し、自立する機会を与えなければなりません。紛争下、常に傷ついたのは、女性でした。私たちの時代にこそ、女性の人権が侵されない世の中を実現しなくてはいけません。自衛隊員が積み重ねてきた実績と、援助関係者たちがたゆまず続けた努力と、その両方の蓄積は、いまや私たちに、新しい自己像を与えてくれました。いまや私たちが掲げるバナーは、「国際協調主義にもとづく、積極的平和主義」という旗です。繰り返しましょう、「国際協調主義にもとづく、積極的平和主義」こそは、日本の将来を導く旗印となります。テロリズム、感染症、自然災害や、気候変動――。日米同盟は、これら新たな問題に対し、ともに立ち向かう時代を迎えました。日米同盟は、米国史全体の、4分の1以上に及ぶ期間続いた堅牢さを備え、深い信頼と友情に結ばれた同盟です。自由世界第一、第二の民主主義大国を結ぶ同盟に、この先とも、新たな理由付けは全く無用です。それは常に、法の支配、人権、そして自由を尊ぶ、価値観を共にする結びつきです。
まだ高校生だったとき、ラジオから流れてきたキャロル・キングの曲に、私は心を揺さぶられました。「落ち込んだ時、困った時、目を閉じて、私を思って。私は行く。あなたのもとに。たとえそれが、あなたにとっていちばん暗い、そんな夜でも、明るくするために」。2011年3月11日、日本に、いちばん暗い夜がきました。日本の東北地方を、地震と津波、原発の事故が襲ったのです。そして、そのときでした。米軍は、未曾有の規模で救難作戦を展開してくれました。本当にたくさんの米国人の皆さんが、東北の子どもたちに、支援の手を差し伸べてくれました。私たちには、トモダチがいました。被災した人々と、一緒に涙を流してくれた。そしてなにものにもかえられない、大切なものを与えてくれました。――希望、です。米国が世界に与える最良の資産、それは、昔も、今も、将来も、希望であった、希望である、希望でなくてはなりません。米国国民を代表する皆様。私たちの同盟を、「希望の同盟」と呼びましょう。アメリカと日本、力を合わせ、世界をもっとはるかによい場所にしていこうではありませんか。希望の同盟――。一緒でなら、きっとできます。ありがとうございました。
戦死の妹、遺骨70年ぶり発見 保志門さん「長い間ごめんね」
沖縄戦体験者の保志門(ほしかど)繁さん(84)=浦添市=が3日、沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」の協力を得て、沖縄戦で亡くなった妹のものとみられる遺骨を八重瀬町新城の山中で発見した。保志門さんは戦後ずっと妹の遺骨を見つけて弔うことを気に掛けてきたが、戦後70年の節目でようやくその思いを果たした。ガマフヤーが遺族からの依頼を受けて遺骨を発見するのは初めて。見つかったのは子どもの頭蓋骨の一部で、保志門さんは「節ちゃん、長い間迎えることができなくてごめんね」と小さな遺骨に語り掛け、大切そうに両手で包んだ。
保志門さんは、沖縄戦で祖母、父、弟、妹の節子さんの4人を亡くした。当時6歳の節子さんは避難場所の八重瀬町新城の壕で弾に当たって即死。14歳だった保志門さんが壕近くの岩場の下に埋葬した。
家族の戦没場所はそれぞれ別々で、節子さん以外の遺骨は戦争直後に収集した。戦後、母から「妹の遺骨を必ず収骨しなさい」と言われていたが、うっそうと草が覆い茂る山に1人で入ることは難しく、なかなか収骨できずにいた。
保志門さんは「妹にニーニー(お兄さん)と呼ばれているようで戦後ずっと心が落ち着かなかった。孫を見るたびに節子を思い出していた」とずっと気に掛かっていた心中を明かす。
戦後70年の節目に、新聞で知ったガマフヤーの具志堅隆松代表に遺骨収集の協力を依頼した。沖縄大学の須藤義人准教授のゼミ生も作業に参加した。
保志門さんの「川の下流に向かって右側に家族で隠れた避難壕が三つ、左側に大きな岩があった。川には橋が架かっていた。その岩の根元に妹を埋葬した」との記憶を基に、4月19日から計4回にわたり埋葬場所を捜した。やぶをかき分け、斜面をロープで上り、3日目にようやく証言と一致する場所を捜し当てた。壕や岩の位置から保志門さんは「ここに違いない」と確信した。
4日目の作業は約5時間に及んだ。参加者が諦めかけていた時に子どもの頭蓋骨の一部が地表に現れた。
遺族からの依頼で遺骨探索に初めて携わった具志堅さんは「遺族の証言を基に遺骨を捜し出せたことは大きな可能性だ。継続して全身の骨を捜す」と話した。
保志門さんは「天国の父母にもやっと報告できる。胸のつかえが取れた。門中墓に納めたい」と語り、遺骨をなでた。(赤嶺玲子)
琉球新報社
最終更新:5月5日(火)10時37分
戦争で行けなかった修学旅行、70年越しの実現 兵庫の小学校
太平洋戦争末期の混乱で行けなかった修学旅行を70年ぶりに実現させようと、兵庫県の西志方国民学校(現・志方西小=加古川市志方町)の卒業生らが27日、1泊2日の赤穂市への旅行に出発した。出発前、本年度で83歳になる同級生14人が母校で集合写真に収まった。亡くなった級友らを悼み、そして思い出話に花を咲かせてバスに乗り込んだ。
【写真】70年前のクラス写真
国民学校2年生で太平洋戦争が始まり、終戦が迫る1945年3月に卒業した。当時いた87人の多くは亡くなったが、会社経営の三村正信さん(82)=志方町=が呼びかけ、各地の同級生に連絡が広がった。
バスの中、メンバーたちは6年生のとき、教諭が放った言葉を懐かしんだ。「今年の修学旅行は(近くの)高御位山へ日帰りです」
戦況の悪化は幼心に分かっていた。神戸から同い年の子たちが疎開にやって来た。姫路が空襲されて高御位山の上空が真っ赤に染まった。加古川にも米軍機が飛来して隣の小学校が狙撃された。「それでも、日本は勝つと信じてた」。
午後3時、赤穂市の旅館に着いて食事を楽しみ、当時を語り合った。「授業で山に入ったな。軍のために木材を運んだっけ。いつも腹が減っとった」「石けんがなくて、女子は友達同士で髪の中のシラミをつぶしたよね」
風呂に入り、カラオケに興じた。軍歌を歌って泣く人もいた。
三村さんは「物心がついたときは既に戦時。軍国主義に疑問は感じなかったが、今思えば不思議ですな。同級生と本音を語り合えるのも、終戦70年という節目なのかもしれません」と話した。(安藤文暁)
最終更新:5月5日(火)14時6分
B29迎撃機を研究=木製も、戦時設立の航空研究所―技術院資料などで判明

太平洋戦争の戦局が悪化した1943(昭和18)年、軍用機生産の中心地となっていた名古屋市に国が設立した航空機に関する研究所の概要が、複数の資料や取材で分かった。米戦略爆撃機B29の迎撃機や、物資不足を補うための木製機などの研究を行っていた。
この研究所は「財団法人名古屋航空研究所」。存在は一部で知られていたが、連合国軍総司令部(GHQ)による航空禁止令を受けて保管資料は処分・散逸したとみられ、実態は戦後ほとんど分からなくなっていた。
戦時中に科学技術政策を所管した政府機関「技術院」の初代総裁を務めた井上匡四郎が残した技術院の会議記録は、名航研の43年度の研究として16項目を列挙。最初に「高高度飛行用与圧胴体の構造」と記載されていた。
別の技術院資料には「(名航研は)昭和19年度においては、高高度機機体艤装(ぎそう)に関する研究を重点的に採り上げんとす」とあり、「この方面の研究は、現下最も要望されつつある問題」との記述もあった。
米軍は44年6月、空気の薄い1万メートルの高高度でも高出力を維持できるエンジンや与圧室を装備したB29で日本本土を初めて空襲。同11月以降、空襲を本格化させた。
名航研設立の43年夏までに、日本は開発中のB29についてかなりの情報を入手していたにもかかわらず、自国の技術開発は遅れ、対抗し得る迎撃戦闘機は開発できていなかった。
「日本軍用機事典」などの著書がある航空史家の野原茂氏は「B29迎撃には、与圧室やそのための機体構造が求められた。日本にはこれらを備えた戦闘機はなく、重点的に研究する必要があった」と指摘する。
一方、研究員だった篠原卯吉名古屋帝国大学教授(後の名古屋大学長)は、名航研が戦後改組された「名古屋産業科学研究所」(同市)の資料に「『木製機の迅速接着加工』などの研究をさせられた」と書き残していた。不足していたジュラルミンに代わる材料による機体製造を研究していたとみられる。
最終更新:5月5日(火)10時58分
ネパール国際緊急援助医療援助隊の活動(4月29日)
防衛省・自衛隊は、平成27年4月25日にネパールにおいて発生した地震の影響により、甚大な被害を被ったネパール政府の要請と、これに基づく日本政府の決定に基づき、4月28日、同国に対し国際緊急援助医療援助隊を派遣することとなり、先遣隊約20名が29日未明に日本(羽田空港)を出国しました。 陸上自衛隊は、今後先遣隊を含む約110名の医療支援要員の他、連絡調整要員を参加させ、現地において医療支援などを行う予定です。
【海上自衛隊の日】
4月26日(日)、「海上自衛隊の日」を記念して呉基地で行った満艦飾の様子を一部紹介します。
※海上自衛隊の日:昭和27(1952)年4月26日に海上自衛隊の前身となった海上警備隊が創設されたことにちなみ、平成25(2013)年4月26日に海上自衛隊の歴史と伝統を考える日として海上自衛隊において設けたものです。
【軍艦島アーカイブサイトがオープン】

長崎県長崎市の沖合に浮かぶ通称「軍艦島」(正式名称は「端島」)の歴史を伝えるサイト「軍艦島アーカイブス」が4月21日にオープンした。
西日本新聞(福岡県福岡市)が開設したこのサイトは、19世紀末から炭鉱開発が始まり、1974年の閉山とともに無人の島となった軍艦島を、古い写真と映像でたどるものだ。南北480m、東西120mという狭い土地に、最盛期には5000人以上が暮らし、当時の東京の9倍の人口密度を誇った軍艦島。この島がいかにして誕生し、そして無人化したのかを、全8話のストーリーで紹介している。
現在(4月22日)、軍艦島ヒストリーは3話まで公開されており、第1話の「軍艦島の出現」では、島の発見から三菱による買収、住環境の整備、さらに「軍艦島」という名前が付けられた経緯などを紹介。元・軍艦島住民から提供された貴重な写真が、多数掲載されている。ツイッターには、
「これは貴重な映像資料だ」
「バ、バトルシップアイランド…」
「写真onlyで説明なしの軍艦島本は見たことあるけど、波長が合わなくて結局買わなかった。それとは形態は違うけれど、写真に文章が自然と入ってくるものが欲しかったんだなぁ。・・・西日本新聞社さんナイスだぜ!」
など、称賛の声が相次いでいる。
軍艦島に関しては、これまでもネットでさまざまな試みが行われてきた。2013年にはGoogleが長崎市の許可を得て、立ち入りが禁じられている地域も含めて島全体を撮影し、それを同社の「ストリートビュー」に掲載した。また昨年11月には、西日本新聞が無人小型飛行機「ドローン」を駆使して撮影した4K画像(フルハイビジョンの4倍の解像度に相当)が、YouTubeで公開され、半年たった現在までに35万回以上も再生されるなど人気を博している。
前述の軍艦島アーカイブスのFacebookページは、すでに2万人以上に「いいね!」を押されている。世界遺産入りを目指す動きもある軍艦島に対し、ネット界からも熱い視線が送られているようだ。
(R25編集部)
※コラムの内容は、フリーマガジンR25およびweb R25から一部抜粋したものです
※一部のコラムを除き、web R25では図・表・写真付きのコラムを掲載しております

元グルカ兵(ネパール人)の証言
我々は世界最強の傭兵だ。
第二次大戦で英軍の傭兵の時、マレー軍を3時間で撃破した。
インド軍は1日で降参させた。
玉砕した日本軍の所に行ってさらに驚いた。日本軍は貧弱な武器なうえ食料も、わずかな米しかなく、日本軍の死体はみんなやせ細っていた。
戦友が死んだ時には泣かなかったが、敵である死んだ日本人を見て皆泣いた。
停戦の訳
インドで傭兵としてパキスタン軍と対峙してた時、遠くから歌が聞こえてきた。
知らない言葉の歌だったが味方じゃないことは確かなので銃をそちらに向けたとき、上官に殴り飛ばされた。
何がなんだかわからなかったが不思議なことに、パキスタン側でも銃声がやんでいた。歌声の主は数人の年寄りで、われわれに気づかないのか旗を持って一列で歩いてきていた。
われわれ側もパキスタン側もその数人のお年寄りが通り過ぎて見えたくなるまで一発の銃弾も発射しなかった。結局その日から2日間は戦闘は再開されなかった。
停戦命令も出ていないのにどうして戦闘がやんだのかわからずに、上官に聞きに言った。その年寄りたちが歌っていたのは日本の軍歌で持っていた旗は日の丸だということを聞いた。
その話を聞いてその夜は泣いた。
ものすごく泣いた。
その年寄りたちは第二次世界大戦で死んだ戦友を弔いに来ていたのだと知った。
こんな危険地帯なのに、第二次世界大戦から何年もたっているのに、戦友を弔うためにこんなところまで来てくれる人たちがいることに涙が出た。
あとから知ったが、パキスタン側もそれが日本人でかつてインド(パキスタン)独立のためにイギリス軍と戦った人たちだと知って敬意を表して戦闘を中断したそうだ。
この半年後、傭兵を辞めて日本に留学した。
たくさん勉強して日本語の読み書きも覚えた。
何年もたって日本のお酒が飲めるようになって、サクラを見ながら飲んでいたとき、サクラの花びらがコップに入った。
それを見て急に涙が出てきた。
あの年寄りたちのことを思いだした。
日本人が本当にうらやましい。
百田尚樹も尊敬する元零戦パイロットが安倍首相を批判!「戦前の指導者に似ている」と

4月3日、米「ニューヨーク・タイムズ」に、第二次世界大戦時、零戦のパイロットだった男性のインタビューが掲載された。原田要さん、98歳。元大日本帝國海軍エースパイロットである。
原田さんは真珠湾攻撃では上空直掩隊として艦隊上空を警戒し、セイロン沖海戦、ミッドウェー海戦に参加。ガダルカナル島の戦いで撃墜され、重傷を負いながらも帰国し、教官となって終戦を迎えた。総撃墜数は19機。自らの経験を記録したいくつかの著書を残している。
「Retired Japanese Fighter Pilot Sees an Old Danger on the Horizon(元日本人戦闘機飛行士は差し迫った古い危機をみる)」──そう題された「ニューヨーク・タイムズ」の記事は、長野で行われた原田さんの講演会の描写から始まる。彼はゆっくりと壇上に上がると、セピアに色あせた写真を掲げたという。それは、革のフライトジャケットを着込んだ、若かりし頃の自分の姿だった。そしてこう語った。
「戦争ほど恐ろしいものはありません」
「私は、あなたたちに私自身の戦争体験を伝えたい。若い世代に、私と同じ恐怖を体験させないために」
講演会のあと、原田さんは「ニューヨーク・タイムズ」のインタビューに応じている。
「私は零戦のコックピットから戦争を見ました。いまだに私が殺した兵士たちの顔はよく覚えています」
「戦場でのかつての敵兵もまた、私たちと同じように父であり、息子なのです。彼らを憎んだり、知りもしないでいることはできません」
「戦争は人間から人間性を奪うのです。全くの他人を殺すか、殺されることを選ばざるをえない状況に置かれることによって」
「私は気がつきました。戦争が、私を人殺しへと変えてしまった。私はそうありたかったわけではないのに」
人を殺したくない、そう思っていても、人を殺してしまっている──戦場の現実を知る当事者の言葉は、重い。記事には書かれていないが、原田さんの著書『最後の零戦乗り』(宝島社)には神風特攻のエピソードも記されている。
1943年1月、原田さんは霞ヶ浦航空隊に教官として着任し、海軍兵学校出身者3名を受け持つことになった。そのなかの一人が関行男大尉(2階級特進後、中佐)だった。初の神風特攻により、レイテ沖海戦で戦死した軍人である。そして、原田さん自身もまた、霞ヶ浦航空隊にいたころ、「参謀肩章を付けたお偉いさん」から特攻の志願を促されたことがあったという。ガダルカナルでともに死の淵に立った戦友は、「命令されたら仕方がない。こうなったら俺は志願するよ」と言って、戦死した。原田さんは「俺はいやだ」と志願しなかったと書いている。
〈ミッドウェーでの「巻雲」での経験、ガ島から病院船での出来事、とにかく私は、
「命を大事にしなくては」
と、最後まで、命はむだにしちゃいけないと思っていた。〉(『最後の零戦乗り』より)
──このエピソードを聞いて、なにかを思い出さないだろか。海軍のエースパイロット、教官に転身、「命を大事に」。そう、百田尚樹『永遠の0』の主人公、宮部久蔵である。原田さんと宮部久蔵は、操縦練習生出身という点でも同じだ。
実は、百田と原田さんは少なくとも一度、会って話したことがあるらしい。『永遠の0』出版後の2010年に、百田はツイッターでそのことをつぶやいていた。実際、そんな縁もあり、前出の『最後の零戦乗り』の帯に百田が推薦文を寄せている。
原田さんは、百田に会ったときに「(主人公の宮部は)いろいろな零戦搭乗員の話を聞いてから作った、ひとりの偶像です。このなかには原田さんも入っています」と聞かされたという。しかし、安倍首相を礼賛し、タカ派発言を連発する百田とは対称的に、原田さんはインタビューのなかで、安倍首相の歴史認識や戦争への考え方に対して、こう「鋭いジャブ」を入れている。
「安倍首相は必死で日本の戦争放棄を取り消そうとしたがっているように見える」、そして、「戦後の長い平和がひとつの達成であったということを忘れているように思えてならない」と。
積極的平和主義の名の下に、日本を再び「戦争ができる国」にしてしまった安倍首相。その口から常日頃飛び出すのは「有事にそなえて」「中国の脅威は予想以上」という国防論だ。そこからは、原田さんが語る「全くの他人を殺すか、殺されることを選ばざるをえない状況に置かれる」「戦争が、私を人殺しへと変えてしまった」という生々しい血の匂いと、背負うことになる罪の重さは、まったく感じられない。
原田さんはインタビューで、「安倍首相ら最近の政治家は戦後生まれだから、どんな犠牲を払ってでも戦争を避けなければならないということを理解していないのです」と語り、そして、こう続けている。
「その点で彼らは戦前の指導者たちと似ているんです」
戦後、眠れないほどの悪夢に苦しめられたと語る原田さん。夢のなかで彼が見続けていたのは、自分が撃墜したアメリカの飛行士たちの怯える顔だった。自身の戦争体験をようやく語れるようになるまでに、何年もの時がかかったという。
記事は、原田さんのこんな言葉で締めくくられている。
「私は死ぬまで、私が見てきたものについて語りたいと思う」
「決して忘れないことが子どもたち、そして子どもたちの子どもたちを戦争の恐怖から守る最良の手段なんです」
安倍首相や百田に、その「恐怖」は想像もできないらしい。
(梶田陽介)
【 昭和の日 】
しょうわのひ
【4月29日】なぜ「みどりの日」が「昭和の日」に改名されたの?その歴史的な意味とは
4月29日って、いつから「昭和の日」になったのだろう?
・4月29日といえば、少し前までは「みどりの日」と呼ばれていた日だったのですが、最近は「昭和の日」に改名されたようです。ちなみに「みどりの日」は5月4日に移動したのだそうです。「みどりの日」が「昭和の日」に改名された理由には、歴史的な意味もあり、この祝日の改名の際には賛否両論あったそうです。
昭和の日(しょうわのひ)は、日本の国民の祝日の一つである。日付は4月29日。
多くの国民の要望を受けて、平成17年に国会で「国民の祝日に関する法律」(祝日法)が改正。平成19年(2007)より「昭和の日」とすることになったのです。
・「昭和の日」が制定されたのは実は最近の話…。確かに、幼少期の頃の記憶を辿ると、4月29日は「みどりの日」とされていたように記憶している人も少なくないのでは…。
もともとは昭和天皇・裕仁氏の誕生日が、崩御後に「みどりの日」とされてきた
この日は、裕仁氏が天皇として存命中には、戦前・戦中は「天長節」、戦後は「天皇誕生日」という法定祝日でした。
1989年(昭和64年)1月7日の昭和天皇崩御により、同年以降の4月29日はそれまでの天皇誕生日としては存続できなくなり、祝日法の天皇誕生日に係る項を改正する必要が生じた。
・天皇を務める人物が、先代の裕仁氏から、今の天皇である明仁氏に移行したのが1989年。このとき、4月29日は天皇誕生日ではなくなった。
天皇誕生日は今上天皇の誕生日である12月23日に改められることとなったが、ゴールデンウイークの一角を構成する祝日を廃止することによる国民生活への影響が懸念された
・そのため、昭和天皇・裕仁氏に関連付けた休日として「4月29日」を祝日のままにしておこうという話になったようです。
それまでの天皇誕生日である4月29日を「生物学者であり自然を愛した昭和天皇をしのぶ日」として「緑の日」とすることとなった。
・「みどりの日」とされていた時代でも、この「みどりの日」という祝日名は、やはり昭和天皇に関連した名称だったといえよう。
そして2007年、「みどりの日」から「昭和の日」に名称が変更された。
四月二十九日を「昭和の日」にとの言論は、「みどりの日」制定以来各界でなされ
・当初、「みどりの日」のまま、名称は変更しなくてもよい、との立場だった政府も、徐々に「昭和の日」の設定を真剣に議論するようになっていった
2007年よりこの日は「昭和の日」と改めらました。
それは、「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いを致す」と言う意味合いからです。
同年以降の4月29日は「昭和の日」、従前の「みどりの日」は5月4日に移動した。
一方で「昭和の日」という名称には、複雑な思いを持つ意見の人たちもいて、賛否両論がある
・一方で「昭和の日」という名称には、複雑な思いを持つ意見の人たちもいます。そもそも、昭和時代といえば、戦争という暗い時代でもありましたから…。先の大戦でつらい思いをした多くの日本国民、そして韓国などのアジア諸国の人たちにとっては、「昭和の日」という名称にたいして複雑な思いを持つのも事実だろう。
「昭和」の時代にたいする国民の思いや認識はさまざまであり、とても「こぞって祝う」ことはできない事柄
・確かに、昭和時代といえば、戦争という暗い時代でもありましたから…。
【日本人なら知っていないといけない話】

日本の敗戦の年である昭和20年、戦後の混乱の中で、国民は大変な苦しみに耐え忍んでいました。
特に食糧難は深刻でした。
必要な栄養は配給では到底摂取出来ず、ヤミで補うという状況でした。
人々はたけのこの皮を1枚ずつはぐように、自分の衣類や家財などを少しずつ売って食いつないでいくいわゆる「竹の子生活」という苦しい暮らしをしていました。
また、この年は明治43年以来の不作の年となりました。
天候不順、戦争による労働力不足、粗末な農機具、肥料や農薬生産の減少により、米の収穫が例年より40パーセント近くも減少しました。
しかも敗戦により国家として成り立っていない中、農民は収穫した作物を政府に出さずに闇ルートに横流ししていました。
その結果、政府の配給米が底をつく状況になりました。
大蔵大臣が「食糧がすぐに輸入されなければ1千万人の日本人が餓死するであろう」と述べ、国民は迫りくる飢餓の恐怖におびえていました。
このような中、国民の食糧事情に最も胸を痛めていたのが昭和天皇でした。
昭和20年12月、政治家の松村謙三は宮中からお召しがあり、天皇陛下からお言葉がありました。
「戦争で苦しんだ国民に、さらに餓死者を出すことは堪え難い。皇室の御物の中には国際的価値のあるものもあると聞く。その目録を作製させたから、米国と話してこれを食糧に替えたい」
とのお言葉でした。
さっそく幣原首相がマッカーサーに面会してこれを伝えると、感動したマッカーサーは
「自分としても、米国としても、その面目にかけても御物を取り上げることはできない。断じて国民に餓死者を出すことはさせないから、ご安心されるよう申し上げて下さい」
と答えたと言います。
食糧を求める国民の声はますます高まっていました。
昭和21年5月19日には食糧メーデーが行われました。
参加者は25万人といわれ、坂下門から皇居内にも群集が押し入りました。
教科書にも載っている
「国体は護持されたぞ。朕はたらふく食っているぞ。汝、臣民飢えて死ね。御名御璽」
というプラカードはこの時のものです。
これは共産党によるものでした。
プラカードを持った者は不敬罪に問われました。
皇居前広場ではトラックを3台並べその上にテーブルをのせて演壇がつくられました。
演説が続き、最後に共産党の指導者・徳田球一が演壇に立ちました。
徳田はおもむろに皇居を指さし、「オレたちは餓えている。しかるに彼らはどうだ」と集まった人々に訴えました。

(食糧メーデー)
メーデーの翌日、マッカーサーは「規律なき分子がいま開始している暴力の行使は、今後継続を許さない」と警告し、食糧メーデーはGHQの命令で収拾しました。
そしてマッカーサーは吉田茂をGHQに招き「自分が最高司令官である限り、日本国民は一人も餓死させない」と約束しました。
その約束通りGHQは6~7月にかけて20万トンの輸入食糧を放出し、8~9月にはそれぞれ20万トンの食糧が放出されました。
これによって日本国民は餓死という最悪の危機を乗り越えることができました。
昭和天皇は失意に沈んだ日本国民を元気づけるべく、昭和21年から昭和29年まで沖縄を除く日本全国を巡幸されました。
大阪や名古屋では数千人という群衆が陛下に殺到し、陛下は靴を踏まれボタンを引きちぎられ大混乱でした。
それでも「今日も人並みが崩れたね」と嬉しそうに語ったそうです。
大戦後は世界の食糧事情が悪化していました。
中国・インドでは飢餓が起こり、ヨーロッパも飢餓になりそうでした。
日本は敗戦国として飢餓を強いられても不思議ではない状況でした。
それにもかかわらず国民が餓死から救われたのは昭和天皇の役割が大きかったのです。
昭和天皇は餓えに苦しむ国民を思い、皇室財産を差し出して食糧に替え、国民を餓死から救いたいと申し出ました。
その仁愛の心がマッカーサーの心を動かし、GHQによる食糧放出が行われたのです。
当時の国民はこのことを知る由もありませんでした。
今も多くの国民はただ米軍が食糧を供給してくれたと思っているようです。
実はその陰には国民の身の上を思う昭和天皇の存在があったのです。
こういう真実を私たちは語り継いでいかなければなりません。
幸食研究所 ひふみ塾
http://www.kousyoku.net/ より転載

「戦争はやめよう」日本で多くの反響を呼ぶ「清志郎の手紙」

音楽評論家である湯川れい子さんがtwitterで公開した、忌野清志郎さんからの手紙をご紹介します。
日本のロックミュージシャンであった故・忌野清志郎氏が14年前に書いたメッセージがいま注目を集めています。重要なメッセージが込められているように思います。
忌野清志郎氏からのメッセージ
地震のあとには戦争がやってくる。
軍隊を持ちたい政治家がTVででかい事を言い始めてる。
国民を馬鹿にして戦争に駆り立てる。
自分は安全なところで偉そうにしているだけ。
阪神大震災から5年。
俺は大阪の水浸しになった部屋で目が覚めた。
TVをつけると5ヶ所程から火の手がのぼっていた。(これはすぐに消えるだろう)と思ってまた眠った。6時間後に目が覚めると神戸の街は火の海と化していた。
この国は何をやってるんだ。
復興資金は大手ゼネコンに流れ、神戸の土建屋は自己破産を申請する。
これが日本だ。私の国だ。
とっくの昔に死んだ有名だった映画スターの兄ですと言って返り咲いた政治家。
弟はドラムを叩くシーンで、僕はロックンロールじゃありませんと自白している。
政治家は反米主義に拍車がかかり、もう後戻りできゃしない。そのうちリズム&ブルースもロックも禁止されるだろう。
政治家はみんな防衛庁が好きらしい。
人を助けるとか世界を平和にするとか言って、実は軍隊を動かして世界を征服したい。
俺はまるで共産党員みたいだな。普通にロックをやってきただけなんだけど。
そうだよ。売れない音楽をずっとやってきたんだ。
何を学ぼうと思ったわけじゃない。
好きな音楽をやってるだけだ。
それを何かに利用しようなんて思わない。せこい奴らとは違う。
民衆をだまして、民衆を利用して、いったい何になりたいんだ。
予算はどーなってるんだ。
予算をどう使うかっていうのは、いったい誰が決めてるんだ。
10万円のために人を殺すやつもいれば、
10兆円とか100兆円とかを動かしている奴もいるんだ。
いったいこの国は何なんだ。
俺が生まれ育ったこの国のことだよ。
どーだろう、・・・この国の憲法第9条は、まるでジョン・レノンの考え方みたいじゃないか?
戦争を放棄して世界の平和のためにがんばるって言ってるんだぜ。
俺たちはジョン・レノンみたいじゃないか。
戦争はやめよう。
平和に生きよう。
そして、みんな平等に暮らそう。
きっと幸せになれるよ。
命のメール 365日 24時間 受付致します。 Apex product 命を守り隊 !!
「死にたい」「消えたい」「生きることに疲れた」など、あなたのそんな気持ちを素直にメールして下さい。
命の電話で専門の相談員が受け止める事も出来ますが、何をもって専門家なのですか?エリートの挫折を味わった事のない専門の相談員様は、色々なケースには当たり前の回答しかしません。私どもは、苦労苦労で亡くなった先人の魂で寄り添う相談員になれたらと思っています。代表は、それはそれは苦労人の還暦過ぎた親父さんですが、あなたの状況を一緒に整理し、必要な支援策などについて一緒に考えます。知識人ですから安心して連絡下さい。皆んなで対処すれば何とかなるから頑張らないで生きてみましょう。



 Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します
Apex product エイペックス プロダクト
人を喜ばせたいという気持ち
人との出会いが1番の財産です
みなさまのお役に立てるようにサポート致します